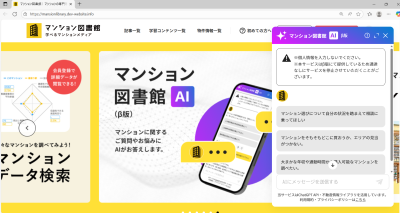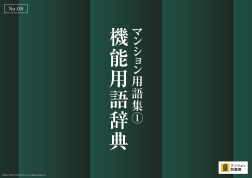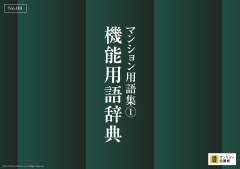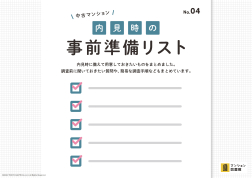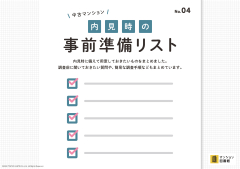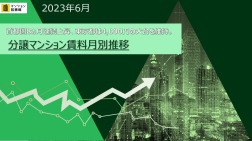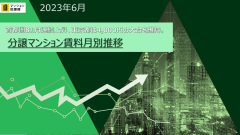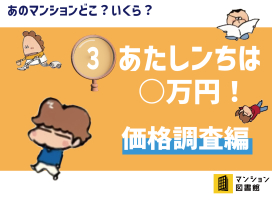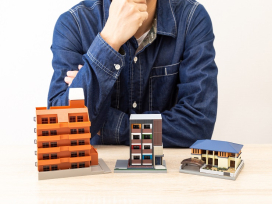全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.03.24
登録日:2025.03.24
火災報知器が鳴ったらどうする?適切な対応方法を解説

火災報知器は一般的な住宅で設置が義務付けられていて、火災の発生を音で知らせてくれます。鳴ったとき冷静に対処できるようにすることが、命を守ることにつながります。
一方で「火災報知器が鳴ったらどうすればいい?」「誤作動のときの止め方は?」など、疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、火災報知器が鳴ったときの基本対応を紹介します。火災でなかったときの対処法や誤作動の原因、メンテナンスの必要性とあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
火災報知器が鳴ったらするべき基本対応

火災報知器が鳴ったらするべき基本対応
自分や家族の命を守るためには、火災報知器が鳴ったときすぐに対応する必要があります。
・火災の有無を確認する
・周囲に知らせて避難する
冷静に対処するために、基本の対応をチェックしておきましょう。
火災の有無を確認する
火災報知器が鳴ったら、慌てずに火災が発生していないか確認します。火や煙は危険なので、近づきすぎないように注意してください。
自宅以外の火災報知器が鳴っていることに気づいたら、消防機関に通報しましょう。屋外から見てわかるくらいに火の勢いが強い場合は、近づいてはいけません。
周囲に知らせて避難する
家族や近隣住民に知らせながら、素早く屋外に避難しましょう。マンションの場合、閉じ込められる可能性があるのでエレベーターは使用できません。安全が確保できたあとは、消防機関に通報します。
天井に火が届かないくらいの小規模な火災なら、初期消火を試みるのも選択肢の一つです。備え付けの消火器や濡らしたバスタオルを使用することで、火が消せる可能性があります。ただし、火が天井に達している場合は、諦めて屋外に避難しましょう。
鑑定士コメント
火災報知器が鳴っても、消防機関などに連絡がいくことはありません。火災が発生した場合は、電話で119番に通報する必要があります。もしスマートフォンなど電話を所持していないときは、周囲の人に頼んでください。ただし、老人ホームといった一部の施設には、「火災通報装置」が備わっていることがあります。ボタンを押すだけで消防機関に通報できるので、いざというときは利用しましょう。
火災報知器が鳴ったけど火災ではなかったときの対処法

火災報知器が鳴ったけど火災ではなかったときの対処法
火災報知器が鳴っても火や煙が発生していない場合、以下の対処法を試してください。
・誤動作の原因を特定する
・警報音を停止する
大きな音がでても慌てないように、冷静に対処することが大事です。
誤動作の原因を特定する
まずは火災報知器がなぜ鳴ったのか調べます。以下のような原因が考えられるので、一つずつチェックしていきましょう。
・小さな虫や汚れ
・結露
・電池切れ
・経年劣化
・調理のときに発生する煙
・くん煙式の殺虫剤
・スプレー式殺虫剤
・加湿器から発生する蒸気や湯気
・エアコンの温風による急激な温度上昇
煙を感知する煙式の場合、火災以外の煙や湯気に反応することがあります。窓を開けたり換気扇を回したりして、原因を取り除いてください。
警報音を停止する
警報停止スイッチを押したり、引きひもを引いたりすることで警報音は止まります。15分ほどすれば機能は復旧するので、特別な操作はいりません。
警報停止スイッチや引きひもが見当たらない場合は、火災報知器を外して電池を取り外します。しばらく様子を見てから、電池を入れ直してもとの状態に戻しましょう。
鑑定士コメント
火災報知器が鳴ったときは、スマートフォンなどから119番に通報しましょう。助けが必要なときの緊急通報につながるため、消防車や救急車を呼べます。公衆電話には緊急通報ボタンがあり、硬貨やカードがなくても通報が可能です。ただし、119番はあくまで緊急通報なので、火災が発生していない場合はかけてはいけません。
火災報知器が誤動作で鳴った原因

火災報知器が誤動作で鳴った原因
火災報知器が誤作動で鳴ったとき、原因を取り除かないとまた繰り返す可能性があります。
・火災報知器に汚れや虫が入った
・火災報知器の電池が切れた
・火災報知器の経年劣化
考えられる原因と対処法をまとめました。
火災報知器に汚れや虫が入った
火災報知器に汚れや小さな虫が入り、火災報知器が誤作動しているケースです。掃除機の隙間ノズルを使って、煙検知部を2周以上吸い取ると原因を取り除けます。
警報部を掃除機で吸い取るのはNGです。掃除機で吸い取ったあとは、警報停止ボタンを押して動作を確認しましょう。それでも警報音が鳴る場合は、汚れや虫以外の原因が考えられます。
火災報知器の電池が切れた
火災報知器の電池が切れたとき、警報を鳴らす機種は少なく有りません。電池の寿命は約10年が目安なので、経過している場合は電池切れが考えられます。
取り外して電池を交換するか、火災報知器そのものを交換します。具体的な交換方法は機種によって異なるため、説明書やメーカーの公式サイトで確認してください。
火災報知器の経年劣化
火災報知器の経年劣化によって、誤動作が発生するケースです。熱を感知する差動式の感知器の場合、「リーク孔」の目詰まりが誤作動の原因になります。
経年劣化を放置していると、誤作動だけではなく火災を正しく感知しない可能性があるため注意が必要です。経年劣化で寿命を迎えた場合は、新しい火災報知器に交換しましょう。
火災報知器の種類

火災報知器の種類
火災報知器は主に以下の2種類に分けられます。
・煙式
・熱式
それぞれの特徴を紹介するので、ぜひチェックしてください。
なお、天井高が20m以上の場所に設置が向いている炎を感知するタイプの火災報知器もありますが、そちらは下記の記事にて紹介しています。
火災報知器設置義務とは?場所・住宅タイプ別の条件や罰則を紹介
煙式
煙式(光電式)は、火災で発生した煙を感知するタイプの火災報知器です。火災では熱よりも先に煙が発生するため、熱式より早期に発見できます。
住宅への設置が義務付けられているのは、煙式の火災報知器です。料理の際に発生する煙や湯気を感知する可能性があるため、キッチンなどには向きません。煙式の火災報知器は、以下の種類に分類できます。
一般的な住宅で使用されるのは光電式スポット型感知器です。光電式分離型感知器は2種類の感知器間で発生する煙を感知できるため、廊下やホールなど広い空間に適しています。
熱式
熱式の火災報知器は、火災によって上昇する熱を感知します。煙で誤作動を起こす心配がないため、キッチンなど湯気や煙が発生しやすい場所におすすめです。
短時間の急激な温度上昇などで、誤作動を起こす可能性があります。エアコンの送風口と近いと誤作動しやすいので、設置場所には注意しましょう。熱式の火災報知器は、以下の種類に分かれます。
差動式スポット型感知器は丸いドーム型が多く、価格がリーズナブルなのが特徴です。定温式スポット型感知器は一定以上の温度になったとき感知するため、キッチンや脱衣所など温度が上昇しやすい場所に向いています。
火災報知器が適切に作動するためのメンテナンスの必要性

火災報知器が適切に作動するためのメンテナンスの必要性
火災報知器を適切に作動させるためには、メンテナンスが必要です。
・点検の重要性
・火災報知器の交換時期
万が一の火災に備えるために、チェックしておきましょう。
点検の重要性
火災報知器に不具合が発生すると、火災を正常に感知できません。いつの間にか鳴らなくなっているケースもあるため、定期的な点検が必要です。
半年に1回ほど引きひもを引っ張るか警報ボタンを押して、正常に作動するか確認します。センサー部分の汚れを落としておくなど、あわせて定期的な掃除をするとよいでしょう。
火災報知器の交換時期
住宅用の火災報知器の交換時期は10年が目安です(※)。寿命によって経験劣化が発生して、正常に作動しなくなる可能性があります。
本体に記載された製造年を確認して、10年を過ぎていれば交換しましょう。交換後は本体に使用開始年月を記載しておけば、いつ交換すべきか簡単に確認できます。
※参照:独立行政法人国民生活センター
まとめ:火災報知器が鳴ったら落ち着いて対応しよう

まとめ:火災報知器が鳴ったら落ち着いて対応しよう
火災報知器が鳴ったら、まず火災が発生していないか確認します。消防機関に通報する、周囲に知らせて避難するなど、落ち着いて対応することが重要です。
一方で火災報知器が誤作動で鳴ることもあります。誤作動の原因を特定したうえで、警報音を停止してください。
また、メンテナンスを怠ると、いざ火災が発生したときに火災報知器が作動しないことがあります。自分や家族の命を守るためにも、定期的な点検や交換を行いましょう。
#火災、#停止、#ボタン、#発生

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
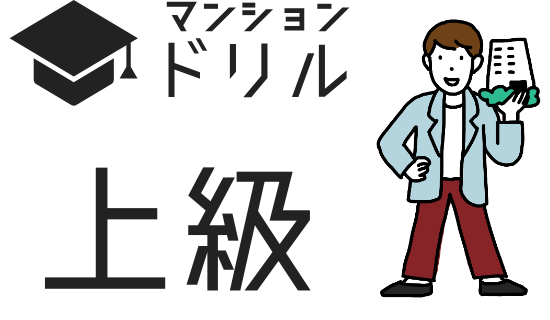
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。