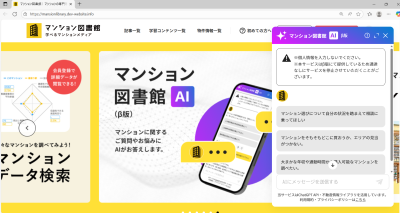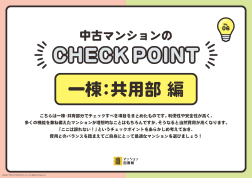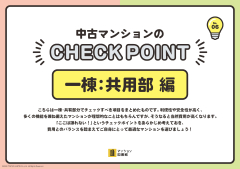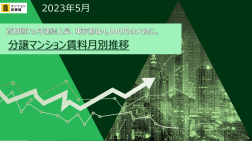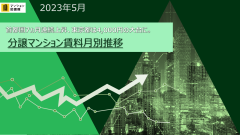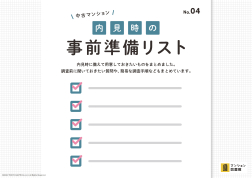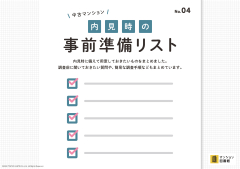全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.10.24
登録日:2023.07.20
液状化現象とは?発生のメカニズムと起こりやすい土地の条件と対策を徹底解説

住宅を新しく建てる方にとって、土地の地盤が安全かどうかは気になるものです。地盤が緩いと、地震により液状化現象が引き起こされ、生活に大きな支障が出ます。
そこで、本記事では、液状化現象が発生する仕組みや液状化リスクの判定方法を解説します。今後、居住予定の地域の液状化リスクを確認し、万が一の事態に備えましょう。
【この記事でわかること】
・液状化は地震による振動で地盤の一部が液体状に変わる現象のこと
・砂土質の地盤は砂粒の大きさが揃っているため液状化リスクが高い
・土地の購入前にハザードマップや地盤調査を活用し、リスクの低い地域を選ぶことが重要
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
液状化現象とは何か

液状化現象とは何か
液状化とは、地震による震動で地盤が揺さぶられ、地盤の一部が液体状に変わる現象のことです。液状化は、主に同じ大きさや同じ成分の砂でできた地盤が、地下水などの水分で満たされている場合に起こりやすいといわれています。
地盤が液状化すると、水の比重より重い建物が傾いたり沈んだりすることがあるため大変危険です。また、水の比重より軽いマンホールなどが浮き上がり、地面のなかにある下水管や水道管などがダメージを受ける場合もあります。
そのほか、地面の割れ目から水と土が地表に噴き出る噴砂(ふんさ)現象も見られるなど、液状化は地震発生時に起こる可能性のある被害です。
土地の購入を考えている場合は、どのような場所で液状化が起こりやすいか・購入予定の土地が液状化する可能性がないかを事前に調べておくとよいでしょう。
液状化が発生する仕組み

液状化が発生する仕組み
液状化現象は、以下の流れで発生します。
平常時では、砂の粒子が緩く結合しており、隙間は水で満たされている状態です。地震が起きると、砂粒同士の結合が崩れてしまい、粒子が水や空気中に浮いた状態となります。そして、バラバラになった砂粒は沈降し、水や空気だけが浮上するという仕組みです。
砂粒が下に沈んで密な状態となり、地盤全体の体積が減ることから、地表面が陥没したり沈んだりします。さらに、砂や水が噴き上がる、噴砂・噴水現象が起きることもあるため注意が必要です。
砂土質の地盤は砂粒の大きさが揃っており、圧力が加わることでかみ合わせが外れやすいため、液状化リスクが高いとされています。
鑑定士コメント
過去の事例では、一度液状化が発生した場所では、再度液状化が発生しやすくなります。液状化によって地盤の中の水が噴き出しても、地盤が十分に固まることはなく、かえって緩んだとの計測報告もあります。また、本震で液状化した場所が、余震によって再液状化したケースもありますので、過去の履歴の調査も必要でしょう。
液状化しやすい地盤の特徴

液状化しやすい地盤の特徴
液状化しやすい地盤の特徴には、砂質の土が地下水に浸かっていてゆるい状態であることが挙げられます。
具体的には以下の数値(※)を満たす場合、液状化しやすいと考えられています。
・地盤の強度を表す「N値」が20以下
・地表面からの深さが15m〜20mより浅い
・砂の粒の大きさが均一かつ、大きさが0.25mm〜0.5mm程度
N値とは、土の締まり具合や強度を表し、標準貫入試験によって求められる値です。
以上の特徴を満たした地盤において、震度5以上(※)の揺れが起こると、液状化が発生する可能性は高くなります。
なお、液状化の起こりやすい土地は、大きく分けて以下の7種類です。
2011年の東日本大震災では、千葉県浦安市をはじめとする過去50~60年以内に作られた埋立地で、重大な液状化の被害が起きました。
埋め立てから長期間が経過した土地や、過去に液状化した土地でも再び液状化が発生するリスクがあるため注意が必要です。
※参照:神奈川県ホームページ
液状化が起こりやすい土地の判定方法

液状化が起こりやすい土地の判定方法
液状化現象の被害を避けるために、液状化が起こりにくい土地に住むことが重要です。
今後、住宅を建てる方は、土地の判定方法を知って液状化リスクの少ない土地を選んでください。
・土地条件図を見る
・ハザードマップを活用する
・ボーリング調査で調べる
・自治体の液状化相談窓口で相談する
土地条件図(国土地理院)を見る
簡易的な手法であるため、専門的な知識がなくても問題ありません。
国土地理院が公表している土地条件図を活用することで、液状化リスクを把握できます。土地条件図に記載されている数値データから、地域ごとの液状化の発生傾向を調べましょう。
液状化だけでなく、洪水や地震などの災害リスクも確認できるため、住む地域を検討している方は一度利用してみてください。
ハザードマップを活用する
国土交通省が提供する、ハザードマップを活用することで液状化が発生しやすい地域を確認できます。
はじめに、国土交通省のハザードマップポータルサイトにアクセスします。「重ねるハザードマップ」に住所を入力し、「すべての情報から選択」をクリックしてください。
「土地の特徴・成り立ち」の項目から「地域区分に基づく液状化の発生傾向図」を選択しましょう。その後、地域ごとに液状化の発生傾向の強弱が5段階で表示されます。
ハザードマップは液状化リスクだけでなく、洪水による水害リスクや避難情報を確認できます。
以下の記事で、洪水ハザードマップの見方や入手方法などを解説しています。居住予定の地域の災害リスクを把握して、万が一の災害に備えてください。
ボーリング調査で調べる
ボーリング調査による土地の調査も、液状化しやすい土地を見分けるうえで役立ちます。ボーリング調査では、地面に穴を掘ることで地盤の強度や地質などを調べられるためです。
具体的には、地面に円筒形状の孔をあけるため50回の打撃を加え、貫入した深さに応じて「N値」を算出し地盤の強度を測ります。また、貫入の過程で採取した土の分析により、地盤の特性や性質を把握することも可能です。
このボーリング調査によって、液状化しやすい土地かどうかを判別しやすくなります。
自治体の液状化相談窓口で相談する
役所の窓口やホームページを活用すれば、地盤の特性や土地の履歴などが調べられるため、液状化の可能性を知ることができます。
また、窓口では過去の地形図のほか、地盤調査データなどの閲覧も可能です。過去の地形図や土地条件図などを調べることで、土地の成り立ちが読み取れるため、液状化しやすい土地かどうかをおおむね把握できます。
地域によっては、液状化の予測図やボーリング柱状図などを、ホームページで確認することも可能です。窓口に出向く前に、各自治体のホームページを一度確認しておくとよいでしょう。
鑑定士コメント
本文に前述した通り、液状化は地盤が緩く、地下水位が浅い場所で発生しやすいと言われています。一方で、地下水位が深い場所や地盤が硬い場所、粘性土地盤や砂礫地盤では発生の可能性は低いです。元々、河川や泥だった場所や、干拓や盛土など人工地盤の場所では液状化が起こりやすいため、過去地図などで地歴を確認し、注意しましょう。
液状化の影響

液状化の影響
液状化現象が、生活に及ぼす影響はさまざまです。液状化によって起こる被害は、主に4つに分類されます。
・噴水や噴砂
・建物への被害
・道路への被害
・ライフライン施設への被害
噴水・噴砂が発生する
液状化現象により、噴水や噴砂が発生する場合があります。
2011年の東北地方太平洋沖地震では、主に埋立地等で液状化が発生しました。具体的には、 地盤沈下や噴砂によって戸建住宅が傾いたというケースが報告されています。
また、過去には噴水や噴砂にともなう地割れに落ちて、死亡したと考えられる事例もあります。
このように、噴水や噴砂によって地盤沈下や地割れが発生することにより、命を落とす場合もあるのです。
建物への被害が起こる
住宅やマンションなどの建物に影響を及ぼすこともあります。液状化現象によって地盤が傾くことで、建物の傾斜や沈下が起こる場合があるためです。
実際に、1964年に起きた新潟地震ではビルの崩壊が発生しています。液状化現象が起きると、ビルや住宅などの建物を支える力が失われ、沈下する場合があるのです。
ほかにも隙間風の発生や、窓やドアの開け閉めの不具合といった住宅の機能障害を引き起こす場合もあります。建物の基礎部分にひび割れが発生するケースも珍しくありません。
道路への被害が起こる
地盤がやわらかくなることによって、道路の通行が困難になる場合もあります。
1983年に青森県から秋田県の日本海沿岸で起きた日本海中部地震においては、道路の変形や蛇行が発生しました。
道路が変形すると転倒等の事故が起こるだけでなく、避難や救助活動がスムーズに行えなくなることによる被害拡大のリスクも生じます。
ライフライン施設への被害がおこる
水道・ガス・電気などのライフラインにも支障が出ます。
2024年に発生した能登半島地震をはじめ、ライフライン施設が被害を受けたことにより、長期的に使用できなくなるケースが多数発生しました。
このように、液状化現象による被害が人々の地震後の生活に及ぼす影響は非常に大きく、多種多様です。さまざまな被害が複合的に発生することで、復旧までにかかる期間はより長期に及ぶことになります。
液状化現象への対策

液状化現象への対策
液状化現象に対し、わたしたちにできる対策にはどのようなものがあるのでしょうか。以下4つについて順に解説します。
・ハザードマップでリスクの低いエリアを選ぶ
・購入前に地盤調査を実施する
・地震保険を確認する
・家具の固定や備蓄品を用意する
ハザードマップでリスクの低いエリアを選ぶ
これから土地を選ぶという場合は、ハザードマップを活用して液状化のリスクが低い土地を選ぶことが大切です。
ハザードマップとは、液状化や地震による建物倒壊の危険度を、地図上に示したもののことを指します。
土地を購入する前に、検討しているエリアのハザードマップを確認することで、液状化リスクの低い土地を選ぶことができます。ハザードマップは国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトで確認可能です。
洪水や土砂災害、道路防災情報などさまざまな項目から選べるので、検討している地域を一度調べてみるとよいでしょう。
購入前に地盤調査を実施する
購入したい土地が絞れたら、土地を購入する前に地盤調査を行います。地盤調査は、液状化の可能性をハザードマップよりも詳しく判定するために有効です。
購入を検討している土地において、過去に地盤調査が行われている場合は結果を確認したり、目視で現地調査を行ったりします。過去の調査データがない場合は、必要に応じて新たに地盤調査を行いましょう。
地盤調査で行うのは、スウェーデン式サウンディング試験や試料採取、土質試験などです。さらに精度の高い調査方法としては、ボーリング調査が挙げられます。
地盤調査は、浅い地層を対象とした簡易的なものから精度の高いものまでさまざまです。調べたいレベルに合った調査方法を選ぶとよいでしょう。
地震保険を確認する
液状化による被害に対する備えとして、地震保険があります。地震保険の対象は、居住用の家財と建物です。公的な支援制度だけでは住宅を修繕できない場合でも、地震保険に加入しておくことで費用を賄うことができます。
地震保険は、被災者の生活再建を目的とした政府関与の制度です。したがって、地震により被害を受けるリスクが高い住宅や居住地でも、原則として加入できます。
液状化リスクの高い土地を購入する場合や、液状化による被害に備えたい場合は、地震保険を検討するのがおすすめです。
家具の固定や備蓄品を用意する
液状化による住宅の傾きに備え、家具を固定しておくことで、ケガや事故を防ぐことができます。家具を固定する場合、一般的に最も適しているのは壁です。
家具を固定するための金具は、壁の中に入っている「間柱・胴縁」という角材に取り付けてください。震度6程度の地震を想定し、金具は厚みが3㎜以上のものを選びましょう。
また、液状化により道路が崩壊し、物流が止まることも想定されます。日頃から食料品や水などをストックする等、備蓄品の準備も重要です。
これからマンションを購入する予定の人は、パンフレットやチラシの見方について以下の記事もあわせて参考にしてください。
まとめ:液状化の仕組みを理解して発生しやすい土地の特徴を把握しておこう

まとめ:液状化の仕組みを理解して発生しやすい土地の特徴を把握しておこう
液状化は、地盤が緩く、地下水位が浅い地域で起こりやすい現象です。
液状化現象は、建物への直接的な被害だけでなく道路や水道管の破損によるライフライン設備への被害など、さまざまな影響があります。
土地条件図やハザードマップを活用して、居住地域の液状化のリスクを把握し、万が一の事態に備えておきましょう。
#液状化現象 #地盤 #地震 #建物

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
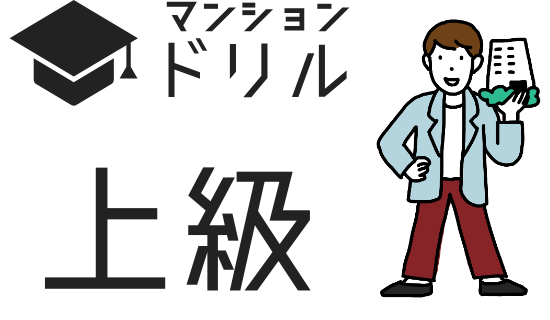
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。