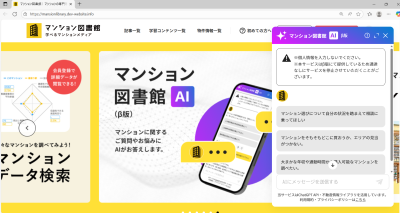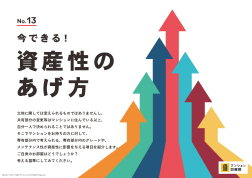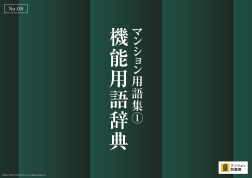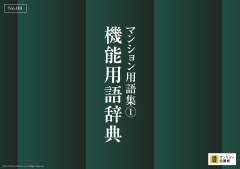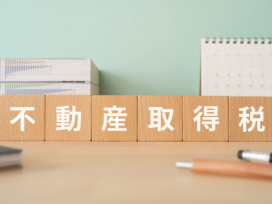全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.10.27
登録日:2025.10.27
耐震等級3はマンションに必要?等級1・2との違いとチェックポイントを解説

「マイホームを探すときよく見かける耐震等級ってなに?」
「耐震等級は必ず3じゃないといけないの?」
耐震等級という言葉について、このような疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では、耐震等級とはなにかを徹底解説します。等級1・2・3の違いや、それぞれの強度の目安なども具体的にわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
・耐震等級は、地震に対する建物の壊れにくさを示す指標のひとつ
・等級3が最も高いランクで、震度7の地震に2度耐えることを想定して設定されている
・地震保険料や住宅ローンなど、多くのシーンで金利の優遇を受けられるメリットがある
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
耐震等級3とは?等級1・2と比較

耐震等級3とは?等級1・2と比較
「耐震等級」とは、耐震性能のランクを表す言葉であり、最も高いレベルが3です。耐震等級という言葉の意味を深掘りするとともに、それぞれの等級によってどのような違いがあるのかを詳しく解説します。
耐震等級は「品確法」で定められた住宅性能の指標
耐震等級は、地震に対する建物の壊れにくさを示す指標のひとつです。「品確法」により定められたもので、阪神淡路大震災を機に制定されました。
耐震等級は、建物の耐震性能により3つのレベルに分けられており、最高ランクは耐震等級3です。次に高いものから等級2、等級1と続きます。
このように、建築の専門知識がない人でもわかるよう、目安として示されているのが「耐震等級」という基準です。数字が大きいほど耐震性が高く、物件を売買する際の目安として役立てられています。
耐震等級1・2・3の違いを比較
耐震等級ごとに、強度がそれぞれ異なります。どれほどの強度があるのかの目安を示したものが、以下の表です。
耐震等級3は、住宅性能表示制度において最も高いレベルの耐震性です。災害復興や災害時の救助活動の拠点となる警察署・消防署などの多くが、等級3の基準で建設されています。
等級2は等級1の1.25倍の強度があり、等級1は現行の建築基準法における最低限の耐震基準と同等レベルの強度です。
耐震等級3はどれくらいの地震に耐えられる?

耐震等級3はどれくらいの地震に耐えられる?
耐震性が最も高いとされる耐震等級3は、どの程度の地震に耐えられるのでしょうか。実際に起きた地震による事例とあわせて解説します。
震度7の地震に「2度」耐えることを想定
耐震等級3の建物の場合、震度7の地震に2回耐えられるとされています。
実際に、震度7の地震を2回記録した熊本地震において、耐震等級3の建物のうち倒壊・大破した棟数は0棟でした。
耐震等級は震度との直接的な関係が定義されておらず、「等級3は震度〇の地震に耐えられる」のように具体的な震度を示せないのが現状です。しかし、熊本地震のデータから、耐震等級3の建物は震度7ほどの大きな地震に2度耐えられると考えられます。
「震度7の地震に2回」というのはあくまでも目安です。したがって、耐震等級3の建物であれば必ず耐えられるわけではないと覚えておく必要があります。
震度7が2度発生した熊本地震での実績
熊本地震においては、耐震等級3の建物のうち無被害が87.5%、軽微な被害が12.5%(※)というデータが記録されています。
対して耐震等級1と同等レベルの建物では、無被害が60.1%、軽微~中壊の被害が33.6%であったのに加え大破・倒壊が6.3%(※)でした。
このことから、耐震等級3の建物の場合、震度7の地震が起きてもほとんどの建物が大きな被害を受けずに済んでいることがわかります。地震を想定して建物を建てる場合は、ひとつの目安としましょう。
地震後も大きな修繕なく住み続けられる
上記のとおり耐震等級3の建物であれば、震度7ほどの大きな地震が起きたとしても、大がかりな修繕をすることなく住み続けられると想定されます。
これからマイホームを建築予定の人は、どの耐震等級を適用するかを自由に決められる場合があるため、業者と相談のうえ決定しましょう。
一方で、地震後も大きな修理なく住めるかどうかは、地震による揺れの回数や地盤の丈夫さなどさまざまな条件によって異なる点には注意が必要です。また、地震に伴う津波や土砂災害といった思わぬ被害を受ける可能性もあることを知っておく必要があります。
鑑定士コメント
「免震」「制震」と「耐震」はどう違うのでしょうか?
「免震」は地盤と建物を分離し地震の揺れを伝えにくくすることであり、「制震」はダンパーなどを用いて地震による揺れを吸収することです。「耐震」は地震の揺れに耐えられるように建物を強化することを意味します。それぞれ似た言葉ですが、意味が異なるため混同してしまわないよう注意しましょう。
耐震等級3のメリット

耐震等級3のメリット
耐震等級3の建物を建てるメリットとして、主に以下の5つが挙げられます。
・安心感がある
・住宅の資産価値を維持しやすい
・地震保険料が最大50%割引になる
・住宅ローン「フラット35S」の金利優遇が受けられる
・長期優良住宅の認定基準をクリアしやすい
安心感がある
耐震等級3は強度が最も高いことから、命や財産を守るうえでの安心感を得られます。
在宅中の地震の場合、家が無事であれば、家族がケガをしたりがれきに押しつぶされたりするリスクは低くなるでしょう。また、家の修繕や家具・家電の買い替えなどにかかる時間とお金も不要となります。
地震によって住み慣れた家が壊れ、通常の生活ができなくなることは、想像以上に人々に不安や焦りを与えるものです。地震が起きたとしても、家が倒壊しなければ備蓄品や防災用品を活用することで、通常に近い生活が送りやすくなります。
普段意識することは少ないものの、家の強度が高ければ大きな地震があった時でも命や通常の生活を守れるという安心感が得られるのです。
住宅の資産価値を維持しやすい
家の資産価値を保ちやすいこともメリットのひとつです。もしも将来的に家を売ることになった際にも、家が壊れにくければ買い手にとって安心材料となるため、選ばれやすくなります。
耐震等級3という指標は、中古住宅の市場において他の物件との差別化ができる大きな強みです。同じような広さ・築年数・立地の中古住宅の中からひとつを選ぶとしたら、より安心感が得られ、地震保険料も安く抑えられる物件が選ばれるでしょう。
このように、等級3の物件は中古住宅の市場において有利に売却しやすいことから、資産価値を長期的に維持しやすくなると考えられます。
地震保険料が最大50%割引になる

地震保険料が最大50%割引になる
家にかかる地震保険料が、通常の住宅よりも安く抑えられるメリットもあります。耐震等級3の物件の場合、建物の耐震や免震性能によって保険の割引が受けられるためです。
「品確法」または国土交通省の「耐震診断による耐震等級の評価指針」で定められた耐震等級を持つ場合、等級ごとに割引が適用されます(※)。
ただし、割引が適用されるためには、耐震等級が公的に証明されていなくてはなりません。「耐震等級3相当」の家の場合も、地震保険の割引の適用外となるため注意が必要です。
耐震等級3相当とは、正式な認定は受けていないものの、等級3と同等の性能を持つとされる住宅のことです。公的な証明ではないため、保険料割引などの優遇は受けられません
※参考:日本損害保険協会「地震保険」
住宅ローン「フラット35S」の金利優遇が受けられる
住宅ローンにおいても優遇措置を受けることが可能です。実際に、全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の利用条件には、「耐震等級3」「耐震等級2以上」などと示されています。
耐震等級3の建物であれば、金利がより低く抑えられる「フラット35S(金利Aプラン)」を利用することも可能です。金利Aプランでは、借入当初5年間の金利が年0.5%引き下げられます。
このように、借入金額の大きい住宅において、大幅なコストダウンが叶えられる点がメリットです。
長期優良住宅の認定基準をクリアしやすい
長期優良住宅の認定基準のひとつに耐震性があり、耐震等級3がひとつの基準とされていることから、認定基準を満たしやすくなります(※)。
長期優良住宅とは、長期間にわたり良好な状態で使うための措置が講じられた、質の高い住宅のことです。認定を受けることによって、固定資産税の減額や住宅ローン控除の拡充など、税制上のさまざまな優遇措置を受けられます。
このように、家の基本的な性能を向上させることで優遇制度を利用しやすくなるため、費用を抑えた家づくりを進めやすくなるのです。
鑑定士コメント
耐震等級3でも倒壊する可能性はあるのでしょうか?
耐震等級3の家であっても、経年劣化によって地震が起きた際に倒壊する可能性があります。たとえば、木材がシロアリ被害を受けた場合や、壁内の結露により柱や梁が腐った場合などです。新築時には十分な強度があったとしても、経年劣化によって建物の強度が落ちてしまっていると、地震の揺れに耐えられない可能性が考えられます。地震による被害を防ぐためには、家を建てた後に定期的なメンテナンスや点検を行うことが大切です。
耐震等級3のデメリット

耐震等級3のデメリット
耐震等級3の家を建てるデメリットは、主に以下の3つです。
・建築コストがアップする
・間取りやデザインに制約が出ることがある
・取得のための申請費用や手間がかかる
建築コストがアップする
通常よりも建築コストが多くかかりやすくなります。
耐震等級が高くなるにつれて、耐力金物・耐力壁などの材料費や工事費などが多くかかるためです。そのほか、建物の設計や構造計算にかかる費用も多く発生します。
ただし、建築コストが増えたとしても、地震が起きた際には修繕費用を抑えられる可能性が高くなることも忘れてはいけません。初期費用と将来的なメリットを比較したうえで、耐震等級3を取得するかどうかを検討しましょう。
間取りやデザインに制約が出ることがある
家の間取りやデザインなどを自由に決められない場合があります。耐震等級3の住宅を建てるためには、柱や耐力壁などの配置を考慮した構造計算をしなければならないためです。
たとえば、リビング等の広くしたい空間に耐力壁を入れざるを得ない場合や、窓の配置に制限があり外観を自由に設定できない場合などがあります。将来的にリフォームやリノベーションをする際も同様です。
もしも叶えたい間取りやデザインがある場合は、実績のある施工会社に相談する手もあります。高い設計力を持つメーカーであれば、希望のデザインと耐震性を両立させたプランを考えてくれるでしょう。
取得のための申請費用や手間がかかる
耐震等級3を取得するには、第三者機関に対し調査を依頼する必要があることから、認定取得費も別途発生します。上記の建築コストに加えて、耐震等級3と認定してもらうための費用がかかるのです。
費用だけでなく、申請には手間もかかります。設計の段階で、施工業者が住宅性能評価機関に申請しますが、場合によっては設計の修正や追加資料の提出が必要です。さらに、現場での検査を3回行う必要があります。
このように、取得には申請のコストと時間がかかり、工期も長引きやすくなるのです。
マンション購入で知っておきたい耐震等級のポイント

マンション購入で知っておきたい耐震等級のポイント
マンションを購入する際に知っておきたい、耐震等級に関する知識や注意点を3つ解説します。
新築マンションの多くは耐震等級1
戸建て住宅では耐震等級3が多いのに対して、新築マンションでは多くが耐震等級1となっています。耐震性能を上げるには、建築コストや間取りなどの問題が大きいためです。
マンションは大規模な建造物であることから建設コストも膨らみやすく、マンションの販売価格が大幅に上昇してしまいます。
また、耐震等級を重視するとなると柱や梁を大きくしたり、窓や開口部を少なくしたりしなければなりません。結果、間取りの使いやすさや採光・通風のしやすさが低下し、販売しにくい物件となってしまうことがあります。
ただし、マンションが必ずしも地震に弱いというわけではありません。地震対策として、免震や制震構造を取り入れているマンションもあるため、さまざまな要素を比較することが大切です。
耐震等級3のマンションは希少価値が高い
新築マンションの多くが耐震等級1であるため、耐震等級3のマンションは希少価値が高いです。そのため、マンションの購入を検討する際、等級3を希望するとなると選択肢が限られると覚えておく必要があります。
新築マンションの場合は、震度6程度の大規模地震を想定した「新耐震基準」を満たしているので耐震性に関しては基本的には問題ありません(※)。
地震に強いマンションを選びたい場合は、耐震等級のほかにも地盤が頑丈か、1階が駐車場等で壁のない空間になっていないかなども確認するとよいでしょう。
※参考:内閣府「震災対策」
中古マンションの耐震等級は必ず確認する
中古マンションの購入を検討する際は、耐震等級を必ず確認する必要があります。とくに昭和56年以前に建てられたマンションの場合、新耐震基準を満たさない物件が多数あるため注意が必要です。
耐震等級を調べる際は、不動産会社に問い合わせて「住宅性能評価書」を確認します。もし(評価書が)ない場合は、耐震診断が必要です。
マンションにおける耐震診断には多額の費用がかかるため、個人での依頼は現実的とはいえません。不動産会社や管理会社へ、耐震診断を実施してもらえるかを確認しましょう。
中古マンションの内見を控えている人は、以下が参考になります。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。
まとめ:耐震等級3は家選びにおける非常に重要な基準

まとめ:耐震等級3は家選びにおける非常に重要な基準
耐震等級は、地震に対する建物の壊れにくさを示す指標のひとつであり、等級3は最も高い位置づけです。
等級3は、震度7の地震に2度耐えることを想定して設定されており、警察署や消防署などに求められている基準でもあります。
住宅の資産価値を維持しやすいほか、地震保険料や住宅ローンなどにおいてさまざまな金利の優遇を受けられるなどがメリットです。
マイホーム選びの際は、住まいの安全性や資産価値の維持などに関わる重要なポイントのひとつとして、ぜひ役立ててみてください。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
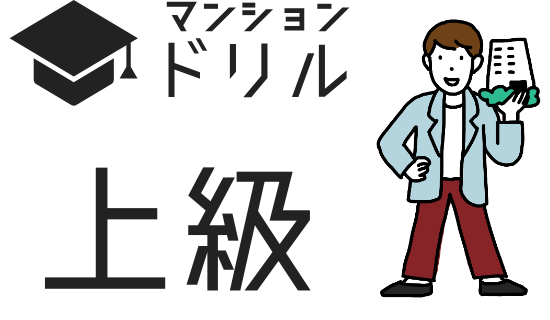
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。