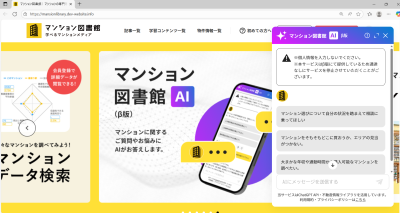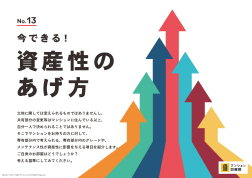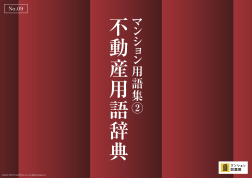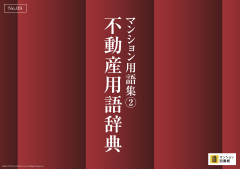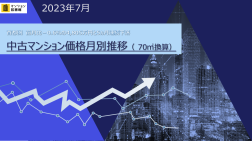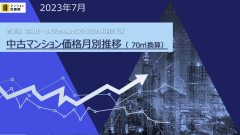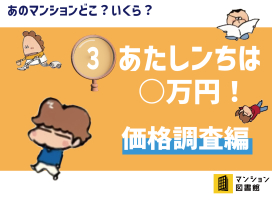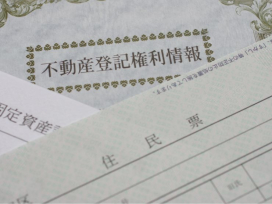全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.02.20
登録日:2025.02.20
壁紙カビ取り完全ガイド!自分でできる効果的な方法と予防策

長い間同じ壁紙を使っていると、どうしてもカビが発生してしまうことがあります。カビを放置するとさまざまな悪影響が考えられるため、早めにカビ取りを実施することが大切です。
とはいえ、「どのようにカビを除去すればいいかわからない」という方も少なくないでしょう。
本記事では、壁紙のカビ取りに関する基礎知識をはじめ、実際のカビ取り方法やカビ取り剤の選び方、使用時の注意点を解説します。さらに、再発防止策やカビ取りが難しいケースへの対応策についても触れているので、ぜひ最後までお読みください。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
壁紙のカビ取りの基本知識

壁紙のカビ取りの基本知識
壁紙のカビ取りには、カビに関する基礎知識を知ることが大切です。ここでは、下記の2点を中心に解説します。
・壁紙に発生するカビの種類
・壁紙のカビが人体に与える影響
それぞれ詳しく見ていきましょう。
壁紙に発生するカビの種類
カビの種類を見分けることは、カビ取りを行う際の重要なステップです。種類によって除去の方法や対策が変わるため、カビが生じたらまずどのようなカビかを確認しましょう。
壁紙に発生しやすいカビには、複数の種類がありますが、特に代表的なものは下記の3種類です。
カビは、一般的には湿度が高い場所に発生しやすいとされますが、実際には人が暮らせる環境であればどこでも繁殖する可能性があります。また、見た目に特徴があるとはいえ、カビが発生してから時間が経過すると区別が難しくなることも覚えておきましょう。
例えば、白カビでも放置しているうちに黒ずみ、黒カビのような見た目になるケースがあります。時間が経つほど根が深くなり除去が大変になるため、できるだけ早い段階で対応することが肝心です。
なお、白カビ・青カビの特徴をより詳しく知りたい方は、下記の記事も一緒にご覧ください。
壁紙のカビが人体に与える影響
壁紙のカビは、人体に影響を与えるものもあるため注意が必要です。カビの中には食品として利用される種類もある一方で、有害なものも多く、壁紙に生えるカビについても同様です。壁紙のカビによる人体への影響には、下記のようなものがあります。
・鼻炎
・気管支喘息
・肺炎
・その他アレルギー症状
呼吸器系への悪影響だけでなく、発がん性物質を含むカビもあることが報告されています。壁紙に生じたカビを放置してよいことはないため、見つけたら早期に対処して人体へのリスクを減らしましょう。
状況別:壁紙カビ取りの方法

状況別:壁紙カビ取りの方法
壁カビ取りは、カビの発生状況に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、壁紙カビ取りの方法について状況別で解説します。
・軽度の壁紙カビの落とし方
・ひどい壁紙カビへの対処法
・自然素材で安全に壁カビを除去する方法
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
軽度の壁紙カビの落とし方
軽度の壁紙カビには、消毒用エタノールを使用したカビ取りが有効です。
1.ティッシュやスポンジに消毒用エタノールを含ませる
2.カビが発生している部分に押し当て、軽く擦り取る
ただし、消毒用エタノールには漂白作用がないため、カビの状態によっては跡やシミが残ることがあります。カビが長期間にわたって放置されていた場合、完全に取りきれない可能性がある点に注意が必要です。
ひどい壁紙カビへの対処法
壁紙カビがひどい場合は、市販のカビ取り剤を使用するのがおすすめです。カビ除去に特化した成分を含むため、しつこいカビでも落としやすくなります。
市販のカビ取り剤を使用した壁紙カビ取りの方法は下記の通りです。
1.カビから10〜15cm離れたところからスプレーする
2.そのまま10〜15分ほど放置する(詳しい放置時間はカビ取り剤の取り扱い方法を確認ししてください)
3.固く絞った雑巾などで拭き取る
自然素材で安全に壁紙カビを除去する方法
クエン酸と重曹といった自然由来の素材でも、壁紙カビを除去することが可能です。酸性のクエン酸とアルカリ性の重曹を組み合わせることで発生する泡が、根の深いカビを浮き上がらせます。
手順は以下のとおりです。
1.200ccの水に対し小さじ1のクエン酸を入れ、スプレーボトルでよく混ぜる
2.プラスチック容器などに重曹と水を2:1の割合で入れ、ペースト状にする
3.カビのある箇所にキッチンペーパーを当て、上からクエン酸スプレーをして約5分放置する
4.キッチンペーパーを外し、重曹ペーストを歯ブラシなどで刷り込む
5.ペーストを塗った部分にキッチンペーパー・ラップの順で被せ、テープで固定して1〜2時間置く
6.キッチンペーパー・ラップを外し、雑巾などで乾拭きする
7.消毒用エタノールで拭き上げる
自然素材とはいえ手荒れの恐れもあるため、作業時は手袋を着用すると安心です。
正しい壁紙カビ取り剤の選び方

正しい壁紙カビ取り剤の選び方
壁紙カビ取り剤にはさまざまな種類があり、特徴やメリット・デメリットが異なります。ここでは次の2点に注目して、市販の壁紙カビ取り剤について解説します。
・市販の壁紙カビ取り剤の種類と特徴
・壁紙の素材別おすすめカビ取り剤
それぞれ詳しく見ていきましょう。
市販の壁紙カビ取り剤の種類と特徴
市販の壁紙カビ取り剤には、下記のような種類があります。
カビ取り剤の中でもっとも強い成分は塩素系漂白剤です。ただし、洗浄力が強いため素材を痛めてしまう恐れがあります。基本的には水で洗い流せる場所でしか使用できないため、壁紙カビ取りには使用しない方がよいでしょう。
酸素系漂白剤は、過酸化ナトリウムや過酸化水素などの酸化剤を主成分としたカビ取り剤です。素材を痛めにくく、食器や布などにも使用できます。壁紙カビ取りでも使用でき、高い効果を期待できるでしょう。
中性洗剤・アルコール・乳酸系洗剤は漂白力が弱めです。その代わり、素材を傷つけにくく安全に使いやすいため、軽度なカビ対策に適しています。
スプレー型は広範囲への塗布に向き、ジェル型はピンポイントで使えるため、壁紙のカビの広がり具合に合わせて選びましょう。
壁紙の素材別おすすめカビ取り剤
一口に壁紙といっても、その素材はさまざまです。素材とカビ取り剤の組み合わせによっては壁紙を痛めてしまう恐れがあるため、素材によってカビ取り剤を選ぶ必要があります。壁紙の素材の特徴として、大きく下記の2つに分けられます。
水分を吸収しにくい壁紙であれば、漂白剤を含む洗剤などでカビを落とせることが多いです。しかし、水分を吸収する壁紙には漂白剤の使用を避けたほうが無難でしょう。代わりに中性洗剤やアルコールなどで拭き取るのが望ましいケースが多いです。
また、素材別に専用のカビ取り剤が市販されている場合もあるため、「どれを使えばいいか分からない」と迷ったときは、壁紙の素材と対応する専用カビ取り剤を選ぶと安心です。
壁紙のカビ取り剤使用時の注意点

壁紙のカビ取り剤使用時の注意点
壁紙のカビ取り剤を使用する時は、以下のポイントに気をつけて作業しましょう。
・作業時はしっかりと保護具を装備する
・換気をしながら行う
・壁紙を痛めないようにやさしく掃除する
カビ取り時にはどうしても胞子が舞いやすく、吸い込むと体調不良の原因になる可能性があります。マスクやゴーグルなどを使用し、肌の露出を最低限にしましょう。
また、カビの胞子が飛び散って室内のほかの場所についてしまっては意味がありません。カビ取り剤の成分が充満することで気分が悪くなってしまう可能性もあります。そのため、作業中は窓は扉を開けて換気しながら作業することが大切です。
洗剤を使いすぎたり強く擦りすぎたりすると、壁紙そのものを痛めてしまうこともあります。カビ取りを行う際は、壁紙がダメージを受けないように洗剤や作業の方法などをしっかりと確認して、壁紙が傷まないように細心の注意を払って作業しましょう。
鑑定士コメント
カビ取り剤を使用するときは、可能な限り換気を行うことが重要です。窓が複数あればすべて開放し、1つしかない場合でも扇風機やサーキュレーターを活用して空気を循環させてください。換気が不十分だと胞子や薬剤の成分が室内に留まり、体調不良を引き起こす場合があります。
壁紙カビの再発防止方法

壁紙カビの再発防止方法
ここでは、壁紙カビの再発防止方法について、下記の4つを解説します。
・こまめに換気する
・除湿器や乾燥機を活用する
・防カビ剤を使用する
・壁紙を定期的にメンテナンスする
それぞれの再発防止方法について、詳しく見ていきましょう。
こまめに換気をする
カビの再発予防には、まず換気が欠かせません。日光が当たりにくく、湿度が高くなりやすい環境ほどカビは繁殖しやすいものです。
部屋の空気が循環しないと湿度はこもりやすくなります。こまめに換気してカビが繁殖しにくい環境を作ることで、再発を防止できます。
除湿機や乾燥機を活用する
換気をしても湿気が除去しきれない場合は、除湿機や乾燥機の利用がおすすめです。特に梅雨などの雨が続く時期は、どうしても室内の湿度が高くなりがちで、カビの繁殖を促してしまいます。
天候や季節によっては換気だけでは不十分な場合があるため、機械的な除湿や乾燥も併せて活用するのが効果的です。
防カビ剤を使用する
防カビ剤を使用することで、カビの再発を防止できます。カビは一度発生した場所に再度発生しやすいという特徴があります。
カビ取りを行なった後に防カビ剤を使用することで、同じ場所での繁殖を抑制できます。壁紙用の防カビ剤は市販されています。使用方法をよく確認してから適切に使いましょう。
壁紙を定期的にメンテナンスする
カビが発生しないように、壁紙を定期的にメンテナンスすることも大切です。壁紙カビは、壁紙に付着した埃や汚れを栄養にして繁殖します。
壁紙を定期的にメンテナンスすることで、壁紙を清潔に保ちカビの繁殖を抑えられるでしょう。また、カビが繁殖を始めても初期段階で対処できるため、簡単に取り除けます。
月に1回程度、消毒用エタノールを塗布して壁紙を除菌しましょう。
壁紙カビ取りが困難な場合の対処法

壁紙カビ取りが困難な場合の対処法
カビの種類や広がり方によっては、個人の力で除去するのが難しいケースがあります。その場合は、下記のような対処法を検討してみましょう。
・壁紙を貼り替える
・プロに依頼する
それぞれの対処法について、詳しく解説します。
壁紙を貼り替える
カビが壁紙全体に広がっている、あるいは下地のボードまで浸食しているような場合は、早めに壁紙を剥がして内部からカビを取り除き、貼り替えるのが得策です。
カビは放置するとどんどん繁殖していきます。ボードにまで侵食してしまうと、壁紙の表面を綺麗にしてもすぐにカビが再発する可能性が高くなります。そのため、一度壁紙を剥がしてボードのカビ取りを行う必要があります。
ボードまで侵食したカビをしっかり除去したうえで壁紙を新調すれば、再発を大幅に抑えられるでしょう。
プロに依頼する
壁紙カビ取りの専門業者やリフォーム会社に依頼すれば、費用はかかるものの、短時間で労力をかけずに徹底的なカビ除去が可能です。特に、下記のような状態の場合はプロに依頼するとよいでしょう。
・広い範囲でカビが発生している場合
・壁紙の素材が特殊だったりわからなかったりする場合
カビが広範囲に広がっている場合、自分だけではカビの場所を全て把握できない恐れがあります。プロに依頼することで、正確にカビの位置を把握してカビを一掃できるでしょう。
プロならカビの状況や素材にあわせて最適な方法を選択できるため、見落としを最小限に抑えて安心して任せられます。
鑑定士コメント
賃貸でカビが発生した場合、状況によって責任が変わります。建物の構造の問題でカビが発生しやすい状態の場合は大家の責任となり、結露の放置や掃除・換気が十分にできていない場合は入居者の責任となります。どちらの責任であったとしても、まずは大家に報告して状況を共有しましょう。その後、大家や入居者でカビ取りを行い、それだけでは対処できない場合はプロに依頼することになります。
まとめ:適切な対策と予防で壁紙のカビを撃退しよう

まとめ:適切な対策と予防で壁紙のカビを撃退しよう
壁紙カビは、湿気の多い場所や換気が不十分な環境で特に発生しやすいとされています。しかし、人が生活できる空間であればどこにでも繁殖する可能性があるため、常日頃からカビが発生しにくい状況を整えておくことが重要です。
もしカビが発生してしまった際は、できるだけ早く対処することが大切です。すぐに対処することで、カビが根を張る前に除去できます。もし壁紙の広範囲にカビが発生してしまった場合は、プロへの依頼も視野に入れましょう。
#カビ #カビ取り #壁紙

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
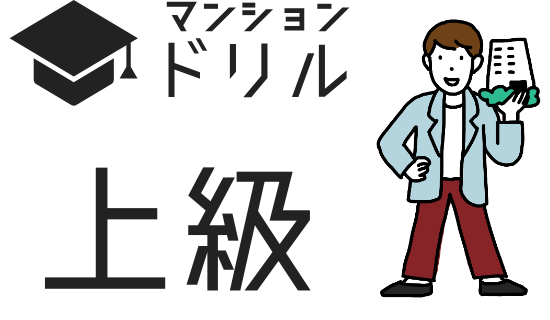
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。