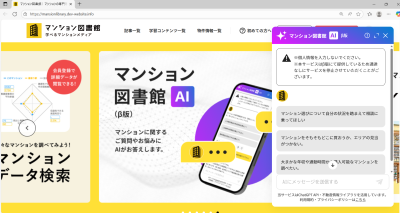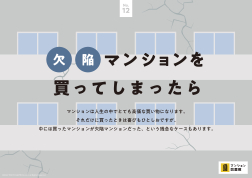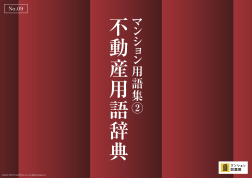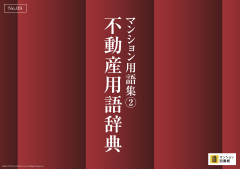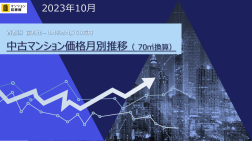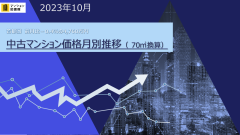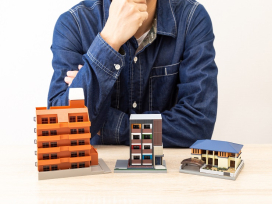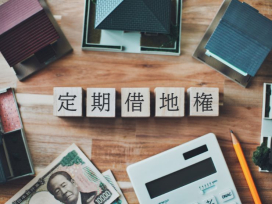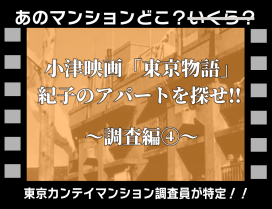全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.07.25
登録日:2025.07.25
不動産契約もクーリングオフできる?知っておきたい条件・期間・手続き方法を解説

「不動産契約もクーリングオフできるの?」
「クーリングオフの条件や期間は?」
不動産は人生でもっとも大きな買い物の一つです。そのため、契約後に「やっぱりやめたい」と悩む方も少なくありません。
実は、不動産取引でも一定の条件を満たせば、クーリングオフ制度を利用して契約を解除することができます。
本記事では、不動産契約におけるクーリングオフの基本知識から、適用条件・期間・手続き方法までわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
・不動産売買でも、条件を満たせばクーリングオフができる
・売主が一般個人や物件引き渡し後、クーリングオフの説明を受けた日から9日以上経過した場合などはクーリングオフできない
・クーリングオフの手続きの流れ
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
不動産売買のクーリングオフとは

不動産売買のクーリングオフとは
不動産の購入は金額が高額なだけに、「契約したあとに気が変わったらどうしよう…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。そのようなときに備えて設けられているのが「クーリングオフ制度」です。
ここでは、クーリングオフ制度の概要や目的、そのほかの解除方法との違いについて解説します。
クーリングオフ制度の概要
クーリングオフ制度とは、契約を結んだあとでも、一定の期間内であれば無条件で契約を取り消せる制度です。訪問販売や電話勧誘など、冷静な判断がしにくい状況で契約してしまった消費者を守るために設けられています。
不動産の取引でも、昭和55年の宅地建物取引業法の改正によりクーリングオフ制度が導入されました。
規定は、宅地建物取引業法の第37条の2に定められており、対象となるのは「宅地や建物の売買契約」に限られます。(※)
アパートなどの「賃貸契約」にはクーリングオフ制度は適用されないため、注意が必要です。
※ 参照:宅地建物取引業法
クーリングオフ制度の目的
クーリングオフ制度の目的は、冷静さを欠いたまま契約してしまった人が、一度立ち止まって考え直すための時間を確保することです。
不動産の購入は高額な取引であり、本来であれば時間をかけて慎重に検討したいものです。
しかし、かつては訪問販売や旅行先での勧誘など、落ち着いて判断するのが難しい状況で契約が結ばれるケースが見られました。また、購入者の知識不足につけ込んで、強引に契約を進めるような営業手法が問題となることもあったのです。
こうした背景から、法律では「買主が不利になりやすい場面」において、契約を見直す機会を設けています。
クーリングオフ制度は、消費者にとって冷静に判断し直す時間を確保するための大切な制度なのです。
クーリングオフと手付解除・違約解除の違い
不動産売買契約を解除する方法には、「クーリングオフ」のほかに、「手付解除」や「違約解除」があります。
「手付解除」とは、契約時に交付された「手付金」を利用して契約を解除する方法です。契約相手が履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は倍額を返すことで、それぞれ契約を解除できます。
「違約解除」は、相手が契約内容を守らなかったときに適用される解除方法です。売主が所有権移転登記を行わなかった場合などが該当し、違反した側は「契約解除」と「違約金」の支払いが求められます。
クーリングオフは、一定の条件はありますが、無条件で解除できる制度です。ほかの解除方法と比べて負担が少なく、買主にとって安心できる制度といえるでしょう。
「手付解除」については、以下の記事で詳しく解説しています。
手付解除とは?いつまで解除できるのか、手付金がどうなるかも解説
鑑定士コメント
クーリングオフが適用される場合、支払った「申込金」も全額返金されます。クーリングオフは無条件で契約を解除できる制度であり、手付金や申込金など、契約に関連して支払ったお金はすべて返還の対象です。これは、買主に冷静に判断する時間を与えるという「消費者保護」を目的とした制度だからです。したがって、申込金も例外なく返金されることになります。
不動産のクーリングオフができる条件

不動産のクーリングオフができる条件
クーリングオフは、すべての不動産取引に適用されるわけではありません。ここでは不動産取引においてクーリングオフが認められる条件を5つ解説します。
・売主が宅地建物取引業者である
・買主が宅建業者以外である
・事務所や案内所以外の場所で契約している
・クーリングオフの説明を受けた日から8日以内である
・物件の引渡しや代金全額の支払いが完了していない
売主が宅地建物取引業者である
クーリングオフを利用できるかどうかは、売主が「宅地建物取引業者(宅建業者)」であるかどうかで決まります。
宅建業者とは、家や土地の売買・賃貸を事業として反復・継続して行っている個人や法人のことです。不動産取引の専門家であるため、取引に慣れていない買主を守る目的でクーリングオフ制度が設けられています。
ただし、次のようなケースでは制度の対象外となるので、注意が必要です。
・仲介をしたのが宅建業者でも、「実際の売主」が個人の場合
・売主が法人でも、宅建業の免許がなく事業として不動産を扱っていない場合
クーリングオフが使えるかどうかは「だれと契約を結ぶのか」がポイントになります。契約書や重要事項説明書などを確認し、売主が宅建業者であるかをしっかりチェックしておきましょう。
買主が宅建業者以外である
クーリングオフができる条件には、買主が宅建業者ではなく、一般の消費者であることも含まれます。
ここでいう一般消費者とは、「不動産に関する専門知識を持たない個人のこと」を指します。例えば、自宅用に住宅や土地を個人名義で購入するケースなどが該当します。
一方、買主が宅建業者である場合は、専門的な知識や取引経験を持っていると判断されるため、クーリングオフの対象にはなりません。
クーリングオフ制度の目的を一言で表すなら、「一般消費者を保護すること」です。そのため、買主が宅建業者である場合には制度で保護する必要はなく、クーリングオフは行使できません。
事務所や案内所以外の場所で契約している
不動産会社の事務所や営業所ではなく、別の場所で契約した場合は、クーリングオフの対象になります。
例えば、次のような場所で契約したケースです。
・買主の自宅
・喫茶店やカフェ
・ファミリーレストラン
・ホテルのロビー
・駅の待合室
上記のような場所では購入者が落ち着いて契約内容を検討できません。そのため、クーリングオフが認められています。
なお、原則、不動産会社の「案内所」で契約した場合はクーリングオフはできませんが、「テント張りの仮設案内所」での契約はクーリングオフの対象になることがあります。建物として土地に定着していない場所と考えられるためです。
クーリングオフの説明を受けた日から8日以内である
クーリングオフを行使できる期間は、「契約書面で説明を受けて書面が交付された日」から数えて8日以内とされています。
この8日間は、「契約日」ではなく、「宅建業者からクーリングオフに関する書面での説明を受け取った日」が起算日です。契約した日と混同しないように注意しましょう。
期間内に書面で契約解除の意思を伝えれば、理由を問わず契約を取り消すことができ、支払済みの「手付金」や「申込金」も全額返金されます。
なお、宅建業者にはクーリングオフの説明をする法的義務があるわけではありません。そのため、もし制度の説明が行われていなければ8日の制限は適用されず、買主はいつでも契約解除を申し出ることが可能です。
物件の引渡しや代金全額の支払いが完了していない
クーリングオフを利用するには、物件の引渡しや代金の全額支払いがまだ行われていないことも条件となります。
ここでいう「引渡し」とは、鍵をもらうだけでなく、名義変更(所有権移転登記)も終わっている状態を指します。また、代金についても、全額を支払っていないことが必要です。
たとえほかの条件を満たしていても、すでに引渡しや支払いが終わっている場合は、クーリングオフは使えません。
不動産の購入は金額が大きく、一度決まると契約を取りやめるのは難しくなります。あせらず流れをよく確認しながら、手続きを進めましょう。
不動産を売買したときは「所有権移転登記」が必要となります。手続きが必要な場面や費用の目安については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
所有権移転登記とは?手続きが必要な場面や費用の相場をわかりやすく紹介
鑑定士コメント
クーリングオフをしても、ペナルティは一切発生しません。契約は無条件で解除され、支払った手付金や申込金も全額返還されます。クーリングオフは、買主が冷静な判断をできない状況で契約してしまった場合に備えた、消費者保護のための制度だからです。
なお、通常の契約解除である「手付解除」や「違約解除」では、「手付金の放棄」や「違約金の支払い」といった一定のペナルティが発生します。クーリングオフは買主にとって非常に強い権利といえるでしょう。
不動産のクーリングオフができない5つのケース

不動産のクーリングオフができない5つのケース
ここでは不動産のクーリングオフができないケースを5つ紹介します。
・売主が一般個人/買主が業者の取引の場合
・業者の事務所・常設モデルルーム等で契約した
・物件引渡し+代金全額支払い完了後
・クーリングオフの説明を受けた日から9日以上経過した場合
・買主が自ら希望して事務所外契約を行ったとき
売主が一般個人/買主が業者の取引の場合
クーリングオフができるかどうかは、「誰が売主で、誰が買主か」によって決まります。
まず、売主が「一般の個人」である場合は、クーリングオフは行えません。あくまでも「宅建業者」を売主とする取引が対象です。
また、買主が「宅建業者」などの事業者である場合も、制度の対象外となります。これは、クーリングオフ制度が、不動産取引に不慣れな「一般消費者を保護すること」を目的としているためです。専門知識や経験を有する業者に対しては、保護の必要性が低いとされています。
したがって、クーリングオフが認められるのは、「売主が宅建業者」、「買主が宅建業者ではない個人」であるときです。
業者の事務所・常設モデルルーム等で契約した
クーリングオフができるかどうかは、「誰と契約したか」だけでなく、「どこで契約したか」も重要なポイントです。
不動産会社の事務所や、宅建業者が常駐する常設のモデルルームなどで契約をした場合は、クーリングオフ制度の対象にはなりません。これらの場所では、落ち着いた環境で十分な説明を受けたうえで契約に至ったと判断されるためです。
一方で、喫茶店やホテルのロビーなど、業者の管理下にない場所で契約をした場合は、買主が冷静な判断をしづらい場面とみなされ、クーリングオフの対象になります。
物件引渡し+代金全額支払い完了後
「物件の引渡し」と「代金の全額支払い」の両方が完了している場合、クーリングオフ制度の利用は認められません。このような状態は、不動産の契約がすでに完了し、不動産の取引が確定しているとみなされるためです。
不動産は高額な取引であり、一度成立した契約はしっかり守られることが求められます。たとえ「やっぱりやめたい」と思っても、引渡し後に契約を白紙に戻すことは原則としてできません。
ただし、手付金や一部の代金を支払っていても、引渡しが済んでいない場合には、クーリングオフを行使できる可能性があります。
大切なのは、「引渡し」と「全額支払い」が両方とも終わっているかどうか。どちらか一方でも未完了であれば、制度の対象となる可能性があります。
クーリングオフの説明を受けた日から9日以上経過した場合
クーリングオフができる期間は、宅建業者から「契約解除が可能であること」の書面による説明を受けた日から「8日以内」です。
そのため、書面を受け取ってから9日以上が過ぎている場合は、クーリングオフを利用することはできません。
例えば、5月1日に契約し、5月2日にクーリングオフの書面を受け取った場合、行使できるのは5月2日から9日までです。10日以降は対象外となります。
なお、8日間は「暦日」で数えるため、土日祝日も含まれます。最終日が休日であっても期間の延長はないため、日数のカウントには十分注意しましょう。
買主が自ら希望して事務所外契約を行ったとき
事務所以外で契約した場合でも、買主自身がその場所を希望していたなら、クーリングオフの対象にはなりません。
自ら契約場所を指定したということは、買主が納得のうえで判断したとみなされ、特別な保護は不要とされるためです。
一方、売主の提案で事務所以外の場所で契約した場合や、売主が自宅を訪問して契約した場合は、クーリングオフの対象になります。
「購入をやっぱりやめたい」と思っても、自分で契約場所を選んでいた場合は制度を使えません。不動産の購入時は、契約場所にも注意を払うことが大切です。
クーリングオフの手続き手順

クーリングオフの手続き手順
「契約をなかったことにしたい」と思ったとき、どのような手順でクーリングオフを進めればよいのでしょうか。
ここでは、以下の3つのステップに沿って、クーリングオフの手続き手順を解説します。
1.意思表示を書面で行う
2.書面に記載する内容
3.通知を送付する
1.意思表示を書面で行う
クーリングオフを行うには、「契約を解除したい」という意思を売主に書面で伝える必要があります。
法律上は口頭でも有効ですが、後で「聞いていない」と言われるリスクがあるため、必ず証拠が残る書面で通知しましょう。
通知方法はハガキ・封書・FAXなどがありますが、最も確実なのは「内容証明郵便(配達証明付き)」です。送付記録が残るため、トラブル時の証拠になります。
内容証明郵便は書面を3通用意し、1通を相手に送付、1通を自分用、1通を郵便局が保管します。
確実に解除の意思表示をするためにも、内容証明郵便での通知がおすすめです。
2.書面に記載する内容
クーリングオフの通知書には決まった用紙はありませんが、「契約を解除したい」という意思が明確に伝わる内容にしましょう。
記載する項目は、以下のとおりです。
・クーリングオフにより契約を解除する旨
・契約説明書(クーリングオフの告知書)の受領日
・物件の情報(所在地・物件番号・面積など)
・売買代金
・売主の会社名および担当者名
・買主の氏名(署名または記名押印)
また、すでに手付金などを支払っている場合は、「支払済みの〇〇円の返金をお願いします。」明記すると安心です。
なお、内容証明郵便で送る場合は、「1行20字以内・1枚26行以内」などの形式制限があるため、レイアウトにも注意しましょう。(※)
※ 参照:郵便局
3.通知を送付する
書面を作成したら、忘れずに相手へ送付しましょう。クーリングオフは、書面を相手に送ることで効力が発生します。
なお、制度には「発信主義」が採用されており、基準となるのは届いた日ではなく「発送日(消印日)」です。8日以内に発送すれば、クーリングオフが有効となるため、送付日には十分注意しましょう。
また、万が一のトラブルに備えて、次の書類は5年間を目安に保管しておくと安心です。
・郵便局の受領証
・通知書のコピー(はがきや内容証明の控え)
・契約書のコピー
万が一、購入した物件に重大な不具合が見つかった場合、どう対応すべきか悩む方も多いでしょう。欠陥マンションを購入してしまったときの対処法や注意点については、以下で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
まとめ:8日間を逃さず、正しい手順で安全にクーリングオフしよう

まとめ:8日間を逃さず、正しい手順で安全にクーリングオフしよう
不動産の契約は、基本的に一度結ぶと取り消すことができません。しかし、買主が十分に考える時間を持てなかった場合に備えて「クーリングオフ制度」が設けられています。
クーリングオフ制度を使えるのは、「売主が宅建業者であること」「契約が事務所以外で行われたこと」「引渡しや代金の全額支払いがまだ済んでいないこと」など、いくつかの条件をすべて満たすときです。
条件に該当する場合は、クーリングオフの説明を受けた日(または契約書面を受け取った日)から8日以内に書面で解除の意思を伝えれば、契約をなかったことにできます。
不動産は大きな買い物です。制度の内容を正しく理解し、万が一に備えておくことが大切です。
#不動産 #クーリングオフ #宅建業者 #解約

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
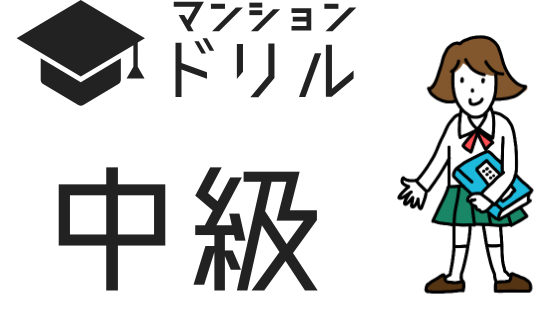
マンションドリル中級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。