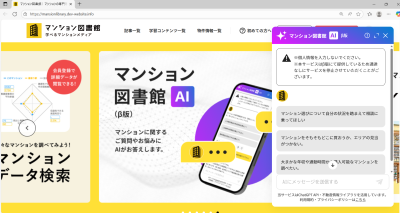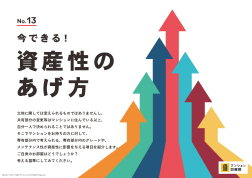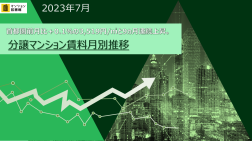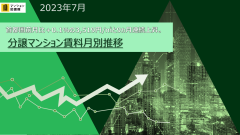全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.03.24
登録日:2025.03.24
お香の煙で火災報知器は鳴ってしまう?仕組みと感知方式を知って誤作動に適切に対処する方法

お香の香りでリラックスしたいけど、「火災報知器が鳴るかも…?」と不安に思ったことはありませんか。
実際、お香の煙が火災報知器に反応することはあります。しかし、適切な使い方をすれば誤作動を防ぐことが可能です。
この記事では、火災報知器の仕組みや感知方式をわかりやすく解説し、火災報知器を鳴らさずにお香を楽しむ方法を紹介します。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
お香の煙で火災報知器は作動する?

お香の煙で火災報知器は作動する?
結論から言うと、お香の煙によって火災報知器が反応することはほとんどありません。
1~2本程度のお香を焚く場合、火災報知器が反応することはほとんどなく、室内でも安心して楽しめます。
しかし、まれにお香の煙が原因で火災報知器が鳴ることがあるため、注意が必要です。
では、なぜ火災報知器が作動してしまうのか、仕組みを理解すれば誤作動を防ぐための適切な対策が取れます。
次章では、火災報知器の種類と誤作動を防ぐポイントについて詳しく解説します。
お香の煙と火災報知器の関係

お香の煙と火災報知器の関係
お香を焚いていると、火災報知器が反応することがあるのは事実です。特に煙を感知するタイプは、お香の煙にも敏感に反応します。
ここでは、火災報知器の仕組みや感知方式をわかりやすく解説し、誤作動を防ぐポイントを紹介します。
火災報知器の仕組みと感知方式
火災報知器は、主に3つの種類があります。
・煙感知器
・熱感知器
・炎感知器
「煙感知器」は、煙を感知して作動します。「熱感知器」は、温度が一定以上に上昇すると作動する仕組みです。「炎感知器」は炎が発する放射エネルギーを感知します。
上記のうち、特に「光電式の煙感知器」は、お香を焚く際に気をつけなければなりません。光電式は、煙の粒子が光を散乱させることで反応する仕組みです。お香の煙のように粒子の大きい成分を含む煙に敏感で、誤って感知することがあります。
一方、熱感知器や炎感知器は温度や炎を感知する仕組みのため、お香の煙では作動しにくいでしょう。
お香で火災報知器の誤作動を防ぐための注意点
火災報知器の誤作動を防ぐには、お香の使い方に注意することが大切です。
まず、お香を焚く前に火災報知器の種類を確認しましょう。煙感知器の近くでは、お香の煙が反応する可能性があるため注意が必要です。
エアコンや換気扇の風向きも工夫しましょう。お香の煙が火災報知器に直接流れないようにしてください。
複数本を同時に焚かないことも重要です。大量の煙が発生すると誤作動のリスクが高まります。一本ずつ焚くと、安全です。
正しい使い方を心がけ、安全にお香を楽しみましょう。
鑑定士コメント
蚊取り線香の煙で火災報知器が作動する可能性はほとんどありません。煙感知器は煙の粒子を検知しますが、通常の使用では煙の量が少なく誤作動しにくいです。熱感知器も一定以上の温度上昇で作動するため、蚊取り線香の燃焼温度では反応しません。ただし、密閉空間で大量に焚くと反応する可能性があるため、注意が必要です。
火災報知器を作動させずにお香を楽しむポイント

火災報知器を作動させずにお香を楽しむポイント
火災報知器を作動させないために、以下のポイントを押さえてお香を楽しみましょう。
・火災報知器との適切な距離を保つ
・十分に換気をする
・煙の少ないお香を選ぶ
・お香の使用時に避けるべき場所に置かない
・燃えない素材の香皿を使う
・お香の火の始末に気をつける
火災報知器との適切な距離を保つ
お香を安全に楽しむためには、火災報知器との距離を適切に保つことが重要です。煙感知器は煙の粒を検知して作動するので、すぐそばで焚くと誤作動を引き起こす可能性があります。
ただし、通常の使用では、お香の煙が天井まで上がることは少なく、警報が鳴る心配はほとんどありません。
とはいえ、火災報知器の近くでお香を焚くのは危険です。火災報知器から横に1メートル以上、縦に1.5〜1.8メートル以上離して焚くことで、誤作動のリスクを軽減できるでしょう。
十分に換気をする
お香を焚くときは、火災報知器が作動しないよう、十分に換気をすることが大事です。
窓を閉め切った状態だと、煙が滞留して火災報知器が反応することがあります。特に狭い部屋では、空気の流れを作ることが大切です。
また、換気をしないと煙のにおいが強くなり、お香本来の香りを楽しめなくなることもあります。
換気扇を回す、窓を少し開けるなどして、空気の流れを作りましょう。
煙の少ないお香を選ぶ
火災報知器の誤作動を防ぐためには、煙の少ないお香を選ぶことが有効です。
火災報知器は煙の濃度が高いほど反応しやすくなります。1〜2本程度のお香では作動しにくいですが、換気が不十分で煙がこもると誤作動のリスクが高まるでしょう。
そこでおすすめなのが、煙の少ないお香です。
少煙タイプは炭をベースに作られていることが多く、燃えても煙が出にくいのが特徴です。そのため、火災報知器が作動する可能性を抑えることができます。
また、煙が少ないことで、お香本来の香りを純粋に楽しめるメリットもあります。
お香の使用時に避けるべき場所に置かない
火災報知器の誤作動を防ぐためには、お香の置き場所に注意することが重要です。
まず、布団やソファなど燃えやすいものの付近にはお香を置かないよう注意しましょう。お香の火は小さいですが、燃え移ると火災の原因になる可能性があります。
扇風機の近くや窓際など、風が強い場所も避けましょう。風でお香が倒れるほか、煙が広がり火災報知器が誤作動するリスクが高まります。
子どもやペットの手が届く場所も危険です。誤って倒してしまうと、火事につながる可能性があります。
火災報知器を作動させずお香を楽しむためには、置き場所を慎重に選ぶことが大事です。
燃えない素材の香皿を使う
燃えない素材の香皿を使うことで、火災報知器の誤作動を防ぐことができます。お香を焚く際は、陶器・磁器・金属製の香皿を使用しましょう。
お店などで「お香立てに使えそう」と思い購入したものが、実は可燃性の素材だったというケースもあります。燃えない素材かどうかを必ず確認してから使用しましょう。
また、お香の長さに合った香皿を選ぶことも大切です。お香がはみ出すと灰が落ちやすく、火災や火災報知器の誤作動の原因になることがあります。
火の取り扱いが心配な場合は、「電子香炉」を活用するのもおすすめです。
お香の火の始末に気をつける
火災報知器が作動しないよう、お香の火の後始末には気をつけましょう。 特に渦巻き型のお香は燃焼時間が長いため、火の管理を徹底することが大切です。
途中で火を消す場合は、金属製のクリップで挟むか、手で追って消す方法がありますが、やけどには十分注意してください。
また、焚き終わった後も気を抜かないことが重要です。見た目は消えていても、灰やお香本体に熱が残り、煙が出続けることがあります。
完全に火が消えたことを確認し、水をかけてから処分することで、火災報知器が反応するのを防げるでしょう。
鑑定士コメント
賃貸物件では退去時に原状回復の義務があります。お香の煙がこもると、壁紙ににおいが染みつき、修繕費を請求される可能性も。だからこそ、換気をしっかりおこなうことが大切です。窓を開けたり換気扇を使ったりして、煙がこもらないようにしましょう。少煙タイプのお香を選ぶのも有効な対策です。
火災報知器が作動した場合の対処法

火災報知器が作動した場合の対処法
お香を焚いていたら火災報知器が作動してしまい、突然の警報音に驚くこともあるかもしれません。 そのようなときに慌てず冷静に対応できるよう、事前に停止方法を把握しておくことが大切です。
また、誤作動の原因を特定することで、再発を防ぐことができます。
ここでは、誤作動時の停止方法や考えられる原因について解説します。
誤作動時の火災報知器の停止方法
お香の煙で火災報知器が誤作動した場合、まずは換気をしましょう。 窓を開けたり換気扇を回したりして、煙を外に逃がすことが大切です。
次に、火災報知器の警報停止ボタンを押すか、ヒモを引くことで警報音を止められます。機種によって操作方法が異なるため、取扱説明書やメーカーのサイトで確認しておくと安心です。
また、一部の火災報知器には「一時停止機能」があり、一定時間だけ煙感知をオフにすることができます。お香を焚く前に活用すると、誤作動を防げます。ただし、一時停止後は必ず元の状態に戻すようにしてください。
誤作動の原因
火災報知器は煙や熱を感知して作動しますが、次のような原因で誤作動を起こすこともあります。
・料理の煙や湯気
・燻煙式の殺虫剤
・ホコリや小さな虫
・結露による水滴
・電池切れや故障
特にホコリには注意が必要です。ホコリがたまると誤作動しやすくなるため、半年に1回は掃除をしましょう。掃除の際は、感知部に水分や掃除機の先が直接触れないよう注意してください。
また、火災報知器の交換目安は10年(※)です。古くなると電池切れや故障で誤作動しやすくなります。使用期間を確認し、必要に応じて交換しましょう。
※参照:東京消防庁
まとめ:お香で火災報知を鳴らさないように、正しい方法で楽しもう

まとめ:お香で火災報知を鳴らさないように、正しい方法で楽しもう
お香を焚く際は、火災報知器の誤作動を防ぐ工夫が大切です。
まず、火災報知器との距離を適切に保ちましょう。煙感知器の近くで焚くと誤作動の原因になります。
また、換気をしっかりおこない、煙がこもらないようにすることも重要です。少煙タイプのお香を選ぶことで、火災報知器が鳴るリスクをより抑えられます。
燃えない素材の香皿を使い、火の取り扱いにも十分注意しましょう。焚き終えた後は、完全に火が消えたことを確認してから処分することが大切です。
正しい使い方を守り、安心してお香を楽しみましょう。
#お香、#火災報知器、#線香

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
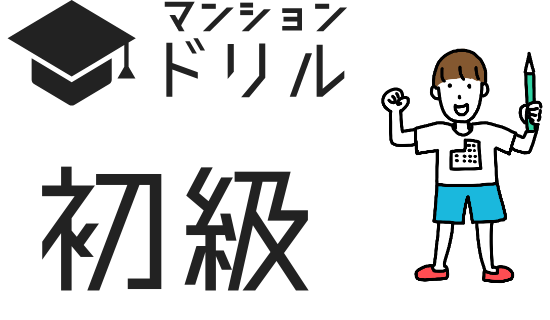
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。