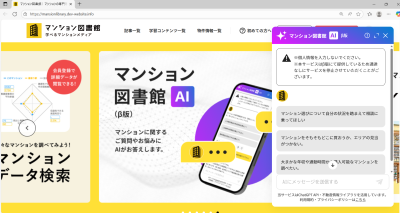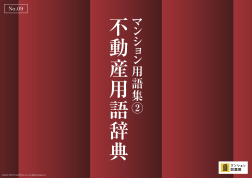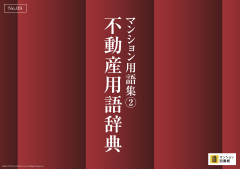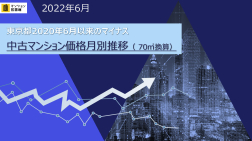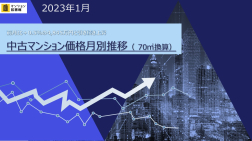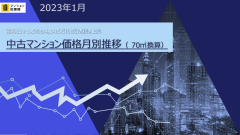全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.02.20
登録日:2024.02.22
不動産取得税がかからないケースがある?非課税条件や軽減措置を徹底解説
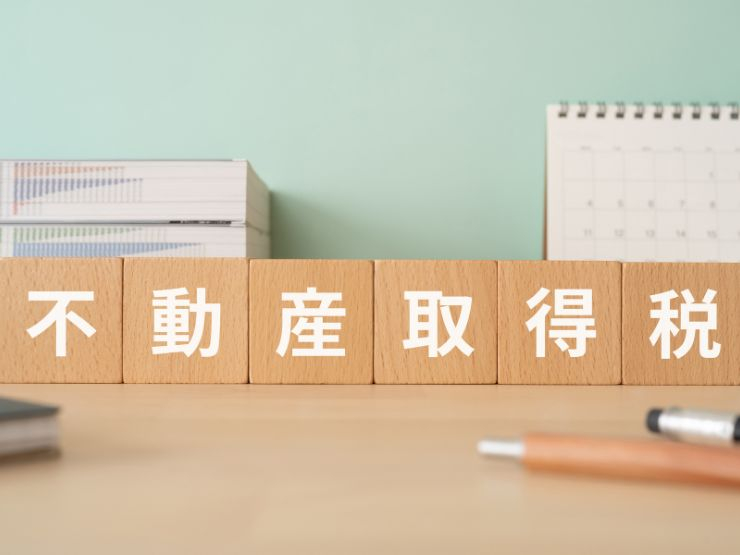
不動産を取得したとき、取得者は不動産取得税を納める必要があります。一方で不動産取得税がかからないケースがあるのをご存知でしょうか。
条件によっては減免措置が受けられるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。不動産を取得したあとでも、申告することで還付される可能性があります。
本記事では、不動産取得税が非課税となるケースや、非課税措置が適用される条件についてまとめました。不動産取得税の基礎知識や計算方法とあわせて紹介するので、不動産の取得を検討している方はぜひ参考にしてください。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
不動産取得税とは

不動産取得税とは
不動産取得税は、都道府県によって課税される税金のひとつです。土地や家屋などの不動産を贈与・売買・建築・交換などにより取得した場合が対象となります。
有償・無償や、登記の有無にかかわらず納税義務があります。ただし、以下の場合には課税されません。
・相続によって不動産を取得した
・公共のために用いる道路を取得した
・政令で定める分割または法人の合併による不動産を取得した
・宗教法人に用いる不動産を取得した
・学校法人が直接教育または保育に用いる不動産を取得した
上記に当てはまらない場合は、原則として不動産取得税を納める義務が発生します。不動産取得税については以下の記事で紹介していますので、納税における軽減措置や納税時の注意点などを知りたい人は参考にしてください。
不動産取得税とは?軽減措置や計算方法・納付時のポイントを解説
不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、以下の計算式で求められます。
税額=不動産の価格×税率
ここでいう不動産の価格は、購入代金や建築費ではありません。家屋や土地の種類によって評価額が異なるため、どの金額を参照すればよいのか事前に確認しましょう。以下は種類別の参考です。
平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得された不動産において、適用される税率は以下のとおりです。
※参照:愛知県
鑑定士コメント
マンションの場合の固定資産税評価額はどのように決めるのでしょうか?マンションの場合、土地と建物をあわせて固定資産税評価額を評価します。個人で所有する専有部分と、区分所有者全員が共有する共用部分の共有持ち分で算出します。共用部分の共有持ち分は、共有部分を各戸の専有床面積の割合で按分して床面積を割り出します。
不動産取得税がかからないケース

不動産取得税がかからないケース
以下の場合、原則として不動産取得税は発生しません。
・相続で不動産を取得した場合
・不動産価格が免税額以下の場合
・土地区画整理法により換地を取得した場合
・特定の法人が事業用の不動産を取得した場合
・法人の合併または分割で不動産を取得した場合
※本制度や手続きは自治体によって異なる場合があるため、必ず最新情報を確認しましょう
相続で不動産を取得した場合
相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税は発生しません。相続とは、すでに納税された財産が移転するものと位置づけられているためです。相続は贈与や売買などとは異なり、あくまでも「形式的な所有権の移動」とみなされるため、贈与や売買とは異なります。
一方で、生前に贈与された不動産は相続とはみなされず、課税の対象となる点に注意が必要です。
また、故人の残した遺言にもとづいて遺産が譲られる「遺贈」ケースでは、その種類によって課税・非課税が分かれます。
遺言書により受遺者と財産内容が具体的に示される「特定遺贈」などが代表例です。遺贈の種類ごとの課税・非課税の分類は以下のとおりです。
不動産価格が免税額以下の場合
不動産価格が免税額以下の場合も、不動産取得税はかかりません。ここでの「価格」とは、固定資産税評価額のことを指します。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
・土地の取得日から1年以内に、その土地に隣接する別の土地を新たに取得した
・家屋の取得日から1年以内に、その家屋と一体となる建物を新たに取得した
上記のケースでは、ひとつの土地や建物として評価されるため、合算した価格が免税額を超過すると課税の対象です。
なお、免税額のラインは都道府県によって異なります。自分の住んでいる地域の免税額がいくらなのかを知りたい場合は、各自治体のホームページで確認が可能です。
具体的には、「県税の紹介」や「県税Q&A」といったカテゴリ内で紹介されているので、気になる人は確認してみてください。
土地区画整理法により換地を取得した場合
土地区画整理により換地(かんち)を取得した場合も、原則として不動産取得税は非課税です。
土地区画整理事業は都市づくりに活用される方法の一つで、幹線道路や生活道路の整備によって交通の安全性や土地活用の効率を高めることを目的としています。
換地とは、土地区画整理事業により、現在の宅地から新しく定められる宅地のことです。換地では、既存の土地を細かく分筆・合筆・交換するのではなく、いわば「白紙」から再編する方法です。
このように、道路の整備をはじめとする土地区画整理によって、新たに定められた宅地を取得した際は不動産取得税が発生しません。
特定の法人が事業用の不動産を取得した場合
以下のような、特定の法人が事業用の不動産を取得した場合も課税の対象外です。
・宗教法人
・学校法人
・医療法人
・社会福祉法人
具体例として、宗教法人や学校法人などが、本来の事業のために不動産を取得した場合が挙げられます。また、医療法人や社会福祉法人などが、政令で定める事業のために不動産を取得した場合も該当します。
ただし、本来の事業とは無関係の用途で取得した不動産は課税対象になるため、注意が必要です。
法人の合併または分割で不動産を取得した場合
会社の合併または分割で不動産を取得した場合も非課税となります。理由は、不動産の所有権が単に変更されるだけに過ぎず、新規取得ではないと判断されるためです。
ただし、会社の分割による不動産取得が非課税となるには、「金銭等不交付要件」を満たす必要があります。
金銭等不交付要件とは、会社分割により事業を引き継ぐ会社が、事業を分割した分割会社に対して支払う分割対価として株式のみを許可するというものです。したがって現金などは使えません。使用できる株式は、以下の2つに限られています。
・承継会社の株式
・承継会社の親会社株式
この要件を満たさない場合は課税対象となるため注意しましょう。
不動産取得税対象でも不動産取得税がかからないケース

不動産取得税対象でも不動産取得税がかからないケース
不動産取得税の対象となる場合でも、減免措置が受けられる可能性があります。
・新築住宅の軽減措置
・中古住宅の軽減措置
それぞれ減免措置の対象となるケースをまとめました。
新築住宅の軽減措置
建物の軽減措置
新築住宅を取得した際、以下の条件を満たせば1,200万円の控除を受けられます。
・居住用として取得する不動産であること
・延べ床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上で240㎡以下
延べ床面積にはマンションの共用部や車庫、物置が含まれます。新築住宅だけではなく、増改築したケースにも適用することが可能です。
減免措置を受ける場合、「(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×税率」で不動産取得税を計算しましょう。なお、耐震性や住宅環境など条件を満たして「長期優良住宅」に認定された場合、控除額は1,300万円に拡大されます。
※参照:国土交通省
土地の軽減措置
以下の条件を満たした新築住宅の土地は、減免措置の対象となります。
・土地に建てた住宅が新築住宅の減免条件を満たしている
・土地を先に購入した場合は取得後3年以内に建物を建てること
・先に建物を建築している場合は1年以内に土地を取得すること
土地に対する減免措置は2つあり、これらは併用できます。
つまり「((土地の固定資産税評価額×1/2)× 税率)– 軽減額」で、土地の不動産取得税額が計算できます。2024年3月31日以降に取得した土地の場合は、「(土地の固定資産税評価額×税率)– 軽減額」で算出しましょう。
※参照:国土交通省
中古住宅の軽減措置
建物の軽減措置
中古住宅で不動産取得税の減免措置を受けるための要件は、以下の通りです。
・自ら居住するために所有する住宅であること
・住宅の延べ床面積が50~240㎡以下
・1982年1月1日以後に新築されていて新耐震基準を満たしている
中古住宅の不動産取得税額は、「(固定資産税評価額 -築年次ごとの控除額)× 税率」で計算できます。築年次ごとに定められた控除額は下記でチェックしてください。
土地の軽減措置
以下の要件を満たせば、中古住宅の土地で不動産取得税の減免措置を受けられます。
・住宅と土地の所有者が同一である
・建てた住宅が中古住宅の減免条件を満たしており、土地の取得が住宅取得前後の1年以内
中古の土地の場合でも、減免額の計算方法は新築の土地と同じです。「((土地の固定資産税評価額×1/2)× 税率)– 軽減額」または、「(土地の固定資産税評価額×税率)– 軽減額」で計算します。
※参照:東京都
鑑定士コメント
軽減措置の申請はいつまでにすれば良いのでしょうか?不動産取得税の減免措置を受けるためには申請が必要です。原則として不動産を取得してから、60日以内に申請してください。届いた納付書に従って納税額を収め、減免措置を申請したあとに払いすぎた納税額が還付される流れです。期限に間に合わなかった場合でも、5年以内であれば申請を受け付けてもらえます。適用条件を満たしている場合は、なるべく早く申請をおこないましょう。
不動産取得税を抑えるためのポイント

不動産取得税を抑えるためのポイント
不動産取得税をさらに抑えるための方法は、以下の3つです。
・軽減措置を最大限活用する
・不動産の取得時期を考慮する
・専門家に相談する
それぞれについて詳しく解説します。
軽減措置を最大限活用する
不動産取得税を抑えるためのポイントとして、軽減措置を最大限活用するという方法が挙げられます。条件を満たせば、土地や建物に対して軽減措置を適用することが可能です。
例えば新築住宅の場合、新築住宅の建物部分に対して軽減措置を適用するための条件は、以下の2つです。
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下
(賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下)
・個人の居住のための住宅
上記の条件を満たすことで、建物部分の固定資産税評価額から控除が受けられます。また、土地にかかる税に対する軽減も可能です。軽減措置が適用となる新築住宅の土地の条件は、以下のとおりです。
・建てられた住宅が、建物の軽減条件を満たしている
・住宅よりも土地を先に購入した場合、取得3年以内に建物を建てること
・建物の建築が先行している場合は、その土地を1年以内に取得すること
上記の条件を満たすことで、土地や建物にかかる税金を抑えられます。
※参照:東京都
不動産の取得時期を考慮する
不動産の取得時期によっても不動産取得税が変わります。不動産取得税の税率は、原則4%です。しかし、令和9年3月31日までに取得した土地と住宅については、税率が3%に引き下げられています。
上記のように、令和9年3月31日までの取得分に限り、税率が3%となります。この引き下げには特別な要件はないため、不動産の取得を予定している人はぜひこれを参考に取得時期を考えてみてください。
※参照:愛知県
専門家に相談する
不動産取得税を抑えるために、専門家に相談するのもひとつの手です。不動産取得税を軽減させるためには自身で申告を行う必要がありますが、初めての人にとって簡単なことではありません。
実際には税務署への申し出が必要となり、申告しない場合は税務署も対応してくれません。軽減措置は用意されているものの、税務署側から税の軽減に関する案内をすることは稀です。
そのため、税金についてもし不明点がある場合は、専門家である税理士を頼るのもよいでしょう。税理士に相談すれば、自身に合った節税効果の見込める方法を提案してもらえます。
税理士に相談する場合は、税の軽減に関する情報を事前に調べておくことで、より適切な方法を選ぶことができます。知識を頭に入れたうえで、相談に臨むとよいでしょう。
軽減措置を利用すれば不動産取得税の支払いは抑えられる

軽減措置を利用すれば不動産取得税の支払いは抑えられる
不動産を取得した場合、不動産取得税がかからないケースがあります。相続による取得や不動産価格が免税額以下など、非課税の条件をチェックしておきましょう。
不動産取得税対象であっても減免措置が受けられる可能性があります。新築住宅と住宅にわけて要件や控除額を紹介したので、ぜひ参考にしてください。
減免措置を利用すれば不動産取得税の支払いを抑えられます。不動産を取得したあと5年以内なら申請できるので、払いすぎた還付金を受け取りましょう。
#不動産取得税、#土地、#軽減措置

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
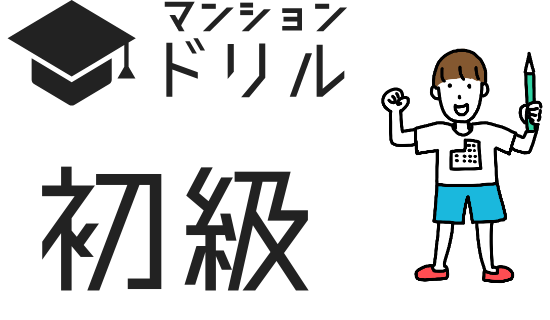
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。