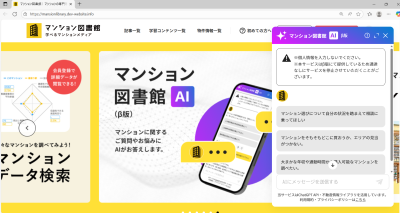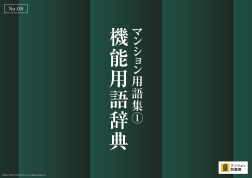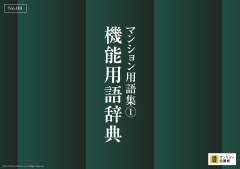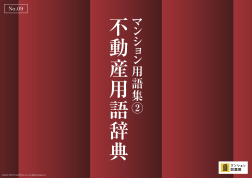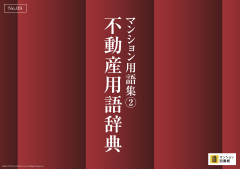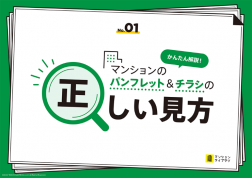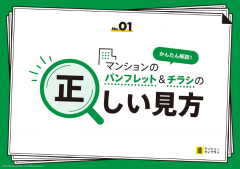全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.03.24
登録日:2025.03.14
沖積層とは? 地盤の基礎知識とマンション選びのポイント

マンションを選ぶ重要なポイントとして、耐震性を上げる人は少なくないでしょう。マンションの耐震性は、マンションそのものの構造だけではなく、その土地の地盤も大きく影響します。
沖積層という地盤を、聞いたことがある人がいるのではないでしょうか。沖積層は一般的に固まっていない軟弱な地層です。
本記事では、沖積層についての基礎知識やマンションの地盤と耐震性の関係、マンション選びのポイントなどについて解説します。地盤の固さの確認方法や沖積層は地震に弱いのかについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
沖積層とは

沖積層とは
沖積層とは、約1.8~2万年前から現在にかけて堆積した土砂によって形成された地盤のことです。
比較的新しい地盤であるため、地層がまだ固まっておらず、広範囲の地盤沈下や液状化が見られることもあります。
まずは沖積層についての基礎知識を知り、マンション選びのヒントにしてください。
・沖積層の特徴
・沖積層と洪積層との違い
・沖積層の分布
それぞれ解説していきます。
沖積層の特徴
沖積層は、主に以下の4つの層に分けられます。
・礫層
・砂層
・粘土層
・腐植土層
沖積層において、マンションの地盤として向いているのは「礫層」と「砂層」です。この2つの層は、よく締まっているため液状化が起こりにくい傾向があります。ただし、なかにはゆるい砂層もあり、地下水位が高い場合は液状化が起こりやすくなるので注意が必要です。
一方、 「粘土層」と「腐植土層」は、地盤が軟弱なためマンションの地盤には向いていません。とくに水分を多く含む腐植土層はスポンジのような性質をしていて、地盤沈下が起こりやすいです。
同じ沖積層でも、層によってマンションの地盤に向き不向きがあるため、よく確認する必要があるでしょう。
沖積層と洪積層との違い
沖積層と洪積層との違いは、地層が蓄積された年代の違いです。
今から約1.8~2万年前以降に蓄積された地層を沖積層とするのに対して、洪積層は約1.8~2万年以前の地層で構成されています。
洪積層は古い時代の地層であることから、水分量が少なく、固く引き締まった地盤が特徴です。このような性質から、建物の基礎を支える良質な地盤として利用されています。
沖積層と洪積層を正確に分別することは難しく、実際の判別は地層の色や土の性質などを肉眼で観察する方法が一般的です。
洪積層については以下の記事でくわしく解説しています。ぜひ参考にしてください。
沖積層の分布
沖積層は、海や河川によって移動しながら蓄積された地層で、川や海沿いに広く分泌しています。
とくに、海沿いの平野には広範囲の沖積層が分布しており、地層の中でも人々の暮らしに近い存在と言えるでしょう。
日本における沖積層は約13%(※)といわれていますが、主要な都市に集中して分布しているため、マンション建設では地盤対策が重要になります。
沖積層におけるマンションの耐震性

沖積層におけるマンションの耐震性
沖積層におけるマンションの耐震性は、地盤や耐震基準への理解が重要です。
・マンションにおける地盤の重要性
・耐震基準の変遷と沖積層への対応
2025年4月以降は耐震基準が強化されるため、沖積層への対応も知っておきましょう。
マンションにおける地盤の重要性
免震マンションの耐震性において、とくに重要となるのが地盤です。マンションは、下記3つのいずれかの構造によって耐震性を確保しています。
・免震
・制震
・耐震
免震とは、建物と地盤の間に「免震装置」を設置する構造です。地震が起きた際、そのエネルギーを免振装置が吸収することで、建物の揺れを抑えます。
制震とは、建物の柱や梁などの主要構造部材に「制震装置」を設置する構造です。地震エネルギーを制震装置が吸収することで、主要部材が損傷することを防ぐとともに建物の揺れを収束します。
一方で耐震は、装置を設置するのではなく主要構造部材をより頑丈なものにすることで、揺れに耐える構造です。地震エネルギーを吸収する装置がないため、建物がおおきく揺れてしまう可能性があります。
マンションでは、さまざまな耐震構造によって地震への備えを行っていますが、地盤が弱ければその効果は発揮できません。たとえ構造のおかげで建物が無事であっても、地盤沈下などによって地面が傾いてしまう恐れがあるからです。
耐震基準の変遷と沖積層への対応
地震が多い日本にとって、建物の耐震性は命や財産を守る重要な制度です。現在の耐震基準にいたるまで、旧耐震から新耐震への3度の大きな改正が行われています。
1950年に建築基準法にて制定された耐震基準は、震度5程度の地震で大きな損傷を受けないことが基準でした。一方、1981年に改正された新耐震では、震度6程度の地震を基準として耐震基準が変更されています。
また、省エネ性能の向上にともなう断熱材や太陽光パネルのような建材の重量化によって、2025年4月から耐震基準が引き上げられる予定です(※)。
このように耐震基準は時代とともに強化されていますが、沖積層のような柔軟な地層では地盤の固さに応じた基礎構造が重要になります。
マンションの地盤構造は、ボーリング調査での地質調査によって柔軟な地盤を特定し、堅固な支持地盤まで杭を打ち込むことで構造を支えます。
※参考:国土交通省
沖積層のマンション選びのポイント

沖積層のマンション選びのポイント
沖積層に建つマンション選びのポイントをご紹介します。
・地震への安全性を調べるための資料を確認する
・液状化対策の確認する
・信頼できる不動産会社を選択する
沖積層は日本の平野に多く分布しているため、新しく建設されたマンションの地盤が安全かどうか気になるかもしれません。
それぞれ解説していくので、マンションを選ぶ際の参考にしてみてください。
地震への安全性を調べるための資料を確認する
マンションを探す際、そのマンションの地盤がどのようなものか知ることは重要です。しかし、地面を見ただけではどのような地盤かわかりません。
その土地の地盤の良否を確認するには、下記3つの資料を確認するとよいでしょう。
・表層地質図
・土質柱状図
・液状化予測図
それぞれどのような資料か、詳しく解説します。
表層地質図
表層地質図とは、国土交通省が「5万分の1都道府県土地分類基本調査」として公開している、地表5メートルから数十メートルの表層の地表がどのような状態かを表した資料です。各種国土の開発・保全や土地利用などの計画策定を目的として、土地の自然要素である地形や表層地質、土壌などを縮尺5万分の1相当の精度でまとめられています。
各県や市区町村ごとにまとめられているため、検討している土地の表層地質をピンポイントで調べられるでしょう。昭和27年から順次更新されており、表層地質図を見れば沖積層や洪積層などの層の違いによる地盤の強弱を把握できます。
土質柱状図
土質柱状図とは、ある地点の地質断面図を見るための資料であり、ボーリングなどによる地質調査の結果を示したものです。
断面的な地質の構成や地層の硬さなどを知ることができ、該当の土地における地盤の構成や硬軟、支持基盤の深さがわかります。支持基盤とは、建物を支えるだけの耐力のある地盤のことであり、この地盤まで杭や基礎を設置することでマンションを安定した構造にできるのです。
土質柱状図で確認できるのは、あくまで過去に実際に調査したポイントのみの結果です。そのため、ポイント周辺は参考データとして見る必要があります。地下の地盤は、調査ポイントから数メートル離れると異なる場合もあるため、確認の際は注意が必要です。
土質柱状図について詳しく知りたい方は以下も読んでみてください。
液状化予測図
液状化予測図とは、地盤の液状化のしにくさ・しやすさを相対的に表した資料です。どの程度の地震で地面が液状化するかを、段階的に予測しています。
液状化とは、地震によって激しく揺さぶられた地盤が液体状になることです。砂層などの地盤は、砂の粒子が結びついて支えあっています。地震によって繰り返し揺さぶられることで地中の地下水の圧力が高くなってしまうと、その水分によって砂の粒子の結びつきが弱くなってしまい、地面が液状化してしまうのです。
地盤が液状化してしまうと、水よりも重い建物が沈んでしまったり、反対に軽いマンホールなどが浮き上がったりする場合があります。このような液状化の起こりやすさを知ることができるのが液状化予測図です。
液状化対策の確認する
沖積層のように未固結で液状化のリスクが懸念される地盤では、液状化対策が行われているかどうか確認しましょう。
一般的な液状化対策には以下のような方法があります。
信頼できる不動産会社を選択する
マンション選びは耐震構造や地盤への対策など、専門的な知識が必要になるため、信頼できる不動産会社に相談するのもひとつの方法です。
不動産会社の選び方は以下のようなポイントを参考にしてみてください。
・問い合わせ時の対応が誠実
・レスポンスが早い
・過去に行政処分や資格の更新を何度も行っていない
・評判や口コミを確認する
鑑定士コメント
耐震性にすぐれたマンションを見極めるコツは何でしょう?一番分かりやすいのが、マンションが分譲時に作られたカタログでしょう。1995年の阪神大震災、2011年の東日本大震災とそれぞれの契機により、マンションの耐震性はアピールポイントとして認知され、カタログに説明されることが多くなっています。支持地盤がどれくらいの深さで、杭を何本打っているか、という説明がビジュアル付で説明していることが多いです。
沖積層に関するよくある質問

沖積層に関するよくある質問
沖積層に関するよくある質問をまとめました。
・地盤の硬さはどのようにして確認する?
・新しくできた住宅地は地盤が良くない?
・沖積層のマンションは地震に弱いというのは本当?
ひとつずつ解説していきます。
地盤の硬さはどのようにして確認する?
地盤の硬さは、先述した「表層地質図」などのほかに、土地の高低を知ることでもある程度予測できます。地盤が軟弱になる原因のひとつは、液状化などの原因にもなる水分です。
周囲と比べて低い土地は、地下に水が集まってたまりやすい傾向にあります。また、過去に河川や湖、沼であった可能性も高いです。そのため、周囲と比べて地盤が軟弱な可能性があるでしょう。
地盤の軟弱さ以外にも、大雨の際などに浸水被害に遭う可能性も高いため、周囲と比較してできるだけ高い土地を選ぶのが無難です。地図を見ることで土地のある程度の高さはわかるため、一度確認してみるとよいでしょう。
新しくできた住宅地は地盤が良くない?
「新しくできた住宅は地盤がよくない」と聞いたことがある人がいるのではないでしょうか。結論から言うと、新しくできた住宅地だからといって地盤がよくないということはありません。
新しく住宅地を建設する際、かならず事前にボーリング調査などによって地質調査を行っています。その結果、住宅地として問題ないと判断されているため、一概に地盤が悪いわけではないということを認識しておきましょう。
沖積層のマンションは地震に弱いというのは本当?
沖積層に建つマンションが必ずしも地震に弱いというわけではありません。マンションの耐震化で重要なポイントは、「地盤へ打ち込む杭の深さ」です。
地盤が固い場所では直接基礎で建てられるマンションもありますが、沖積層のように軟弱な地盤の場合、その下にある固い支持層まで杭を打ち込む杭基礎が用いられます。
つまり、沖積層の地盤に建つマンションが「地震に弱い」という単純な認識は正確ではなく、地層によってどのような基礎構造を採用しているかが重要になります。
鑑定士コメント
良好な地盤を見分けるポイントは何でしょう?まずは記事にある通り、一般的に公開されている表層地質図、土質柱状図、液状化予測図を確認することです。その上で、個別のマンションが建てられた時のカタログに記載された内容も参考になります。また、ここらの土地は地盤が良い、良くないという情報は案外その土地で語り継がれ、長く住んでいる人は知っていることが多いです。例えば何代にも渡ってそこで商売をしているお店など、その地域の長老的な存在の人に聞いてみるのもいいかも知れませんね。
まとめ:地震に対する強さは地盤の状況も大切

まとめ:地震に対する強さは地盤の状況も大切
マンションの耐震性には、地盤の強さも大きく影響します。マンションを選ぶ際、構造による耐震性に目が行きがちですが、その土地の地盤にも目を向けて事前に確認しておきましょう。
地盤にはさまざまな種類があり、特にマンションの地盤に向いているのは洪積層です。また、礫層や砂層の沖積層も比較的向いている地盤でしょう。ただし、砂層の場合は周囲との高低差や地下水位などにも注意する必要があります。
土地の地盤を調べる際は、表層地質図や土質柱状図、液状化予測図の3つがあるため、必要に応じて確認が必要です。地盤の状況を確認して、地震に強いマンションを選びましょう。
#地層、#沖積層、#堆積、#地盤

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
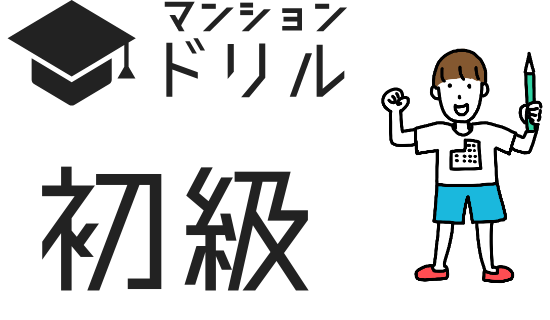
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。