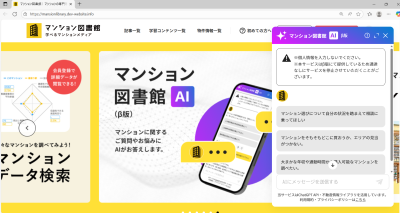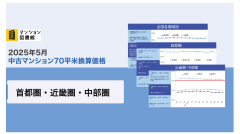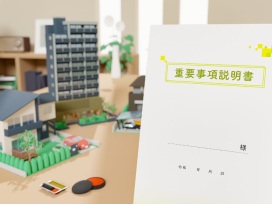全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.07.25
登録日:2025.07.25
不動産の共有名義とは?メリット・デメリットと後悔しないための基礎知識

「不動産を共有名義にするか迷っていて、メリットとデメリットが知りたい」
「共有名義にする手続きをする前に、知っておくべきことはある?」
不動産の共有名義について、このような疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では、不動産を共有名義にするメリットとデメリットを徹底解説します。共有名義にする前に必ず確認しておくべきことも具体的にわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
・不動産の共有名義とは、ひとつの不動産を複数人で所有している状態のこと
・売却・増改築時には全員の同意が必須であるなどのデメリットがある
・共有名義を検討する際は、後に起こりうるトラブルを想定したうえで慎重に決定する
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
不動産の共有名義の基礎知識

不動産の共有名義の基礎知識
不動産の共有名義に関する基礎知識について、以下の3点を順に解説します。
・不動産の共有名義とは複数人でひとつの不動産を持つこと
・各人が持つ権利の割合「持分」とは
・不動産が共有名義になる主なケース
不動産の共有名義とは複数人でひとつの不動産を持つこと
不動産における共有名義とは、ひとつの不動産を夫婦や兄弟などの複数人で所有している状態のことです。たとえば、兄弟3人でひとつの土地を所有しているとすると、その土地は共有名義ということになります。
相続においても同様です。遺言による遺産分割方法の指定がない場合、被相続人名義の不動産は、相続人が複数いる場合は相続人の共有状態となります。
なお、共有名義では法律で決められた行為の制限があります。詳細は以下のとおりです。
各人が持つ権利の割合「持分」とは
土地や不動産において、どれだけ所有権を持っているかという所有権の割合のことを、「持分」といいます。たとえば、兄弟3人が土地300㎡を均等の割合で所有しているとすると、3人の持分はそれぞれ100㎡です。
共有名義にする際は、登記において必ず持分を決めなければなりません。それぞれの持分は、上記のように均等に分けたり、遺産分割協議で決めた相続分の割合としたりする場合があります。
なお、持分割合は「登記簿謄本」に表示されており、法務局や一般財団法人民事法務協会のホームページで確認が可能です。
不動産が共有名義になる主なケース
不動産が共有名義となるケースはさまざまですが、主に以下の2つが挙げられます。
・不動産を複数人の兄弟で相続した場合
・夫婦で資金を出し合って不動産を共同購入した場合
不動産が共有状態となるきっかけの多くが相続です。たとえば、親が亡くなり兄弟3人で実家を相続したとします。遺産のなかでも、不動産の分割は厄介です。現金であればきっちりと分割できますが、不動産の場合は平等な分割が難しいとされています。
話し合いの結果、「揉めないようにひとまず共有名義にしておこう」と、不動産を共有名義で相続するケースがあるのです。
また、資金を出し合って不動産を購入する場合も、共有名義となります。たとえば、6,000万円のマンションを夫と妻が3,000万円ずつ出し合って購入した場合は、持分がそれぞれ1/2の共有名義です。
上記のように、不動産の購入で複数人がお金を出し合った際、出資の割合に応じた持分で登記することで共有名義となります。
不動産を共有名義にする4つのメリット

不動産を共有名義にする4つのメリット
不動産を共有名義にすることで、以下の4つのメリットが得られます。
・住宅ローン控除をそれぞれが受けられる
・売却時の3,000万円特別控除を各々が利用できる
・単独より高額なローンを組める可能性がある
・相続税評価額を抑えられる場合がある
それぞれについて解説します。
住宅ローン控除をそれぞれが受けられる
建物を共有名義とすることで、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。1人でローンを組むときと比べて、控除額が増える場合もあります。
具体的には、金額が5,000万を超える場合に、共有名義で住宅ローンを組むメリットが出ます。1人でローンを組む場合は、控除額の限度が35万ですが、複数人でローンを組むことで各々が控除を受けられるためです。
しかし、すべての場合において得になるわけではありません。それぞれの物件情報や、持分割合の設定などによっても変わるため、自分たちの場合はどうなのかを事前に確認しておきましょう。
売却時の3,000万円特別控除を各々が利用できる
居住用の財産であるマイホームを売ったとき、所有期間の長さに関係なく、最高で3,000万円まで譲渡所得から控除ができる特例があります。
3,000万円特別控除では、譲渡所得税が発生しなくなったり、軽減されたりする点がメリットです。
共有名義で不動産を持っていると、3,000万円特別控除をそれぞれが利用できます。たとえば2人で所有する物件が6,000万円で売れた場合、2人がそれぞれ特別控除を受けられるのです。
1人で物件を持っている場合と比べ、共有名義で物件を持っているほうが、トータルで見るとより多くの控除を受けられます。
ただし、以下の場合は控除を受けられないため、注意が必要です。
・特例の適用を受けることだけが目的の家屋
・家屋を新築する期間だけ仮住まいのために使った家屋
・別荘などのように娯楽・趣味・保養目的で所有する家屋
単独より高額なローンを組める可能性がある

単独より高額なローンを組める可能性がある
不動産を共有名義とすることで、1人の場合よりも高額なローンを組みやすくなります。
1人だけでは借りられないローン額だとしても、夫婦2人でそれぞれローンを組むことで高額物件を購入できる場合があります。
希望の不動産の購入が難しい場合は、収入状況を確認したうえで、共有名義での購入を検討するのもひとつの手です。
なお、持分割合は出資額の比率で決めます。2人で半分ずつ出資した場合、持分割合は1/2です。妻が半分を出資していても、夫の単独名義だと妻の負担分は夫からの贈与とみなされ、贈与税が発生するため注意しましょう。
相続税評価額を抑えられる場合がある
相続税評価額とは、「財産の価額」のことです。主に相続税の計算時に使われます。不動産を親子が共有名義で購入することで、相続税評価額を抑えられる場合があるのです。
たとえば不動産を親子が共有名義で取得し、「親ひとり・子ひとり」だった場合、親が所有していた持分割合の部分のみが相続されます。
そのため、親名義で所有する場合よりも、相続税を抑えることが可能です。 親が不動産を購入する際は、親子の共有名義で購入するのもよいでしょう。
不動産を共有名義にする5つのデメリット

不動産を共有名義にする5つのデメリット
メリットがある一方で、以下5つのようなデメリットもあります。
・売却・増改築には全員の同意が必須
・諸経費が名義人数分かかる
・相続が発生すると権利関係が複雑化する
・固定資産税やローン返済の連帯義務で揉めやすい
・離婚時の財産分与の手続きが複雑
それぞれについて順に解説します。
売却・増改築には全員の同意が必須
共有名義の不動産は、1人の意思だけで売却や増築といった不動産の活用方法を決定できません。なぜなら、ひとつの不動産に対して複数人が所有権を持っているからです。
実際に、共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の承諾を得る必要があります。仮に自分の持分割合が9割だったとしても、不動産全体の売却はできません。
家賃収入を得たい・高く売りたい・自分が住みたいなど、不動産を持つ目的が共有者間で異なる場合もあります。共有者と意見が一致しない場合もあるため、自分の思い通りに不動産を活用することが難しい点がデメリットです。
諸経費が名義人数分かかる
不動産を共有名義にする場合は、諸経費が人数分かかります。代表者1名が支払うのではなく、共有者がそれぞれ支払わなくてはなりません。
具体的には、不動産を購入する際に住宅ローンを組む場合、金融機関とローン契約を結ぶための手数料が必要です。また、不動産を登記する際の登記費用なども発生します。
上記のような手数料や登記費用といった諸費用が、名義人それぞれにかかります。単独名義で不動産を購入する場合よりも、トータルで見ると購入時の出費がかさんでしまう点には注意が必要です。
相続が発生すると権利関係が複雑化する
共有者が亡くなった際は、共有名義で所有していた不動産も相続の対象となります。
相続によって、ひとつの不動産の共有者が芋づる式に増えていくため、権利関係が複雑化する点がデメリットです。また、共有者が増える事により、不動産の管理や交渉なども難しくなっていきます。
このように、共有名義は相続が発生すると権利関係が複雑化しやすく、トラブルに発展してしまうと裁判になるケースも珍しくありません。
解決のためには費用や時間がかかる場合があるため、不動産を共有名義にする際は、相続を見据えた将来的なリスクを考えておくことが重要です。
鑑定士コメント
自分の持分だけを売ることは可能でしょうか?共有名義の不動産自体は、共有者全員の同意がなければ売却できません。しかし、自分が管理・所有している「共有持分」のみであれば、自分の意思で売却が可能です。勝手に売却すると、ほかの共有者とトラブルになる等さまざまなリスクがあるため、共有部分の売却は慎重に検討する必要があります。
固定資産税やローン返済の連帯義務で揉めやすい

固定資産税やローン返済の連帯義務で揉めやすい
固定資産税やローンの返済において、一部の共有者が支払いを滞納した場合、ほかの共有者に負担が生じるリスクがあります。
共有名義の不動産を所有するときは、通常の不動産の場合と同様に、固定資産税や修繕費用といった費用の支払いが必要です。支出は共有者それぞれの持分割合に応じて負担することが、民法で定められています(※)。
固定資産税の支払い通知書は、共有者のうち代表者1名に届くのが一般的です。そのため、代表者が立て替えて支払うことになりますが、ほかの共有者に請求しても支払って貰えないケースがあります。
このように、共有名義の不動産を持ち続けるなかでは、税金・維持費・ローン返済などの支払いの面で揉めやすいという点にも注意が必要です。
離婚時の財産分与の手続きが複雑
夫婦で共有名義とする不動産があった場合、後のトラブル回避のため、離婚時に財産分与の手続きをすることになります。
財産分与をするうえでは、共有名義の不動産を夫婦いずれかの単独名義に変更しなければなりません。具体的には、離婚協議書を作成し、法務局で所有権の移転登記申請をします。
また、共有名義の不動産に住宅ローンなどの負債が残っている場合は、さらに金融機関の承諾が必要です。承諾を得ず勝手に単独名義に移すと、ローン契約に従い一括返済を迫られたり、抵当権を行使されたりすることがあります。
上記のように、法務局や金融機関などでさまざまな手続きが必要です。
不動産の共有名義を単独名義へ変更する方法

不動産の共有名義を単独名義へ変更する方法
離婚や相続などの事情で、共有名義を単独名義へと変更する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、不動産の共有者との間に「同意がある場合」と、「同意がない場合」の2パターンにわけて解説します。
同意ありの場合
共有状態にある不動産を単独名義へと変更する場合、ほかの共有者全員の同意を得る必要があります。不動産を単独名義にするための登記において、共有者全員の印鑑登録証明書が必要となるためです。
事前に共有者同士で話し合い、単独名義にすることへの同意を得ておきましょう。同意を得たあとは、単独名義へ変更するにあたり、以下の流れで手続きをすすめます。
1.必要書類を収集する
2.登記申請書を作成する
3.法務局へ申請する
4.登記識別情報などを受領する
基本は上記の流れで手続きを行いますが、どのような経緯で名義変更するかによって、手続きの流れが異なる場合もあるため注意しましょう。また、登記申請書は法務局公式サイトからダウンロードできますので、申請前に作成しておくとスムーズです。
同意なしの場合
不動産の共有者から同意が得られない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談する方法がおすすめです。
共有不動産の活用や処理について、共有者同士で話し合いがまとまらないケースも少なくありません。意見がまとまらず、不動産の名義変更ができずにいる間にも、固定資産税や維持・管理の費用といったコストは発生し続けます。
また、不動産を放置してしまうと自身の子どもや孫の世代までトラブルの解消を先送りにすることになるため、できるだけ迅速に対応しましょう。
共有持分のトラブルに関しては、交渉スキルや法律の知識が必要です。共有者同士での話し合いがすすまない場合は、専門知識を持つ司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう。
鑑定士コメント
住宅ローンが残っている家でも共有名義を解消できるのでしょうか?共有名義の解消は、基本的には住宅ローンが完済していなければできません。しかし、不動産の売却価格が住宅ローンの残高を上回る場合は、不動産を売却するという方法が選択できます。売却によって得た資金を住宅ローンの支払いに充てられ、売却することで共有名義状態は解消されます。共有名義を解消したい場合は、住宅ローンの残高を上回るかを一度確認してみるとよいでしょう。
これから不動産を共有名義にする前に必ず確認すべきこと

これから不動産を共有名義にする前に必ず確認すべきこと
不動産をこれから共有名義にするという人に向け、事前に確認しておいたほうがよいことを紹介します。
・持分割合は「実際に出資した金額の割合」で登記する
・将来起こりうるリスク(離婚・相続など)を書面で取り決めておく
・迷ったら安易に共有名義にしない
上記3つについて順に解説します。
持分割合は「実際に出資した金額の割合」で登記する
共有持分は、基本的に「自己負担額÷購入代金」により求められた割合で設定されます。
計算の間違いや勘違いをしたり、割合を無視して持分を登記してしまうと、贈与とみなされる場合があります。贈与とみなされると、受けられるはずの控除が受けられなかったり、税金が課せられたりする恐れがあるため注意しましょう。
登記の際、もしも持分の決め方に不安や疑問がある場合は、不動産に詳しい税理士や弁護士などの専門家に相談することが大切です。
将来起こりうるリスク(離婚・相続など)を書面で取り決めておく
不動産を共有名義にする場合は、離婚や相続といったリスクを想定し、事前に書面で取り決めをしておくことがおすすめです。
仮に、離婚後に夫婦の片方が共有名義の家に住み続ける場合、住宅ローンの返済や残りの持分の扱いなどの対処法を考える必要があります。
相続の場合は共有人が増えることにより、不動産の管理や協議が複雑になることが考えられます。
いざというときにスムーズに対処できるよう、想定されるケースに応じた対処法を決め、書面で保存しておくとよいでしょう。
迷ったら安易に共有名義にしない
不動産を共有名義にするか迷ったときは、さまざまなリスクやデメリットをいま一度考え、慎重に判断する必要があります。
もし、不動産の相続にあたって兄弟で平等に分けるために、共有名義にするか悩んでいる場合はほかの手段を一度検討するのがおすすめです。
不動産を売却して現金で分けたり、相続する金額を不動産以外の財産で調整したりと、共有名義にしない方法もいくつかあります。
さまざまな方法を検討し、状況に合わせた最適な方法を選ぶようにしましょう。
不動産に関する専門用語について詳しく知りたい人は、以下を参考にしてください。資料は無料でダウンロードできます。
まとめ:不動産の共有名義はメリットとリスクを天秤にかけて、専門家に早めの相談を

まとめ:不動産の共有名義はメリットとリスクを天秤にかけて、専門家に早めの相談を
不動産の共有名義とは、ひとつの不動産を兄弟や夫婦など複数人で所有している状態のことです。兄弟3人でひとつの土地を所有している場合などが当てはまります。
不動産を共有名義とする場合、住宅ローン控除や売却時の3,000万円特別控除を、共有人それぞれが受けられる等のメリットがあります。
一方、売却・増改築には全員の同意が必須であったり、相続が発生すると権利関係が複雑化したりとさまざまなリスクもあります。
共有名義を検討する際は、後のトラブルを回避するため、メリットとデメリットをよく考えたうえで決定することが大切です。
また、不動産を共有名義とした後にトラブルがあった際は、専門知識をもつ税理士や弁護士などに早めに相談するようにしましょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
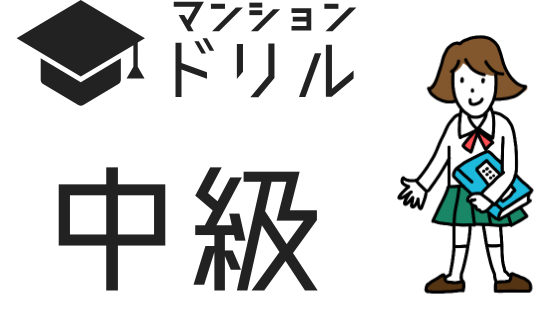
マンションドリル中級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。