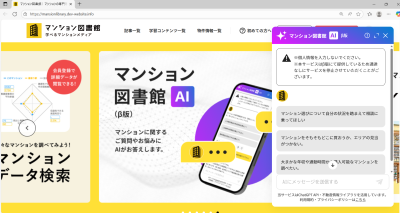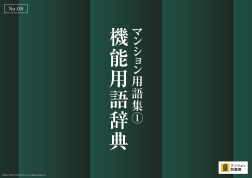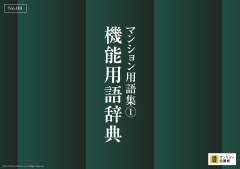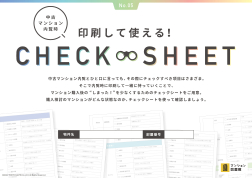全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.05.26
登録日:2025.05.26
建築設備定期検査を徹底解説!検査対象から流れまでまるごと解説

「建築設備定期検査とは?」
「建築設備定期検査の対象は?」
建築設備定期検査について、上記の疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、建築設備定期検査の基礎知識を解説します。加えて、検査の対象となる設備、検査の流れ、依頼先を選ぶ際のポイントなども紹介するので、建築設備定期検査について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
・建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づいて行われる検査のこと
・換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備が検査の対象
・検査の流れと依頼先を選ぶときの注意点
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
建築設備定期検査の基礎知識

建築設備定期検査の基礎知識
建築物の安全性や快適性を保つためには、定期的な設備の点検が欠かせません。
ここでは「建築設備定期検査」について、その概要や対象となる建築物、特定建築物定期検査との違い、調査の実施回数など、基本的な知識をわかりやすく解説します。
建築設備定期検査とは
建築設備定期検査は、建築基準法第12条第3項に基づいて行われる検査です。(※)
換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備などが、適切に設置・維持されているかを点検し、その結果を特定行政庁へ報告します。
建築設備定期検査の目的は、ふだんの生活だけでなく、火災や地震などの非常時にも、建物を安心して使えるようにすることです。
特に人が多く集まるマンションや商業施設などの建物では、設備が正しく作動しないと被害が拡大する可能性が高まります。
そのため、建物の所有者や管理者には定期的な検査と報告が義務づけられているのです。
※ 参照:建築基準法
建築設備定期検査が必要な建築物の種類
建築設備定期検査はすべての建物に必要なわけではありません。不特定多数の人が利用する次のような建物が対象となります。(※)
特定建築物定期検査との違い
建築設備定期検査と似た言葉に、「特定建築物定期調査」があります。どちらも建築基準法第12条に基づく法定点検であり、特定行政庁から指定された建築物に対して実施が義務づけられています。
名前が似ているため混同されやすいですが、実際には異なる内容の検査です。
両者の大きな違いは、検査の対象です。建築設備定期検査では、以下の4つの設備が対象となります。
・換気設備
・排煙設備
・非常用の照明装置
・給排水設備
一方、特定建築物定期調査は、「建物本体」の安全性を確認するための調査です。敷地や屋上、外壁、天井、避難経路など、建物の内外にわたって幅広く点検が行われます。
いずれも建物の安全を守るうえで欠かせない検査ですが、それぞれの目的と内容を正しく理解しておくことが大切です。
建築設備定期検査を行う回数
建築設備定期検査の実施回数は、原則年に1回です。
そのうえで、建物が新築か既存かによって、初回の検査時期が異なります。
具体的な実施時期は、次のとおりです。
・新築の建物:検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して、2年以内に初回の定期検査を行う
・既存の建物:前回の報告から1年以内に検査と報告を行う
なお、やむを得ず1年以内に報告できない場合でも、年度内であればその年の検査として認められる場合があります。
鑑定士コメント
建築設備定期検査は、建築基準法に基づく法定点検です。そのため、対象となる建物の所有者や管理者は、必ず実施しなければなりません。定期報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりした場合は、100万円以下の罰金が科される可能性があります。建物の安全を守るためにも、必ず検査を受けるようにしましょう。
建築設備定期検査の対象

建築設備定期検査の対象
建築設備定期検査の対象は、以下の4つの設備です。
・換気設備
・排煙設備
・非常用の照明装置
・給排水設備
以下でそれぞれの設備の検査内容について解説します。
換気設備
換気設備は、室内の汚れた空気を排出し、新鮮な空気を取り入れるための設備です。粉じんや臭気、有害ガスなどを外へ逃がし、清浄な空気を取り込むことで、室内の空気環境を快適かつ安全に保ちます。
検査では「給気設備」と「排気設備」の2種類を対象に、以下の点を確認します。
換気設備の不具合は、健康被害や事故の原因にもなりかねません。安全な建物環境を維持するためにも、定期的な検査が必要です。
排煙設備
排煙設備は、火災時に発生する煙や一酸化炭素などの有害なガスを建物の外へ排出するための設備です。煙は視界を奪うだけでなく、中毒や窒息の原因にもなるため、排煙設備は人命を守るうえで欠かせません。
排煙方式には「自然排煙方式」と「機械排煙方式」の2つがあります。
排煙設備は非常時以外は作動しないため、不具合に気付きにくい設備です。故障や経年劣化によるトラブルを防ぐためにも、定期的な点検が欠かせません。
なお、排煙設備を含む消防設備全体の種類や点検・維持管理については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
非常用の照明装置
非常用の照明装置は、地震や火災などで停電が発生した際、自動で点灯し、避難を助けるために使われる設備です。建物内が暗くなっても、通路や室内を照らすことで混乱を防ぎ、安全な避難をサポートします。
照明装置には、内蔵型や外部電源型の蓄電池、LEDや蛍光灯の光源など、いくつかの種類があります。共通して求められるのは、「周囲温度70度の非常時でも30分以上点灯し、必要な明るさを保つこと」です。
主な点検内容は、次のとおりです。
・停電時に正常に点灯するか
・必要な明るさが確保できているか
・設置場所に問題がないか
・周囲に障害物がないか
・配線や充電の状態に異常がないか
上記の点を確認し、不具合があれば早期に修理・交換を行います。
非常時に照明が作動しなければ、転倒やパニックを引き起こすおそれがあります。普段使わない設備だからこそ、定期的な点検が重要です。
給排水設備
給排水設備は、建物に水を届け、使った水を安全に外へ流すための設備です。「給水設備」は生活用水や飲み水を送り込む仕組み、「排水設備」は使い終わった水を下水に流す仕組みを指します。
点検では、「給水設備」と「排水設備」の両方を確認します。
給水設備では、受水槽や高架水槽、給水ポンプなどが正しく設置され、正常に作動しているかをチェックします。サビや異物が混ざっていないかも重要な確認ポイントです。
排水設備では、排水管や汚水槽、空気の通り道である通気管に、詰まりや傷みがないかを調べます。雨水の流れや浄化槽も点検対象です。
給排水設備がうまく働かないと、水が使えなかったり、においや汚れが建物に広がったりしてしまいます。水は人の健康や衛生に大きく関わるため、点検が必須です。
中古マンションを選ぶ際に気をつけたいのが、「設備」の状態です。具体的にどのような点に気をつけてチェックすればいいのか、以下の資料にまとめています。ぜひご活用ください。
建築設備定期検査の流れ

建築設備定期検査の流れ
建築設備定期検査は、法律に基づき決められた手順に沿って進める必要があります。あらかじめ流れを把握しておくことで、スムーズに対応することができるでしょう。
一般的な流れは、以下のとおりです。
・検査通知書が届く
・検査を依頼する会社を選ぶ
・書類を検査会社に提出する
・建築設備定期検査を実施する
・報告書を提出する
検査通知書が届く
建築設備定期検査の時期が近づくと、特定行政庁から建物の所有者または管理者に対して、定期報告を求める通知書が届きます。
通知書には、以下のような内容が記載されています。
・対象となる建築物の情報
・提出が必要な書類の内容
・前回の報告日
・検査・報告の期限
・提出先
ただし、自治体によっては通知書が届かない場合もあります。通知がなくても報告義務はあるため、自身で検査時期を把握しておくことが重要です。
検査を依頼する会社を選ぶ
建築設備定期検査は、専門の資格を持った人しか行えません。そのため、検査会社に依頼するのが一般的です。
依頼する際は、一社だけでなく複数の会社から見積もりを取りましょう。費用のほか、対応のていねいさや説明のわかりやすさなども比較できます。
また、建築設備定期検査は地域によって内容が異なることがあります。地元のルールに詳しい会社を選ぶと、安心して任せられるでしょう。
書類を検査会社に提出する
検査会社が決まったら、必要な書類を提出します。
初回の検査では、建物や設備の情報がわかる以下の書類が必要です。
・確認申請書
・確認済証
・検査済証
・建物所有者・管理者情報
・意匠図面
・設備図面
2回目以降の検査では、次の書類で対応できる場合が多いです。
・前回の報告書
・建築平面図
提出書類は多岐にわたるため、不明点があれば検査会社に確認するようにしましょう。
建築設備定期検査を実施する
必要書類を提出すると、建築設備定期検査が行われます。
検査の対象となる換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備の4つの設備が正しく設置され、正常に作動しているかどうかを、専門の検査員が確認します。
検査は検査会社が実施するため、管理者が立ち会う必要はありません。ただし、設備の位置確認や作動チェックのために、連絡や立ち入りの協力を求められることがあります。
報告書を提出する
検査が終わると、検査会社から「建築設備定期検査報告書」が送付されます。内容を確認し、問題がなければ特定行政庁に提出します。
多くの場合は検査会社が代理で提出しますが、だれが提出するのかを事前に確認しておくと安心です。なお、建物の所有者と管理者が異なる場合、報告義務は「管理者」にあります。
報告書が受理されると、「建築設備定期検査報告済証」が発行されます。提出を忘れると罰則の対象になることがあるため、必ず期限を守りましょう。
鑑定士コメント
建築設備定期検査は、誰でも行えるわけではありません。一級建築士や二級建築士、建築設備検査員など、法律で定められた資格を持つ専門の技術者のみが実施できます。そのため、多くの場合は検査会社に依頼して検査を行います。正しい知識と資格を持つ専門家に任せることで、安全性を確保できるでしょう。
建築設備定期検査の費用目安

建築設備定期検査の費用目安
建築設備定期検査にかかる費用目安は以下のとおりです。
建物の延床面積や用途などによって金額は変動します。
また、検査の費用以外に報告書の作成費用が30,000~45,000円程度、行政への手続き代行費用として8,000~15,000円がかかります。
業者によっては調査員の交通費の実費も別途かかる場合があるので、業者に見積もりを依頼して正確な費用を確かめるのがよいでしょう。
建築設備定期検査の依頼先を探すときのポイント

建築設備定期検査の依頼先を探すときのポイント
建築設備定期検査は専門性が高いため、信頼できる会社に依頼することが大切です。依頼先を選ぶ際は、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
・検査の実績が豊富かどうか
・問い合わせに誠意を持って対応しているか
・明確な料金設定をしているか
検査の実績が豊富かどうか
建築設備定期検査を依頼する際は、その会社に十分な実績があるかを確認しましょう。建物の形や設備はそれぞれ異なるため、豊富な現場経験があるほど、状況に応じた的確な判断ができるためです。
目安として、年間200件以上の検査を行っている会社であれば、対応力や信頼性も高いといえます。
実績がある会社は、検査の流れや人員の手配もスムーズです。また、ムダのない計画によって費用を抑えられる場合もあります。
安心して任せるためにも、まずは実績の多さを確認することが大切です。
問い合わせに誠意を持って対応しているか
検査会社を選ぶ際は、問い合わせへの対応も重要なポイントです。以下のようなトラブルが起こると、管理者側が大きな負担を負うことになってしまいます。
・急に連絡が取れなくなり、対応に困る
・検査会社が廃業し、過去の記録が残っていない
・検査内容の説明がなく、何を改善すべきかわからない
・質問しても曖昧な回答しかなく不安が解消されない
検査後のサポートやアドバイスも含めて、丁寧に対応してくれる会社を選びましょう。
明確な料金設定をしているか
検査会社を選ぶ際は、料金が明確に提示されているかを必ず確認しましょう。建築設備定期検査の費用は法律で定められておらず、会社ごとに自由に決められるからです。
料金の内訳が不明確なまま依頼すると、あとで「追加作業費」として高額な請求を受けるケースもあります。
見積もり内容をしっかり確認し、料金設定が明確な会社を選ぶようにしてください。
まとめ:建築設備定期検査は建築基準法で義務づけられている

まとめ:建築設備定期検査は建築基準法で義務づけられている
建築設備定期検査は、換気、排煙、非常用照明、給排水などの設備が正しく設置・維持されているかを確認する点検です。
検査を怠ると、事故や災害時の被害が拡大するおそれがあるほか、報告義務違反として罰則を受ける可能性もあります。
万が一に備え、毎年確実に建築設備定期検査を実施することが大切です。
#報告、#設備、#建築設備、#検査

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
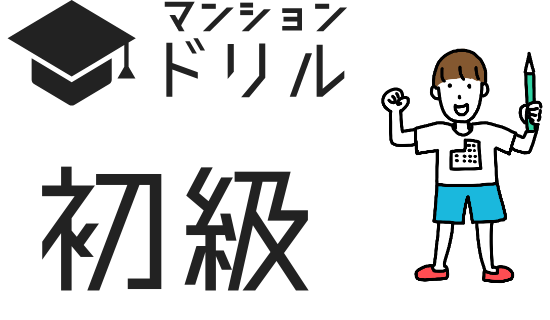
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。