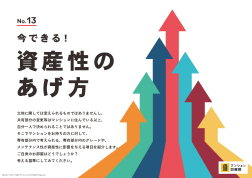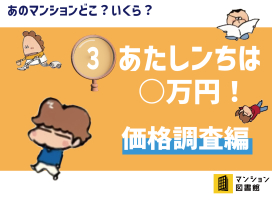全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.03.24
登録日:2025.03.24
消防設備とは?種類・設置基準・点検・維持管理まで徹底解説

消防設備は、火災を素早く検知し、消火や避難を助けるために不可欠です。しかし、設置しているだけでは安心できません。
点検を怠ると、警報が鳴らない・消火器が使えない・避難経路が塞がれるなど、いざという時に機能せず大きな被害を招く恐れがあります。
火災時に設備が確実に作動するためには、日頃から適切な管理が必要です。本記事では、消防設備の種類や設置基準、維持管理の重要性についてわかりやすく解説します。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
消防設備とは

消防設備とは
消防設備は、火災を防ぎ、消火や避難を助けるために設置される設備です。正式には「消防用設備」と呼ばれ、学校や病院、会社、飲食店など、多くの建物で設置が義務付けられています。
火災は一瞬で燃え広がり、大きな被害をもたらします。そのため、消防設備を設置し、しっかり管理することが重要です。
また、法律で定期的な点検が義務付けられており、常に正しく作動する状態を保つ必要があります。
万が一の火災に備え、日頃から設備の管理を徹底しておくことが重要です。
消防設備の定義
消防設備は、火災を防ぎ、消火や避難を助けるために設置される設備です。消防法第17条では、「消防のために使う設備、消防用の水、消火活動に必要な施設」と定められています。(※1)
また、消防法施行令第7条により、消防設備は以下の4つに分類されます。(※2)
・消火設備(消火器・スプリンクラーなど)
・警報設備(火災報知器・非常ベルなど)
・避難設備(避難はしご・救助袋など)
・消防活動に必要な設備(排煙設備・連結散水設備など)
火災時に設備が正しく作動すれば、被害を抑え、人命を守ることができます。
そのため、法律で設置が義務付けられており、定期的な点検と適切な管理が必要なのです。
※1 参照:消防法
※2 参照:消防法施行令
消防設備の必要性
消防設備は、火災の被害を抑えるために欠かせません。火は一瞬で燃え広がるため、早期発見と迅速な対応が必要です。例えば、自動火災報知設備があれば、煙や熱を感知して警報を鳴らし、避難を早めることができます。
また、法的な面でも消防設備は重要です。消防法では、一定の規模や用途の建物に対し、消防設備の設置と定期点検が義務付けられています。違反すると罰則が科されることもあり、法律の観点からも適切な管理が求められます。
消防設備が整っていれば、命を守るだけでなく、建物を利用する人々の安心にもつながるでしょう。
消防設備と防火設備の違い
「消防設備」と「防火設備」はどちらも火災対策に欠かせませんが、役割が異なります。
「消防設備」は、火災の発生を感知し、消火や避難を助ける設備です。消防法に基づき、消火器や自動火災報知器、誘導灯、屋内消火設備などが設置されます。消防設備は火災時だけでなく、地震などの災害時にも活用されることがあります。
「防火設備」は、炎や煙の拡散を防ぎ、避難経路を確保する設備です。建築基準法に基づき、防火戸、防火シャッター、防火スクリーンなどが設置されます。炎や煙から人々を守ることが主な役割で、他の災害で使用されることはほとんどありません。
消防設備の種類

消防設備の種類
消防設備は、大きく以下の4つに分類されます。
・消火設備
・警報設備
・避難設備
・消防活動に必要な設備
以下でそれぞれについて解説します。
消火設備
消火設備は、火災時に水や消火剤を使って火を消すための設備です。主な種類は以下のとおりです。
・消火器・簡易消火用具
・屋内・屋外消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・粉末消火設備
「消火器」は初期段階での消火に使用される、最も基本的な設備です。
「消火栓設備」は、ホースを使い、建物の内外で水を噴射して消火します。「スプリンクラー」や「水噴霧設備」は、火災時に自動で作動し、火の広がりを抑えます。
「不活性ガス消火設備」は、酸素を減らして炎を弱め、火を消す仕組みです。「粉末消火設備」は、粉をまいて空気を遮り、燃えるのを防ぎます。
警報設備
警報設備は、火災やガス漏れ、漏電などを検知し、警報や通報をおこなう設備です。代表的な設備は以下のとおりです。
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・火災通報装置
・住宅用火災警報器
「自動火災報知設備」は、熱や煙を感知し、警報を鳴らして火災を知らせる設備です。「ガス漏れ火災警報設備」は、ガスを検知し、爆発や火災を防ぐために警報を発します。
「漏電火災警報器」は、電気の漏れを感知し、火災を未然に防ぐ設備です。「火災通報装置」は、火災が発生した際に自動で消防へ通報します。
「住宅用火災警報器」は、家庭内で火災を早期に感知し、警報音や音声で住民に知らせます。
避難設備
避難設備は、火災時に安全に避難するための設備です。主な種類は次のとおりです。
・避難はしご
・緩降機(かんこうき)
・救助袋
・避難すべり台
・避難ロープ
・誘導灯・標識
「避難はしご」は、高所からの避難に使用されます。「緩降機」は、ロープを使い、体の重さでゆっくり降下する設備です。
「救助袋」は、筒状の袋の中を滑って降りる避難方法です。「避難すべり台」はらせん状や直線状の形状で、短時間に多くの人が避難できます。
「避難ロープ」は、ロープをつかみながら降下する設備です。「誘導灯・標識」は、非常口や避難経路を示し、安全な避難をサポートします。
消防活動に必要な設備
火災時に消防隊の消火活動を助ける設備には、以下のものがあります。
・排煙設備
・連結散水設備
・非常用コンセント設備
・連結送水管
「排煙設備」は、火災で発生した煙を外に逃がすための設備です。「自然排煙設備」は煙の上昇を利用し、機械排煙設備はダクトを通じて強制的に排煙します。
「連結散水設備」は、地下街や地下階に設置される設備で、天井の散水ヘッドから水を放出して消火を助けます。
「非常用コンセント設備」は、消防隊が消火や救助活動をおこなうときに使う機器の電源を確保する設備です。
「連結送水管」は、消防隊がホースをつなぎ、火災が起きた階まで水を送るための設備です。消火活動が難しい高層建築物や地下街に設置されます。
消防設備の設置基準と法律上の要件

消防設備の設置基準と法律上の要件
消防設備は、火災から人命や財産を守るために法律で設置が義務付けられています。建物の種類や規模によって必要な設備が異なり、適切な基準に従って設置しなければなりません。
また、地域ごとに独自の条例がある場合もあります。
ここでは、消防法に基づく設置義務や建物ごとの基準、地方自治体の規制について解説します。
消防法に基づく設置義務
消防法第17条では、多くの人が利用する建物には火災を防ぐための設備を設置し、適切に管理する義務があると定めています。
対象となるのは、以下のような建物です。
・学校
・病院
・工場
・飲食店
・百貨店
・地下街
・複合施設
上記の施設の管理者は、火災時に安全に消火や避難ができるよう、技術基準に従って消防設備を設置し、適切に管理しなければなりません。
設備が正常に機能すれば、火災による被害を最小限に抑えることができます。
建物の用途・規模別の設置要件
消防法では、建物の用途や規模に応じて適切な消防設備の設置が義務付けられています。
事務所の場合、延べ床面積1,000㎡以上で自動火災報知器、300㎡以上または3階以上・地階・無窓階で50㎡以上で消火器の設置が必要です。
飲食店は、延べ床面積150㎡以上で消火器の設置が義務付けられています。火を使用する設備がある場合は規模に関係なく必要です。また、スプリンクラー設備やガス漏れ火災警報設備、避難器具なども、基準に従って設置しなければなりません。
地方自治体ごとの追加規制や条例
消防法には全国共通の基準が定められていますが、地方自治体ごとに独自の規制を設けることが認められています。
地域の気候や風土により、国の基準だけでは防火対策が不十分になる場合があるためです。
例えば、人口密度が高い市街地では消火設備の追加が求められる場合があります。
条例による上乗せ規制によって、地域ごとの防火対策が強化されているのです。
鑑定士コメント
消防法第17条により、防火対象物の関係者には、消防用設備を適切に設置・維持管理する義務があります。そのため、故障や損傷を放置すると法律違反となるため、注意が必要です。それだけでなく、火災時に警報が鳴らない、消火設備が使えないなどの危険も。いざという時に命を守るためにも、異常を見つけたらすぐに修理や交換をおこないましょう。
消防設備の点検方法

消防設備の点検方法
消防設備は、火災時に確実に作動するよう、法律で点検の実施が義務付けられています。ここでは、消防設備の点検方法について解説します。
消防設備点検の重要性
消防設備の点検は、火災による被害を防ぐために欠かせません。
消火設備が正常に作動しなければ初期消火が遅れ、火災が拡大する恐れがあります。避難経路の確保が不十分な場合は、逃げ遅れによる人的被害が増える可能性も高まるでしょう。
また、消防法では、定期的な消防設備の点検が義務付けられています。点検や報告を怠ると、法律違反となり、罰則や消防署からの指導を受けることがあります。
消防設備は、万が一の火災時に確実に作動しなければ意味がありません。日頃から点検・整備をおこない、異常があれば速やかに修理・交換し、安全な環境を維持することが大切です。
機器点検と総合点検の違い
消防設備点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。
「機器点検」は、半年に1回実施する点検です。消火器や火災報知器などの外観を目視で確認し、必要に応じて簡単な操作をおこない、正常に作動するかをチェックします。
「総合点検」は、1年に1回実施し、機器点検に加えて消防設備全体の機能を詳しく確認します。設備を実際に作動させ電流測定や感知器の反応テストをおこなうため、専門の技術者が担当しなければなりません。
どちらの点検も消防設備が確実に機能するために不可欠です。定期的に実施し、万が一の火災に備えましょう。
点検記録の保管
消防設備点検の報告書は、点検日から「3年間」保管することが義務付けられています。
3年を過ぎた後も、「点検結果総括表」「点検者一覧表」「経過一覧表」は引き続き保存しなければなりません。
点検記録を適切に保管することで、次回の点検準備がスムーズになります。
また、火災や設備の不具合が発生した際、適切な管理をおこなっていた証拠ともなるため、しっかり保管しておきましょう。
消防設備士の役割
消防設備士は、建物に設置された消防設備の点検・整備・工事をおこない、火災時に確実に作動するよう管理する職業です。消火器や自動火災報知設備、消火栓設備、スプリンクラーなどを設置し、異常があれば修理や交換をおこないます。
特に、多くの人が利用する商業施設や高層ビルでは、消防設備士の点検が義務付けられています。適切な点検と維持管理がおこなわれていなければ、火災が発生した際に大きな被害につながるためです。
消防設備士は、火災の被害を最小限に抑え、安全な環境を守るために欠かせない存在なのです。
鑑定士コメント
消防設備の不具合を放置すると、火災時に作動せず、取り返しのつかない被害につながる恐れがあります。さらに、法律違反となり、罰則が科される可能性も。点検報告を怠ると30万円以下の罰金、設置命令違反では1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。また、消防法の改正により、事業主には最大1億円の罰金が課される場合もあるため、適切に管理しましょう。
消防設備を設置するための手続き

消防設備を設置するための手続き
消防設備を設置する際は、届出が必要です。設置後は、法律に基づき定期的な点検と報告をおこなう義務があります。
また、改修や変更をする場合も、所定の手続きを遵守しなければなりません。
ここでは、設置の届出、点検結果の報告、改修時の手続きについて解説します。
消防設備の設置届出
建物に消防設備を設置した場合、工事完了後4日以内に消防署へ届出が必要です。
届出をおこなうのは、建物の所有者や使用者です。工事を担当した業者ではありません。
届出方法は、電子申請・窓口・郵送の3種類です。
設備の種類によって、添付する書類が異なります。主な書類は、防火対象物の概要表、平面図、立面図、設備の機器仕様書などです。
届出後、消防署の検査を受ける必要がありますが、内容によっては省略される場合もあります。
点検結果の報告
設置時の報告で終わりではなく、定期的な点検報告が必要です。建物の用途に応じて、決められた頻度で消防署へ報告しなければなりません。
・百貨店・旅館・病院などの特定防火対象物:1年に1回
・共同住宅・事務所・工場などの非特定防火対象物:3年に1回
報告書は定められた様式で作成し、建物の所有者・管理者・占有者が提出します。点検で不良箇所が見つかった場合は、改修計画を立て、備考欄に改修時期を記載しなければなりません。
報告方法は、消防署への直接提出、郵送、電子申請のいずれかです。
改修・変更時の手続き
消防設備の点検で不具合が見つかった場合や、設備の型式が失効した場合、さらに建物の用途変更や増改築をおこなう際には、消防設備の改修が必要です。改修や変更をする際は、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
改修・変更に関する主な手続きには、次の報告書が必要です。
・点検で発覚した不具合の改修報告:消防用設備等点検報告改修計画書
・防火対象物点検報告で発覚した違反の改修報告:防火対象物点検報告改修計画書
・消防署の指摘による改修報告:改修(計画)報告書
報告書の提出期限は法律で明確に定められていませんが、2週間以内が目安です。
まとめ:いざという時に頼れる消防設備は日頃の備えが大切

まとめ:いざという時に頼れる消防設備は日頃の備えが大切
消防設備は、火災から人命や財産を守るために欠かせません。ただし、設置しているだけでは意味がなく、定期的な点検や適切な維持管理が重要です。
消防法では、消防設備の点検や改修が義務付けられており、違反すると罰則が科されることもあります。また、設備の不具合が見つかったり、建物の増改築をおこなったりする場合は、消防署への届出や報告が必要です。
万が一の火災に備え、日頃から点検をおこない、消防設備を万全な状態に保ちましょう。しっかり準備しておけば、いざという時にも安心です。
#消防、#消防用設備、#消火

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
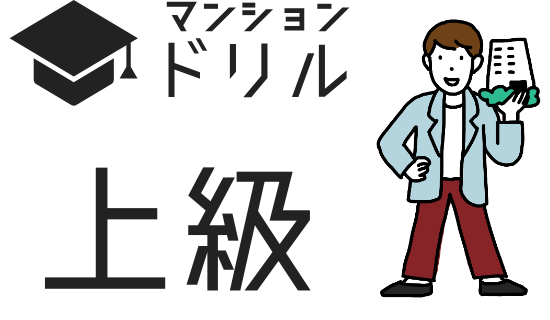
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。