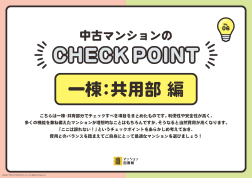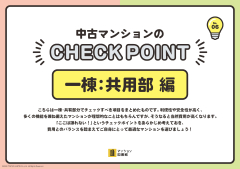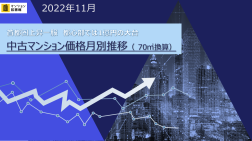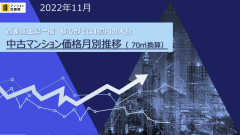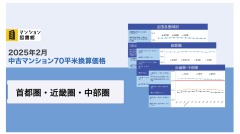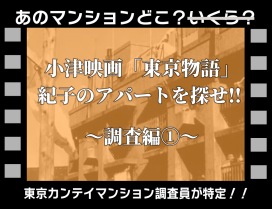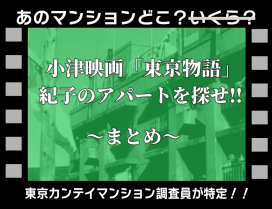全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2024.09.12
登録日:2023.07.20
液状化現象とは?発生する仕組みと判定方法をくわしく解説

住宅を新しく建てる方にとって、土地の地盤が安全かどうかは気になるものです。地盤が緩いと、地震により液状化現象が引き起こされ、生活に大きな支障が出ます。
そこで、本記事では、液状化現象が発生する仕組みや液状化リスクの判定方法を解説します。今後、居住予定の地域の液状化リスクを確認し、万が一の事態に備えましょう。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
液状化現象とは何か

液状化現象とは何か
液状化とは、地震による震動で地盤が揺さぶられ、地盤の一部が液体状に変わる現象のことです。液状化は、主に同じ大きさや同じ成分の砂でできた地盤が、地下水などの水分で満たされている場合に起こりやすいといわれています。
地盤が液状化すると、水の比重より重い建物が傾いたり沈んだりすることがあるため大変危険です。また、水の比重より軽いマンホールなどが浮き上がり、地面のなかにある下水管や水道管などがダメージを受ける場合もあります。
そのほか、地面の割れ目から水と土が地表に噴き出る噴砂(ふんさ)現象も見られるなど、液状化は地震発生時に起こる可能性のある被害です。
土地の購入を考えている場合は、どのような場所で液状化が起こりやすいか・購入予定の土地が液状化する可能性がないかを事前に調べておくとよいでしょう。
液状化が発生する仕組み

液状化が発生する仕組み
地盤の液状化は、地下水に浸かっているゆるい砂の地盤が地震による振動で一時的に強度を失うことで発生します。
通常時、ゆるい砂の地盤は粒子が結合しあい、隙間に水が含まれている状態です。しかし、地震が起こると粒子の結びつきがバラバラになり、砂が地下水に浮いたような状態になります。
砂は粒の大きさが揃っており、地震による地下水の圧力の高まりによってかみ合わせが外れやすいため、砂質土は液状化リスクが高いとされているのです。
一方、粘土層や砂と小石を含む地層などの硬い地盤、地下水位が低いところなどでは液状化が起こりにくいとされています。
住宅のなかで木造住宅は液状化による影響をとくに受けやすい点にも注意が必要です。木造住宅は建物重量が軽いことや、基礎が浅いことなどから液状化の影響を受けやすいと言われています。
液状化による被害予想については、さまざまなハザードマップが公開されているため、住宅を建てる際はぜひ参考にしてください。
鑑定士コメント
過去の事例では、一度液状化が発生した場所では、再度液状化が発生しやすくなります。液状化によって地盤の中の水が噴き出しても、地盤が十分に固まることはなく、かえって緩んだとの計測報告もあります。また、本震で液状化した場所が、余震によって再液状化したケースもありますので、過去の履歴の調査も必要でしょう。
液状化しやすい地盤の特徴

液状化しやすい地盤の特徴
液状化しやすい地盤の特徴には、砂質の土が地下水に浸かっていてゆるい状態であることが挙げられます。
具体的には以下の数値(※)を満たす場合、液状化しやすいと考えられています。
・地盤の強度を表す「N値」が20以下
・地表面からの深さが15m〜20mより浅い
・砂の粒の大きさが均一かつ、大きさが0.25mm〜0.5mm程度
N値とは、土の締まり具合や強度を表し、標準貫入試験によって求められる値です。
以上の特徴を満たした地盤において、震度5以上(※)の揺れが起こると、液状化が発生する可能性は高くなります。
なお、液状化の起こりやすい土地は、大きく分けて以下の7種類です。
2011年の東日本大震災では、千葉県浦安市をはじめとする過去50~60年以内に作られた埋立地で、重大な液状化の被害が起きました。
埋め立てから長期間が経過した土地や、過去に液状化した土地でも再び液状化が発生するリスクがあるため注意が必要です。
※参照:神奈川県ホームページ
液状化が起こりやすい土地の判定方法

液状化が起こりやすい土地の判定方法
液状化現象の被害を避けるために、液状化が起こりにくい土地に住むことが重要です。
今後、住宅を建てる方は、土地の判定方法を知って液状化リスクの少ない土地を選んでください。土地の判定方法は、次の3つです。
・土地条件図を見る
・ハザードマップを活用する
・ボーリング調査で調べる
土地条件図(国土地理院)を見る
簡易的な手法であるため、専門的な知識がなくても問題ありません。
国土地理院が公表している土地条件図を活用することで、液状化リスクを把握できます。土地条件図に記載されている数値データから、地域ごとの液状化の発生傾向を調べましょう。
液状化だけでなく、洪水や地震などの災害リスクも確認できるため、住む地域を検討している方は一度利用してみてください。
ハザードマップを活用する
国土交通省が提供する、ハザードマップを活用することで液状化が発生しやすい地域を確認できます。
はじめに、国土交通省のハザードマップポータルサイトにアクセスします。「重ねるハザードマップ」に住所を入力し、「すべての情報から選択」をクリックしてください。
「土地の特徴・成り立ち」の項目から「地域区分に基づく液状化の発生傾向図」を選択しましょう。その後、地域ごとに液状化の発生傾向の強弱が5段階で表示されます。
ハザードマップは液状化リスクだけでなく、洪水による水害リスクや避難情報を確認できます。
以下の記事で、洪水ハザードマップの見方や入手方法などを解説しています。居住予定の地域の災害リスクを把握して、万が一の災害に備えてください。
ボーリング調査で調べる

ボーリング調査で調べる
ボーリング調査による土地の調査も、液状化しやすい土地を見分けるうえで役立ちます。ボーリング調査では、地面に穴を掘ることで地盤の強度や地質などを調べられるためです。
具体的には、地面に円筒形状の孔をあけるため50回の打撃を加え、貫入した深さに応じて「N値」を算出し地盤の強度を測ります。また、貫入の過程で採取した土の分析により、地盤の特性や性質を把握することも可能です。
このボーリング調査によって、液状化しやすい土地かどうかを判別しやすくなります。
鑑定士コメント
本文に前述した通り、液状化は地盤が緩く、地下水位が浅い場所で発生しやすいと言われてます。一方で、地下水位が深い場所や地盤が硬い場所、粘性土地盤や砂礫地盤では発生の可能性は低いです。元々、河川や泥だった場所や、干拓や盛土など人工地盤の場所では液状化が起こりやすいため、過去地図などで地歴を確認し、注意しましょう。
液状化の影響

液状化の影響
液状化現象が、生活に及ぼす影響はさまざまです。液状化によって起こる被害は、主に4つに分類されます。
・噴水や噴砂
・建物への被害
・道路への被害
・ライフライン施設への被害
噴水・噴砂が発生する
まず被害として考えられるのは、液状化による噴水や噴砂です。
液状化によって堆積した水や砂から抜け出すのは難しく、自転車が埋没し、緊急避難が遅れる可能性があります。大規模な液状化が起こると、噴水が数時間も続き、住宅の浸水や田畑の冠水へとつながります。
噴砂によって、宅地や道路内に土砂が堆積すると、生活や通行の妨げになるでしょう。また、噴砂が乾くと粉塵として舞い上がり、健康被害を引き起こします。
建物への被害が起こる
液状化によって地盤が不安定になると、建物の沈下や傾斜が起こる恐れがあります。建物の基礎部分に亀裂が発生することも珍しくありません。
最悪の場合、建物自体が転倒する可能性もあります。
過去には新潟地震による液状化が発生し、建物への直接的な損傷は見られないまま、RC造のアパートが足元から転倒した事例もありました。
他にも、ドアや窓の開け閉めの不具合や隙間風の発生など住宅の機能障害を引き起こします。
道路への被害が起こる

道路への被害が起こる
液状化によって道路が損傷し、転倒や事故を引き起こします。道路の損傷は、緊急避難や救急活動の妨げになるため、被害がさらに拡大する恐れがあるでしょう。
道路に噴砂が堆積したり、マンホールや水道管などの地中構造物が浮き上がったりして、交通障害にもつながります。
液状化が広範囲に及び、河川側に地盤全体が大きく横に移動(側方流動)し、過去には橋が落ちる事例がありました。
ライフライン施設への被害がおこる
液状化は、電気・水道・ガスなどのライフラインにも大きな被害を与えます。
液状化によって水道管が破損すると、飲料水・洗濯水・風呂の水・トイレの水など、生活に必要不可欠な水の供給が停止します。
また、液状化の程度によっては水の供給にかぎらず、電気やガスの供給が停止する可能性もあるのです。
水道管やガス管の破損は、液状化していない地域にも被害を与えます。ライフライン施設の復旧までに時間がかかるため、長期間日常生活に支障が出るのも深刻な問題です。
上記の通り、液状化によってさまざまな被害を受ける可能性があるため、液状化現象への対策が重要です。以下の記事から液状化現象の対策方法を知って、万が一の事態に備えてください。
以下の記事では、液状化への対策方法を解説しています。新しく家を建てる場合にできる対策を知り、万が一の事態に備えてください。
まとめ:液状化の仕組みを理解して発生しやすい土地の特徴を把握しておこう

まとめ:液状化の仕組みを理解して発生しやすい土地の特徴を把握しておこう
液状化は、地盤が緩く、地下水位が浅い地域で起こりやすい現象です。
液状化現象は、建物への直接的な被害だけでなく道路や水道管の破損によるライフライン設備への被害など、さまざまな影響があります。
土地条件図やハザードマップを活用して、居住地域の液状化のリスクを把握し、万が一事態の備えをしておきましょう。
#液状化現象 #地盤 #地震 #建物

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
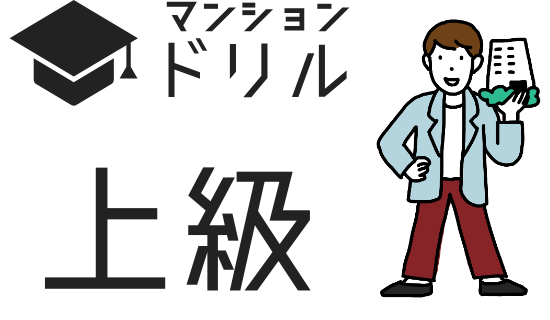
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。