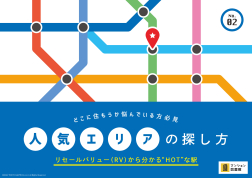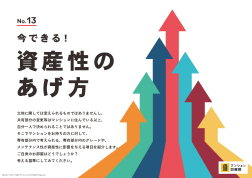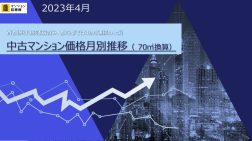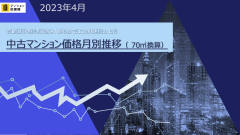全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.06.25
登録日:2023.06.02
第一種住居地域とは?建築制限や特徴についてわかりやすく解説

「第一種住居地域ってどういう地域なの?」
「第一種住居地域に建てられる建物の条件は?」
本記事では、13種類の用途地域の中から「第一種住居地域」について解説します。用途地域とは、その地域に建てられる建物の大きさや種類などが定められているものです。
用途地域によって街の景観や環境が異なるため、不動産の購入の基礎知識としてチェックしておきましょう。その他の用途地域との違いや第一種住居地域のメリット・デメリットもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
・第一種住居地域は住居周辺の環境を保護するために定められた用途地域の一つ
・建築できる建物には道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制が設けられている
・第一種住居地域は利便性が高い一方で場所によっては騒がしく感じることがある
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
第一種住居地域とは

第一種住居地域とは
第一種住居地域の基礎知識をまとめました。
・第一種住居地域の定義
・用途地域13種類の中での役割
・第一種住居地域の特徴
どのような地域なのか、詳細をチェックしましょう。
第一種住居地域の定義
第一種住居地域とは、住居周辺の環境を保護するために定められた用途地域の一種です。用途地域は都市計画法における地域地区で、それぞれ建築できる建物が指定されています。
その中で第一種住居地域は住居系に分類され、住居や店舗、教育施設などの建築が可能です。住みやすい環境を保護する目的があるため、一定以上の面積がある店舗や施設は建築できません。
用途地域13種類の中での役割
用途地域(※)には13種類あり、「住居系」「商業系」「工業系」に分けられています。それぞれの地域の違いは以下のとおりです。
※横にスクロールできます。
土地や不動産を購入する際は、重要事項説明書の中に用途地域に関する記載があります。役所やネットでも簡単に調べられるため、不動産を購入する際にはチェックしておきましょう。
※参照:国土交通省・都市計画法
第一種住居地域の特徴
第一種住居地域は住居を保護する目的の地域ですが、一定の基準を満たした店舗や事務所が建築できます。住居が6~7割、店舗や事務所は3~4割が目安とされ、混在しているのが特徴です。
比較的静かで落ち着いた住環境ですが、利便性も備えている用途地域といえます。住みやすさと利便性のバランスを重視する方に、おすすめです。
第一種住居地域で建てられる建築物とは

第一種住居地域で建てられる建築物とは
第一種住居地域は、「住居系」に分類される用途地域です。用途地域によって建築できる建物が異なります。
第一種住居地域で建てられる建築物、建てられない建築物について見ていきましょう。
建築できる建物
第一種住居地域で建築できる建物は以下のとおりです。
・一軒家やマンション、老人ホームや寄宿舎
・一定規模以下の店舗兼住宅、事務所兼住宅
・学校や図書館、病院などの公共施設
・宿泊施設やボーリング場、スケート場、プール(3000㎡以内)
・自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以下)
・工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない)
・ガソリンスタンド等(火薬類が非常に少ない施設)で床面積の合計が3000㎡以内
住みやすい環境を保護するための地域であり、住居がメインの地域となっていることがわかります。
鑑定士コメント
第一種住居地域に3階建ての住宅は建てられるのでしょうか?実際、第一種住居地域に3階建ては多く見られます。しかし、隣地側に面した建物の高さが20mまたは31mを超える部分について高さを制限することと定められているため、3階建ては建てられても、日影規制や隣地斜線制限などに配慮する必要があるケースもあります。土地の様々な条件によりますので、ハウスメーカーや建築士に確認するとよいでしょう。
建築できない建物
第一種住居地域で建築できない建物は以下のとおりです。
・床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店
・麻雀屋、パチンコ屋、カラオケボックス
・劇場や映画館
・ナイトクラブや風俗
他にも工場の種類や大きさによっては建築が制限されます。
建てられない建築物の種類を把握しておけば、どのような街並みなのか想像しやすいかもしれません。
第一種住居地域の建築制限

第一種住居地域の建築制限
用途地域にはそれぞれ建築制限が定められています。
建てられる建物や施設であっても、この建築制限を越えてしまうものは建築できません。
第一種住居地域の建築制限について見ていきましょう。
道路斜線制限
隣地斜線制限
隣地斜線制限とは、隣の建物との間に空間を確保し、通風や採光を妨げないために定められた制限です。(※)
この制限は、高さが20m、31mを超えた部分の制限となります。そのため、低層住居専用地域や田園住居地域のような高さが10m、12mに制限されているものついては適用されません。
日影規制
日影規制とは「冬至の日」を基準とし、定められた時間以上に日影が作られないように建物の高さを制限するものです。(※)
日影の部分は暗くなるため、周囲の日当たりを確保するのが目的です。
※参照:建築基準法
以下の資料では、マンションタイプごとに注目すべき要素を紹介します。マンションを購入する際に、用途地域とあわせてぜひ参考にしてください。
他の用途地域との違い

他の用途地域との違い
そもそも用途地域の中には「住居地域」と「住居専用地域」の2種類があります。主な違いは規制の厳しさで、詳細は以下のとおりです。
住居専用地域と比較すると、住居地域のほうが建てられる建物の種類は多くなります。また、第一種住居地域とその他の用途地域との違いを、以下でまとめました。
・第一種低層住居専用地域との違い
・第二種住居地域との違い
・近隣商業地域・商業地域との違い
・準住居地域との違い
建てられる建物と環境の違いを解説します。
第一種低層住居専用地域との違い
第一種低層住居専用地域とは、住宅系の中でも最も厳しい規制が設けられた用途地域のことです。厳しい高さ制限があり、低層住宅のために良好な住環境が保護されています。
一部の例外を除いて、店舗や事務所を建築することはできません。第一種住居地域よりも住環境を重視していて閑静ですが、利便性ではやや劣ります。
第二種住居地域との違い
第一種住居地域と第二種住居地域はどちらも住居地域ですが、建築できる建物は異なります。第一種住居地域には建てられない、カラオケやパチンコ屋などの遊戯施設が建てられるのが第二種住居地域です。
第一種住居地域に比べて、住居と店舗や事務所が入り混じっているため人の出入りが多く、賑やかです。主に幹線道路沿いや郊外駅前地域が指定地域になります。
第二種住居地域は利便性が高い一方で、第一種住居地域より騒音や防犯面が気になるかもしれません。第二種住居地域についてはこちらの記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
近隣商業地域・商業地域との違い
近隣商業地域・商業地域は「商業系」に分類される用途地域です。住居を中心とした住居系の第一種住居地域と違い、商業に特化しています。
近隣商業地域は近隣住民が日用品を購入するための地域で、駅周辺や商店街、幹線道路沿いが指定されるのが一般的です。商業地域はより商業に特化しており、大都市の中心部やターミナル駅周辺などが指定されます。
準住居地域との違い
準住居地域は、自動車関連施設周辺の立地とそれと調和する住居のための用途地域です。主に幹線道路沿いや国道が指定されます。
住居系では最も規制がゆるく、車庫や倉庫、一定の広さ以下の自動車修理工場を建築することが可能です。第一種住居地域と比較すると騒がしくなりますが、国道や県道沿いなので車での移動はしやすい傾向があります。
第一種住居地域のメリット

第一種住居地域のメリット
第一種住居地域のメリットは以下のとおりです。
・スーパーや事務所、店舗が建てられるため利便性がいい
・商業施設があるため比較的明るい
・通勤や通学に便利であることが多い
・利便性が高いため不動産の売却がしやすい
パチンコ屋などの遊戯施設がなく、スーパーや商業施設は建てられるため、住居に適した地域と言えるのがメリットです。日常生活の買い物がしやすく、利便性が高い地域といえます。
公共施設や駅にも近いので通勤通学にも便利です。事務所や店舗があるため街灯も多く、比較的明るい地域といえるでしょう。それなりに人の行き来があるため、防犯面でも安心できます。
また、利便性が高い土地なので、売却するときに地価が安定しやすいのも魅力です。不動産の売却がしやすく、高値で取引できる可能性があります。
第一種住居地域のデメリット

第一種住居地域のデメリット
第一種住居地域のデメリットは以下のとおりです。
・人通りが多くなるため騒がしい場合がある
・娯楽施設がない
・制限があまり厳しくない
用途地域としては、幅広い建築物が建てられる地域であるため、必然的に人通りの多い場所も出てきます。場所によっては騒音が気になるかもしれません。
同じ第一種住居地域のエリア内でも、周辺の環境によって住みやすさが大きく異なります。不動産を購入する場合には、あらかじめ周囲の環境を確認しておくことが重要です。
また、第一種住居地域は厳しい高さ制限がありません。店舗やホテルなど近隣に大型の施設ができた場合、日当たりが悪くなる可能性があります。
鑑定士コメント
第一種住居地域を選ぶ際に注意するべきことは何でしょうか。低層住居専用地域よりも、建蔽率や容積率は緩和されるので、同じ土地の面積でも、床面積の広い建物や3階建など高さを確保できます。しかし、裏を返せば隣接建物の影響で、日当たりが悪い場合も出てきます。人通りや騒音も気になることもあります。事前に現地に何度か足を運び、確認しておくのがよいです。
まとめ:第一種住居地域の住宅は購入前に必ず確認しにいこう

まとめ:第一種住居地域の住宅は購入前に必ず確認しにいこう
第一種住居地域は、住宅と商業施設が入り混じった地域です。病院や学校、スーパーなど生活に密接した施設があるため、人通りが多い時間帯や騒がしい時間帯、場所などが生じやすいとも言えます。
住宅を購入する際には、事前に何度か足を運んで住環境を確認しておくのがおすすめです。実際に住むことをイメージしてみると、理想の地域を探しやすいでしょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
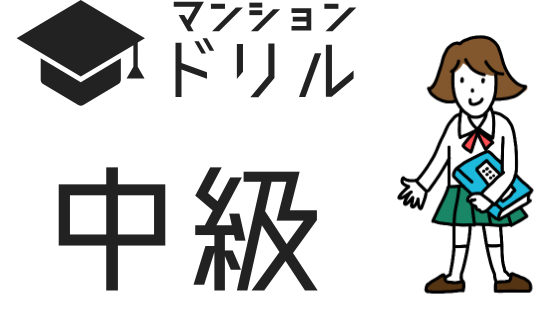
マンションドリル中級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。