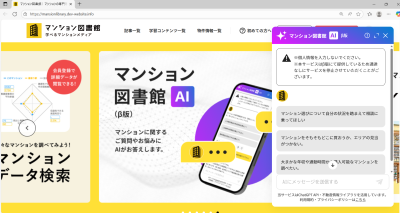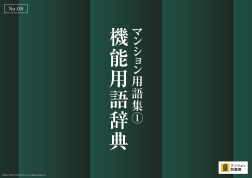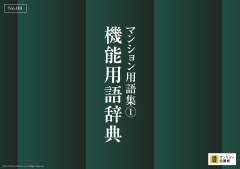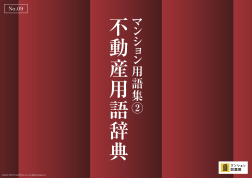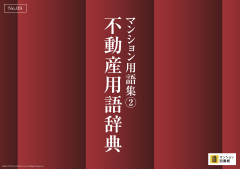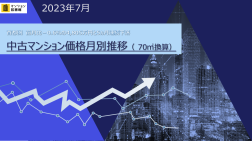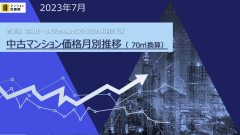全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.10.31
登録日:2023.04.20
【管理会社経験者が解説!】マンションの管理組合の理事会の役割は?役職と仕事内容をくわしく紹介

「マンション理事会と管理組合は何が違うのだろう」
「理事会の業務はどんな仕事なのだろう」
マンションの管理組合と理事会の違いや役割を知らない方も多いのではないでしょうか?
管理組合はマンション購入者全員が入るもので、その中から選出された人物たちで理事会を構成し、実際のマンション管理業務を行っています。
今回は、マンションの管理組合の理事会の役割などについて、マンション管理や売買仲介の最前線で活躍してきた、東京カンテイのマンション専門調査員・今村浩一による経験も交えて詳しく解説します。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
-

【監修者】マンション専門調査員 今村 浩一
マンション管理会社にて管理組合の運営支援業務、その後、大手不動産仲介会社にて売買仲介営業に従事し、2016年に東京カンテイに入社後現在に至る。 マンション専門調査員として東京都心部を中心に、埼玉県全域、 名古屋市、宇都宮市、高崎市、福岡市、広島市など、約9年間で延べ12,000棟以上のマンションについて現地/データの二面から調査を行う。 趣味はマンション関連のネットサーフィン、モデルルーム巡り、マンション将来価格予想。夢は歴代住んだマンションの模型を部屋に並べてお酒を飲むこと。
マンション管理組合での役割|理事会メンバー以外にも役割はある?

マンション管理組合での役割|理事会メンバー以外にも役割はある?
管理組合の中で実働しているのは理事会メンバーだけではなく、組合員も総会の決定に対して議決権を行使したり、管理費や修繕積立金を負担したりして役目を果たしています。
ここでは組合員と理事会役員の具体的な役割について解説します。
組合員
組合員には日常的な業務はありませんが、理事会の提案事項に対して意見表明することで、組合運営に直接的に参加し、理事会機能に間接的に関わります。また、管理費や修繕積立金を負担するなどの役目をはたしています。
理事会の決定に賛否を表す場面は「定期総会」と「臨時総会」の2つです。
定期総会は年に1回必ず開催され、決算の報告や予算の審議、理事会役員の選出や解任について話し合うために開かれます。
臨時総会は、管理組合員全員に影響を及ぼすであろう重要事項を決める時に開催するもので、管理規約の改定や廃止、共用部分の変更など、定期総会前に審議する必要がある場合に開かれます。
日々のマンション管理や総会の開催については理事会が主体となっていますが、マンションをより良くするには組合員ひとり一人の協力が欠かせません。
理事会役員
理事会役員の役割は総会の運営やマンション内の清掃管理、修繕計画の立案や費用の運用、マナーやルールの周知など、多岐にわたります。
これら日常業務の報告や課題解決のために、定期総会や臨時総会を開催し、様々な審議を進めていくことも役割です。
定期総会は1年に1回必ず開催する必要があり、予算や理事会役員の選出などを話し合い、臨時総会は共用部分の変更など、特別に時間を設けて決める必要がある際に開催されます。
マンション管理組合の理事会経験は住民にとってプラスに働く

マンション管理組合の理事会経験は住民にとってプラスに働く
東京カンテイの今村によると、理事会役員を経験する最大のメリットは、自身のマンションを「資産」として捉え、その価値を維持・向上させるための知識と視点が得られることであるとのことでした。
マンションは「住まい」であると同時に、所有者にとっての「資産」です。そのため、役員として運営に関わることで、これまで漠然と支払っていた管理費や修繕積立金が、具体的にどのように使われ、建物の維持に役立っているのかを深く理解できます。
例えば、以下のようなメリットがあります。
役員の仕事はハードルが高く感じることもあるかもしれませんが、自身の重要な資産を守り、より良い住環境を築くための貴重な機会と捉えることができるでしょう。
マンション理事会の役職と仕事

マンション理事会の役職と仕事
マンション理事会は以下の役職で構成されるのが一般的です。
・理事長
・副理事長
・理事
・監事
ここでは、それぞれの役職について具体的な仕事内容を紹介します。
理事長
理事会の代表者であり、総会の議長を務めます。管理組合の「顔」として、管理会社との日常的な連絡や調整が主な業務です。
例えば、騒音トラブルに対する注意文の配布を依頼したり、総会で決まった修繕工事の注文書に署名・捺印したりと、日々の運営における窓口としての役割を担います。
業務は多岐にわたりますが、特に総会で決まった事項の書類手続きが集中する総会の前後に多忙になる傾向があります。
このように管理組合の運営に不可欠な理事長ですが、法律上の位置づけはどうなっているのでしょうか。鑑定士の解説を紹介します。
鑑定士コメント
マンション管理組合の理事長は必ず選出しなければならないのか、という点については、区分所有法第25条に「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。」と規定されています。法律上は必ずしも管理者の選出が強制されているわけではありません。しかしながら、現実的に管理者不在で管理業務をおこなっていくことは困難なため、ほとんどのマンションでは管理規約で「管理者に理事長を選任する」ことが規定されているのが一般的です。管理組合はあくまでも区分所有者全員で組織した団体の名前であり、管理組合自身では契約書を締結する、総会議事録を作成するなどの「行為」ができません。こういった管理組合の運営に必要な「行為」をする方(管理者)が管理組合の代表者として必要であるからです。
副理事長
副理事長は、理事長を補佐する役割です。理事長が入院や転居などで長期にわたり不在、或いは売却などにより区分所有者でなくなった場合に、その代理を務めます。平常時は、理事長がいる限り業務内容は他の理事とほとんど変わらず、理事会の一員として活動します。
-いわば、万が一の事態に備えるための重要なポジションと言えるでしょう。ー今村談
理事
理事は、理事長・副理事長と協力し、マンション管理の実務を担当します。マンションの規模によっては、会計・防災・広報といった専門的な担当が置かれることもありますが、これらの役職が設定されていないマンションも少なくありません。
管理規約で役職が定められている場合、原則として兼務はせず、それぞれの役に1人ずつ就任します。しかし、役員の成り手不足が発生している場合などは、総会で規約を改正し、理事の定数を減らすといった見直しが行われることもあります。
会計
会計は、管理費や修繕積立金の収支管理を担当します。ただし、日々の会計処理や収支報告書の作成は管理会社が行うことがほとんどです。そのため、会計担当理事の主な役割は、管理会社から提出される収支報告書の内容の確認や、町内会費の集金などが挙げられます。専門的な簿記の知識は必ずしも必要ありません。
防災
防災は、地震や水害といった災害に備えるための役割を担います。具体的には、防災訓練の計画・実施や、災害対策マニュアルの整備、防災備蓄品の管理などが主な業務です。マンションによっては、防災担当理事が「防火管理者」を兼務することもありますが、これらは法律上の責務や役割が異なります。
防災担当理事と防火管理者の違い
マンションの安全管理には、「防災担当理事」「防火管理者」「防災管理者」という似た名称の役割が存在しますが、それぞれ根拠となる法律や責務が異なります。
広報
広報は、住民へのお知らせ(掲示物など)の作成や管理を行います。ただし、専門の担当が置かれることは比較的少なく、注意喚起の文章作成なども含め、理事長や他の役員が業務を兼ねることが多いのが実情です。文章作成は管理会社がサポートしてくれることも多いです。
書記
書記は、理事会や総会の議事録を作成します。この業務も、実際には管理会社の担当者が代行してくれるケースがほとんどです。
渉外
渉外は、自治会や町内会との連携や交渉を担当します。この役割も専門の担当が置かれることは少なく、理事長や他の役員が代表して対応することが一般的です。
監事
監事は、理事会の業務執行や会計状況が適切に行われているかを、理事会から独立した客観的な立場で監査する役職です。総会で決まった年間の活動計画がきちんと実施されているか、工事は計画通りに進んでいるかなどをチェックします。
特に会計については、理事会がチェックした収支報告書を最終的に監査する重要な役割を担います。専門知識がなくても、管理会社に不明点を確認しながら務めることが可能です。
マンション理事会役員の選び方

マンション理事会役員の選び方
役員の任期や交代のルールは、管理規約に「任期1年」や「任期2年」といった形で定められており、それに準じて選出が行われます。
選出のプロセスは、まず旧理事会が総会前に次期役員の候補者を推薦し、その候補者を総会で承認を得るのが一般的です。候補者の選び方は、実態として立候補者はあまり現れないことが多く、輪番制(持ち回り)による採用が一般的です。
総会で役員(理事・監事)が承認された後、新役員による初回の理事会で、話し合いによって理事長などの役職を決定します。その際、話し合いでなかなか決まらない場合は、最終的にくじ引きなどで決めるケースもあります。
もし役員に選ばれてしまった場合、断ることはできるのでしょうか。鑑定士の見解は次のとおりです。
鑑定士コメント
理事会の役員に選ばれても断れるのか、という点については、そのマンション個別の事情が強く、一概には言えません。いろいろな実例のケースを聞くと、役員の辞退にペナルティを課すことは住民同士の軋轢を生む恐れもあり、あまり好ましいことではないと思います。ペナルティを課すのではなく、理事会役員の担い手を増やすために就任基準を緩和するのも一つの方法です。
マンション理事会の仕事

マンション理事会の仕事
理事会役員の主な仕事は、以下の3つに大別されます。
・理事会への参加
・マンションの管理業務
・総会の開催
それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
理事会への参加
理事会の開催ペースは、管理組合によって異なります。総会後と前に年に2〜3回程度の場合もあれば、毎月開催するケースもあります。土日の午前中などに1〜2時間程度の時間を確保する必要があります。近年はオンラインで理事会を開催するケースも増えています。
会議以外にも、理事長は管理会社からの報告や住民からの相談などで、週に1〜2回程度、電話やメールでの対応が発生することがあります。特に総会の前後や引き継ぎの時期は、書類の確認や準備で多忙になる傾向があります。
マンションの管理業務
建物の維持管理に関する業務が中心です。具体的には、共用部分の清掃状況の確認、設備の定期点検の立ち会い、修繕工事の計画・発注などが挙げられます。また、近年では住民専用のポータルサイトを導入し、共用施設の予約や各種申請をオンラインで行えるようにするなど、管理業務のデジタル化も進んでいます。
総会で工事の実施などが決まった場合、その後の実行は管理会社がサポートしてくれることも多いです。理事会が主体となって動くことが望ましいですが、特に管理会社が元請けの工事等は発注手続き等を主導してくれるため、過度に心配する必要はありません。ただし、組合直発注の工事等は主体となって管理していく必要があります。
総会の開催
年に1回の定期総会や、必要に応じて臨時総会を主催します。総会で話し合う議題(予算案、工事計画など)を準備し、当日の運営進行を務めます。
また、住民から「こうしてほしい」といった要望が出た場合は、まず理事会でその意見を集約・検討し、案をまとめます。そして、その案を総会に議案として提出し、全組合員の議決を仰ぐという流れになります。
マンション規模による理事会の仕事内容

マンション規模による理事会の仕事内容
マンションの運営方法は、その規模によっても異なります。理事会が直面する課題や仕事内容にどのような違いがあるのか、具体的に見ていきましょう。
マンションの規模による仕事内容の違い
マンションの規模は、理事会の運営スタイルに直接的な影響を与えます。
合意形成のしやすさ
小規模マンションは住民の数が少ないため、意見がまとまりやすく、合意形成がスムーズに進む傾向にあります。一方、大規模マンションは多様な意見を調整する難しさがあります。
役員の兼務に関するルール
住民数が少ない小規模マンションでは、「役員を兼務できないか」という疑問が挙がることがあります。しかし、管理規約で理事長・副理事長・理事といった「役職」が定められている場合、原則として一人が複数の役職を兼任することはできません。
もし役員のなり手が不足している場合は、規約を改正して理事の定数を減らすといった対応が必要になります。ただし、理事会の役員が、修繕委員会などの専門委員会の「委員」を兼任することは可能です。
委員会が設置される場合がある
大規模マンションでは、理事会が日々のトラブル対応や事務処理に追われ、すべての課題に対応するのが難しい場合があります。そこで、理事会の負担を軽減し、より専門的な検討を行うために「専門委員会」が設置されることがあります。特に小規模マンションや、理事会内で対応が可能だと判断される場合は設置されないこともあります。
最も代表的なのが「修繕委員会」です。大規模修繕工事は、スケジュール管理、多額の費用の取り扱い、工事に関する専門知識など、理事会だけでは対応が困難な要素が多くあります。修繕委員会は、こうした専門的な課題に集中して取り組むために、理事会の諮問機関として設置されます。
-メンバーは、ゼネコンや建設関係の経験を持つ住民がなることもありますが、専門知識は必須ではありません。複数の業者から見積もりを取る際の連絡係になるなど、リソースとして協力するだけでも理事会の大きな助けとなります。ー今村談
規模に関わらず「うまく機能する理事会」とは
運営のしやすさだけで見れば小規模マンションに分がありますが、大規模だからといって運営が滞るわけではありません。規模にかかわらず円滑に機能している理事会には「主体性」という共通点があります。
ー管理会社に任せきりにせず、住民自身が積極的に動き、管理会社の意見にも耳を傾け、様々な関係者とのバランスを取りながら運営を進めています。強いリーダーシップは運営において欠かせませんが、一方的な進め方になってしまうと、住民の声が置き去りにされ、不満が生じることもあります。
円滑な運営のためには、周囲との対話や協力も大切です。成功する理事会は、リーダーシップと住民一人ひとりの声に耳を傾ける姿勢のバランスが取れています。ー今村談
マンションの築年数による理事会の仕事内容の違い

マンションの築年数による理事会の仕事内容の違い
築年数も理事会の仕事内容に大きく影響します。
築古マンション
築年数が経過すると、経年劣化による修繕案件が増加します。特に築30年を超えたあたりから、目に見えない給排水管の漏水といったトラブルへの対応が重要な課題となります。
給排水管の更新工事は長期修繕計画に含まれていますが、計画された時期より前に個別のトラブルが発生した場合は、その都度対応が必要になります。こうした状況を踏まえ、長期修繕計画自体の見直しや、積立金の改定などをより慎重に検討することが求められます。
築浅マンション
築浅のうちは目立ったトラブルも少なく、物事がスムーズに決まる傾向にあり、理事会の運営は比較的穏やかです。しかし、その分「将来の老朽化にどう備えるか」という課題も伴います。
ー将来の老朽化のスピードを少しでも遅らせるために、この時期にやるべきなのが「土台作り」です。住民間の利用ルールを明確に定め、共有施設を大切に使う「空気感」を醸成するなど、マンションの将来価値を維持するための基礎を築くことが、築浅マンションの理事会に課せられた大きな役割と言えるでしょう。ー今村談
まとめ:マンションの理事会役員になったら積極的に業務に関わろう

まとめ:マンションの理事会役員になったら積極的に業務に関わろう
マンションの理事会役員は、業務内容が多く、仕事や生活と並行しておこなうことに負担を感じる人も多いかもしれません。
理事会役員になることは負担だけでなく、管理費の運用が把握できたり、マンションの現状が見えたりするメリットがあります。
マンションの住民とともに取り組むため、普段交流することがない人ともつながりが持て、横の関係も広がります。
自分の資産であるマンションをより良いものとするために、マンションの理事会役員になった際には、ぜひ積極的に業務に関わってみましょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

マンション専門調査員
今村 浩一
マンション管理会社にて管理組合の運営支援業務、その後、大手不動産仲介会社にて売買仲介営業に従事し、2016年に東京カンテイに入社後現在に至る。
マンション専門調査員として東京都心部を中心に、埼玉県全域、 名古屋市、札幌市、福岡市、広島市、宇都宮市、高崎市など、延べ15,000棟以上のマンションについて現地/データの二面から調査を行う。
趣味はマンション関連のネットサーフィン、モデルルーム巡り、マンション将来価格予想。夢は歴代住んだマンションの模型を部屋に並べてお酒を飲むこと。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
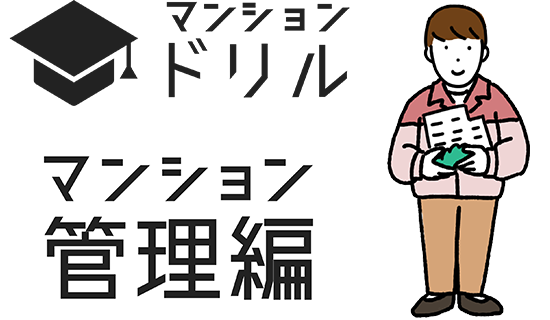
マンションドリルマンション管理編
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。