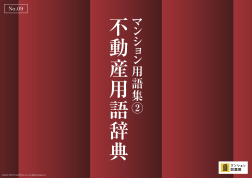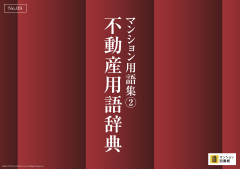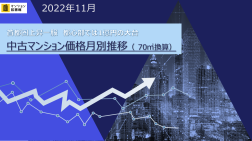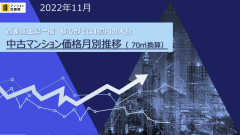全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2023.09.21
登録日:2023.09.21
第三者管理方式とは?3つの管理方式とメリット・デメリットを解説

「第三者管理方式」について、詳しく知りたい人も多いのではないでしょうか。
第三者管理方式は、マンションの管理業務の負担を軽減できるものの、いくつかの懸念点が存在します。
マンションの規模や実情によっても、適切な管理方式は異なるのです。そこで、本記事では第三者管理方式の種類やメリット、デメリットについて解説しています。
この記事を参考に、住んでいるマンションに合う管理方式を見つけてください。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
第三者管理方式とは

第三者管理方式とは
第三者管理方式とは、管理組合の運営業務を外部の専門家である第三者に委託する管理方式のことです。
通常、管理組合はマンションの購入者(区分所有者)から構成され、その中から役員を選出します。役員が管理業務を行い、適切にマンション管理できるようにつとめます。
しかし、近年はマンションの老朽化や住民の高齢化により、役員のなり手が不足しがちです。役員のなり手が少ないと、マンションの管理組合が機能せず、住民同士のトラブルに発展しやすくなります。
第三者管理方式を取り入れ、外部の専門家の力を借りることで、適切な管理体制を整えられます。
委託先は、マンションの管理会社だけではありません。個人のマンション管理士や弁護士、建築士などに依頼する場合もあります。
第三者管理方式を選択するマンションが増えている理由

第三者管理方式を選択するマンションが増えている理由
第三者管理方式を活用するマンションが増加している理由は、次の4つです。
・区分所有者や居住者の高齢化
・マンションの老朽化
・標準管理規約の改正
・理事会活動が面倒と避ける住民の増加
一方で、第三者管理方式を採用せず、自主管理を行うマンションもあります。自主管理のメリットやデメリットについては、以下の記事から確認してみてください。
区分所有者や居住者の高齢化
近年は、区分所有者や居住者の高齢化が問題視されています。
高齢者は、マンションの管理に対して関心が薄い傾向にあり、管理業務に関わることに消極的です。役員の就任を依頼しても、断られる場合があるのです。
高齢者の多いマンションでは、役員のなり手が不足しやすいため、第三者管理方式を採用していることがあります。
マンションの老朽化
築年数の経過とともにマンションの老朽化が進んでいることも、第三者管理方式が採用されている理由の一つです。
老朽化したマンションは、資産価値が低下しており、入居希望者が少ない傾向にあります。空室が多く、役員になる候補者が少ないため、管理組合の機能不全へとつながるでしょう。
入居者が少ないということは、区分所有者だけで管理組合を運営することが難しくなるため、第三者によるマンション管理を行なっています。
標準管理規約の改正

標準管理規約の改正
そもそも、第三者管理方式が注目されはじめたきっかけは、マンション標準管理規約の改正です。
マンション標準管理規約とは、国土交通省が作成したもので、マンション管理における基本的な事項を定めた規約のことを指します。
2011年以前は、マンション標準管理規約には「理事および監事は、マンションに居住する組合員から選出する」と記載されていました。
2011年の改正で、「マンションに居住する組合員から選出する」部分は消去(※1)され、マンションに居住していなくても理事や監事に就任できます。
2016年の改正では、第三者管理方式に関する規約が定められました。(※2)
標準管理規約の改正をきっかけに、第三者管理方式を採用するマンションが増えはじめたのです。
ちなみに管理規約は、マンションに住むうえで重要な用語です。以下の記事で、マンションの管理規約についても確認してみてください。
理事会活動が面倒と避ける住民の増加
役員の業務は決して楽ではなく、休日や夜間などの空き時間が減ってしまうため、負担に感じる人も少なくありません。そのため、お金を払ってでも、理事会活動を専門家に依頼したいと考える住民が増加しているのです。
理事会の役員は、月に1回程度の理事会に出席し、マンション内の問題について話し合います。役職によっては、収支予算案や大規模修繕計画の作成、管理費や駐車場の使用料などの保管や運用などを担当します。
理事会活動は通常ボランティア活動であるのに加え、マンション管理に興味がない層も増加していることもあり、ますます理事会活動をさける住民は多くなるでしょう。
第三者管理方式の種類

第三者管理方式の種類
第三者管理方式には、次の3つの種類が存在します。
・理事長または理事・監事外部専門家型
・外部管理者理事会監督型
・外部管理者総会監督型
マンションの事情にあわせて、適切な管理方式を採用しましょう。
理事長または理事・監事外部専門家型
理事長または理事・監事外部専門家型は、外部の専門家が理事会の一員となり、マンションの管理運営をサポートする形式のことです。
現在、区分所有者が主体となって管理組合を運営していますが、客観的な視点が必要と感じる場合に取り入れられます。
管理会社の選定や長期修繕計画の作成など、重要な議題について話し合う際に役立つでしょう。
ただし、この形式を採用しても、役員の負担がそれほど減るわけではありません。区分所有者の負担を減らすためには、他の形式も検討しましょう。
まだ管理組合の役員になった経験がない人は、以下の記事から理事会の役割について確認しておいてください。
外部管理者理事会監督型
外部管理者理事会監督型は、理事会とは別で、外部の専門家を管理者に置く形式のことです。
理事会は監事のような立場となり、管理業務の執行状況を監視します。
さらに、別の外部の専門家を選任し、理事会の一員として監査業務を委託する方法もあります。
外部管理者総会監督型

外部管理者総会監督型
外部の専門家を管理者に置き、理事会そのものを無くす形式が、外部管理者理事会監督型です。
理事会の廃止によって、区分所有者の業務がなくなり、負担が軽減されるでしょう。
マンションの管理の大半を外部へ委託するため、適切に管理組合が機能しているかチェックできる体制を整えることが重要です。
区分所有者から監事を選出するか、外部の専門家に監査を依頼するなどしましょう。
鑑定士コメント
どのようなマンションが第三者管理方式の対象となるのでしょうか?高齢者が多い、空室率が高いなどの理由から役員のなり手が少ないマンションが、第三者管理方式を採用する場合が多いです。そもそも居住する区分所有者がいない、投資型のワンルームマンションやリゾートマンションも第三者管理方式の対象となりやすいでしょう。
第三者管理方式のメリット

第三者管理方式のメリット
第三者管理方式のメリットとして、次の3つが挙げられます。
・管理組合の負担が軽減できる
・管理内容の適正化が進む
・レベルの高い運営が期待できる
一つずつ解説します。
管理組合の負担が軽減できる
メリットの一つ目は、区分所有者の業務の負担を減らせることです。
普段、家事や仕事で忙しい人にとっては、役員の業務が負担になります。また、役員に就任したことによる責任感で、心理的な負担も少なくありません。
第三者管理方式によって、業務を委託することで、区分所有者のストレスが軽減されるでしょう。
管理内容の適正化が進む
マンション管理に精通した専門家が、理事会のメンバーとして参加することで、管理内容が適正化されやすくなります。
例えば、マンションの維持管理に欠かせないのが大規模修繕工事です。
素人同士で話し合うよりも、専門家がいる方が適切な予算設定や計画の立案ができるでしょう。トラブルに発展しやすい問題を事前に解決できる可能性もあります。
レベルの高い運営が期待できる

レベルの高い運営が期待できる
専門家による知見が生かされるため、管理体制が整い、マンションを適切に運営管理できるでしょう。
たとえトラブルに発展したとしても、適切な対処を取ることで、問題の拡大を抑えられます。管理状態の良し悪しは、マンション全体の資産価値にも影響します。
第三者管理方式を活用して、スムーズなマンション運営を実現させましょう。
第三者管理方式のデメリット

第三者管理方式のデメリット
第三者管理方式には、一定のリスクがあります。
・理事会が機能しなくなる可能性がある
・役員のなり手が不足しやすい
・利益相反行為のリスクがある
適切にマンション管理ができるように、デメリットを把握しておきましょう。
理事会が機能しなくなる可能性がある
「専門家に任せておけば大丈夫」という安心感から、区分所有者の管理に対する関心が薄くなり、理事会が機能しなくなる可能性があります。
たとえ、業務を専門家に依頼した場合でも、区分所有者は外部の専門家の業務が適切に行われているかを監視することが大切です。
専門家のアドバイスはあくまでも参考程度にして、理事会が主体となって判断することが望ましいでしょう。
役員のなり手が不足しやすい
管理業務の大半を委託している場合は、区分所有者が役員の必要性を感じにくくなります。結果として、役員の就任を断られ、役員のなり手が不足しやすいでしょう。
区分所有者が主体となって管理業務を担っていれば、役員の必要性が伝わり、役員に立候補する人がいるかもしれません。
利益相反行為のリスクがある

利益相反行為のリスクがある
委託された外部業者が自身の利益を優先する、利益相反行為のリスクがあります。
利益相反行為とは、一方が利益を得て、他方が不利益を被る行為のことです。通常、委託された専門家や管理会社は、区分所有者側の利益に配慮した運営を行います。しかし委託された業者が、自身の利益を優先した工事の発注を行う可能性があるため、注意してください。
例えば、バックマージンを受け取って特定の会社に発注する場合、不要な工事を発注する場合があります。区分所有者の利益が損なわれないように、第三者管理方式を採用する際には、監視体制を整えることが大切です。
第三者管理方式を採用する場合の注意点

第三者管理方式を採用する場合の注意点
第三者管理方式を採用しても、外部の専門家に依存しすぎず、各区分所有者が責任感をもつことが重要です。
前述の通り、第三者管理方式には、理事会の機能不全や利益相反行為のリスクがあります。
第三者管理方式を採用後も、区分所有者が管理に対する責任感を持ち続けられるように、ルールを設けてください。
・理事会や役員の役割
・外部管理者の監視体制
・外部管理者の選任方法
・外部管理者の解任方法や解任の要件 など
特に、委託する専門家や工事業者の選定は、区分所有者が支払う費用にも影響します。理事会で決議を取り、区分所有者が納得できるような管理体制になるように心がけましょう。
鑑定士コメント
第三者管理者に管理会社がなった場合、気をつけるところはあるでしょうか?まずは管理会社が自身の利益を優先しているようなことが無いか、チェックが必要です。工事の発注を自社に行なっているものについて、不要な工事ではないか、発注先は適切であるかを監視する仕組みや体制構築が必要です。追加費用はかかりますが、監査法人を外部の監査役に委託する方法もあります。
まとめ:第三者管理方式を理解して、もっとも合った管理方法を選択しよう

まとめ:第三者管理方式を理解して、もっとも合った管理方法を選択しよう
第三者管理方式を採用することで、区分所有者の負担が減り、適切なマンション管理が実現できます。
一方で、理事会の機能不全や外部管理者による利益相反行為など、一定のリスクがあります。
あくまでも、主体となるのは区分所有者であると意識をもち続けられるような、マンションの管理方法を模索してみてください。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
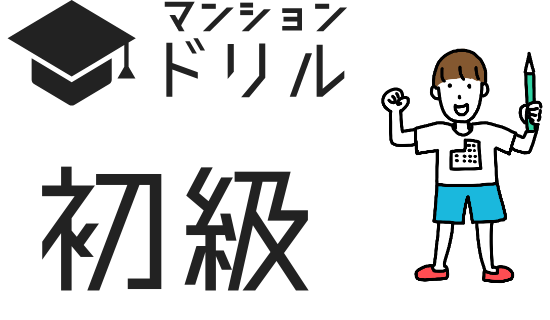
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。