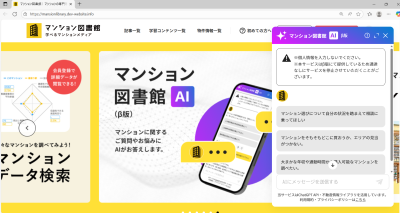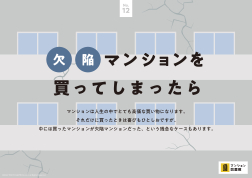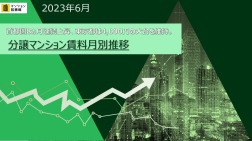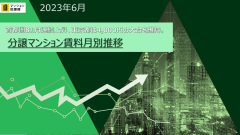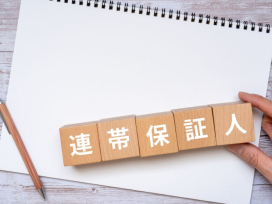全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.09.26
登録日:2025.09.26
知らないと損!固定資産税の軽減措置の条件・手続きを徹底解説

マイホームやマンションを所有すると、毎年かかってくるのが「固定資産税」です。決して安くはない金額に、不安や疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は固定資産税には、税額が軽くなる「軽減措置」が用意されています。ただし、制度によっては申請が必要で、知らずに放置していると本来より多くの税金を払ってしまうケースも少なくありません。
この記事では、固定資産税の基本から、住宅購入・新築・リフォームなどで活用できる軽減制度の種類と申請方法まで解説します。不要な出費を防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
・固定資産税とは毎年1月1日時点で土地や建物などを所有している人に課される地方税
・新築・リフォーム・土地取得などで活用できる軽減措置の種類
・軽減措置を受けるための手続き方法と必要書類
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
押さえておきたい固定資産税の基礎知識

押さえておきたい固定資産税の基礎知識
固定資産税の軽減措置を正しく活用するためには、まずその仕組みを理解しておくことが大切です。
ここでは、固定資産税とは何か、どのように計算されるのか、またあわせて課税される都市計画税について解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの「固定資産」を所有している方に課される地方税です。
固定資産は、以下の3つに分類されます。
納税義務者は、登記簿や課税台帳に所有者として登録されている方です。納税先は、その固定資産が所在する市区町村で、通常、年4回に分けて納付します。
納められた税金は道路・公園・学校の整備や、福祉・介護など地域住民の暮らしを支えるために使われます。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、「固定資産税評価額✕税率」で算出されます。
評価額とは、市町村が定める不動産の価値で、「固定資産評価基準」に基づき3年ごとに見直される仕組みです。
評価の方法は、土地と建物で異なります。
・土地:売買実例価格をもとに、地価や利用状況などを考慮して評価。
・建物・同じ構造・材料で建てた場合の費用(再建築価格)から、経年劣化分などを差し引いて算出。
なお、評価額を自分で正確に算出するのは難しいため、目安としては以下のように考えておくと良いでしょう。
・建物:購入価格の50〜70%程度
・土地:時価の70%程度
税率は自治体によって異なるものの、多くの市区町村では標準税率1.4%が採用されています。
都市計画税とは
都市計画税は、道路や公園などの都市のインフラ整備に使われる「目的税」で、固定資産税とあわせて毎年課税されます。
対象となるのは、都市計画法に基づき「市街化区域」として指定された地域内の土地や建物です。すべての地域に課税されるわけではなく、市街化区域以外ではかからないこともあります。
都市計画税の計算方法は、「課税標準額 × 税率(上限0.3%)」です。課税標準額は、固定資産税評価額をもとに決められます。
自分の住んでいる地域が市街化区域に該当するかどうかは、自治体のホームページや不動産会社に問い合わせれば確認可能です。
マンション購入後にかかる固定資産税の目安や計算方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。購入前にぜひ確認しておきましょう。
マンション購入後の固定資産税はどれくらい?計算方法もやさしく解説
なお、マンションに関わる不動産用語を知りたい方は、以下をダウンロードしてみてください。
覚えておきたい固定資産税の軽減措置

覚えておきたい固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置とは、住宅や土地にかかる固定資産税の一部を、一定期間にわたって減額できる制度です。上手く活用すれば、毎年の税負担を軽減でき、家計にもゆとりが生まれるでしょう。
ここでは、代表的な固定資産税の軽減措置を9つ紹介します。
・住宅用地特例
・新築戸建ての軽減措置
・新築マンションの減額措置
・認定長期優良住宅の減額措置
・タワーマンションの課税ルール変更
・耐震リフォームによる減額措置
・バリアフリーリフォームによる減額措置
・省エネリフォームによる減額措置
・長期優良住宅化リフォームによる減額措置
住宅用地特例
住宅用地特例とは、住宅が建っている土地にかかる固定資産税や都市計画税を軽減できる制度です。住宅として使用されている土地であれば、税負担を大きく抑えることができます。
面積に応じた軽減内容は以下のとおりです(※)。
※横にスクロールできます。
たとえば、評価額2,000万円・100㎡の土地の場合、固定資産税は以下のように軽減されます。
2,000万円✕1/6✕1.4%=約4.7万円
住宅用地の特例が適用されるかどうかは、自治体から届く納税通知書や、自治体への問い合わせで確認できます。
なお、建物を取り壊した場合や「特定空き家」に認定されると、特例は適用されなくなるため注意が必要です。
※ 参照:国土交通省
新築戸建ての軽減措置
新築住宅が一定の要件を満たす場合、建物にかかる固定資産税が最大3年間、2分の1軽減されます。
対象となるのは、以下の条件をすべて満たす住宅です。
・居住部分が住宅全体の2分の1以上であること
・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・令和8年3月31日までに新築されたこと
軽減される面積の上限は120㎡相当分までです。
たとえば、2,000万円の住宅なら、新築戸建ての特例(固定資産税1/2)と土地の住宅用地特例(課税標準1/6)を適用すると、年間の固定資産税は約9.1万円、3年間で合計約27.3万円の節税効果が期待できます。(※)
※ 参照:国土交通省
新築住宅を購入した場合は、住宅ローン控除も活用できます。初年度は確定申告が必要になるため、手続きの流れを知っておくと安心です。詳しくは、以下の記事をご確認ください。
住宅ローン控除の初年度に必要な手続きとは?確定申告の流れを解説
新築マンションの減額措置
新築マンションを購入した場合、一定の条件を満たせば、建物にかかる固定資産税が5年間、2分の1に軽減されます。(※)
主な適用条件は以下の通りです。
・専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・建物が3階建て以上かつ耐火構造であること
・令和8年3月31日までに新築されたこと
軽減の対象は建物部分に限られ、土地には適用されません。また、減額されるのは1戸あたり120㎡相当分までで、それを超える部分には通常の税率が適用されます。
※ 参照:国土交通省
認定長期優良住宅の減額措置
認定長期優良住宅を新築すると、通常の新築住宅よりも長く固定資産税が軽減されます。(※)
・2階建て以下の木造住宅:軽減期間は5年間
・3階建て以上の耐火構造住宅:軽減期間は7年間
たとえば、評価額2,000万円・税率1.4%の住宅なら、本来28万円かかる税額が半額の14万円に。5年間で約70万円(または7年間で約98万円)の軽減が見込めます。
※ 参照:国土交通省
長期優良住宅は建築コストが高くなりがちですが、こうした減税メリットを活用すれば、結果的にトータルコストを抑えることができます。
通常の新築住宅よりもお得になる可能性もあるため、検討する価値は十分にあるでしょう。
タワーマンションの課税ルール変更

タワーマンションの課税ルール変更
これまでタワーマンションでは、高層階の方が眺望や資産価値の高さから販売価格が高いにもかかわらず、固定資産税は低層階と同じでした。そのため「価格差があるのに税額が同じなのは不公平」という声が多く寄せられていたのです。
この不公平感を解消するため、2017年度の税制改正で課税ルールが見直され、2018年度以降に新築されたタワーマンションでは、階が高いほど税額が上がる仕組みが導入されました。
具体的には、「階層別専有床面積補正率」により、1階上がるごとに評価額が約0.25%ずつ加算されます。たとえば40階の住戸であれば、1階と比べて評価額が約10%高くなり、その分税額も増えます。
なお、このルールは2018年度以降に新築されたタワーマンションが対象で、それ以前に購入・契約された住戸には適用されません。
耐震リフォームによる減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に、現行の耐震基準を満たす耐震改修をおこなうと、翌年度の固定資産税が半額になります。(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2に軽減。)(※)
主な適用条件は以下の通りです。
・昭和57年1月1日以前からある家屋
・工事費が税込50万円を超えていること
・店舗併用住宅の場合、居住部分が全体の2分の1以上であること
・改修工事が令和8年3月31日までに完了していること
工事完了から3か月以内に、市区町村へ申告書や契約書の写し、耐震改修を証明する書類などを提出すれば、軽減措置を受けられます。
※ 参照:国土交通省
バリアフリーリフォームによる減額措置
高齢者や障がい者が住む住宅で、バリアフリー改修をおこなうと、翌年度の固定資産税が3分の1軽減されます(家屋100㎡相当まで・都市計画税は除く)。(※)
対象となるのは、新築から10年以上経過した持ち家で、補助金を除いた工事費が50万円を超えている住宅です。
また、居住者が以下のいずれかの要件に該当していることが条件となります。
・65歳以上の方
・障がい者の方
・要介護または要支援の認定を受けている方
対象となる工事は、以下の通りです。(いずれか1つ以上)
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの設置
・段差の解消など
なお、工事は令和8年3月31日までに完了している必要があります。
※ 参照:国土交通省
省エネリフォームによる減額措置
平成26年4月1日以前からある自宅に、省エネ改修工事をすると、翌年度の固定資産税が3分の1軽減される制度があります(都市計画税は対象外)。(※)
対象となるのは、窓や床・壁・天井の断熱工事や、太陽光発電設備の設置などです。また、減額を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・持ち家であること(賃貸は対象外)
・工事が令和8年3月31日までに完了していること
・改修後の床面積が50㎡〜280㎡以下であること
・工事費の自己負担額が一定額(50万円または60万円)を超えていること
・工事が令和8年3月31日までに完了していること
工事後3か月以内に市区町村へ申請することで、固定資産税を軽減できます。
※ 参照:国土交通省
長期優良住宅化リフォームによる減額措置
既存住宅に耐震または省エネリフォームをして「長期優良住宅の認定」を受けると、翌年度の固定資産税の3分の2が減額されます(120㎡相当までの部分が対象)。(※)
主な条件は以下のとおりです。
・改修後の床面積が50㎡〜280㎡以下であること
・耐震改修:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超えること。現行の耐震基準を満たす改修であること。
・省エネ改修:平成26年4月1日以前の住宅で、自己負担工事費が60万円を超えることなど。窓の断熱改修や高効率設備の設置などが対象。
・令和8年3月31日までに工事を完了し、入居していること
なお、長期優良住宅リフォームによる軽減措置を受ける場合、ほかの固定資産税減額制度とは受けられません。
※ 参照:国土交通省
鑑定士コメント
新築住宅の固定資産税には、建物部分の税額が3年間半額になる特例があります。しかし、これはあくまで一時的な軽減措置であり、4年目以降は本来の税額に戻ります。そのため、「急に高くなった」と感じる方も多いですが、実際には軽減が終了して本来の負担に戻っただけです。住宅を購入する際は、4年目以降の税額も見越したうえで資金計画を立てることが大切です。
固定資産税の軽減措置を受けるための手続き方法と必要書類

固定資産税の軽減措置を受けるための手続き方法と必要書類
固定資産税の軽減措置を受けるには、所定の申告手続きと必要書類の提出が必要です。手続きをしないと軽減措置を受けられず、想定以上の税負担が発生する可能性もあるため、注意しましょう。
・土地に関する軽減措置:住宅用地の特例
・建物に関する軽減措置:新築住宅の特例
・リフォームに関する軽減措置:リフォーム減税
これらの制度はそれぞれ手続き方法・提出先・必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅用地の特例
住宅用地の特例を受けるには、あらたに住宅用地として使用することとなった年の翌年1月31日までに市区町村の固定資産税担当窓口へ申告書を提出する必要があります。
ただし、すでに住宅用地として認定されている既存住宅については、あらためて申告する必要はありません。
新築住宅の特例
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置は、自動的に適用されることもありますが、住宅の構造や種類によっては申請が必要です。
※横にスクロールできます。
リフォーム減税
住宅のリフォームにより固定資産税の減額措置を受けるには、工事完了から3か月以内に各種申告書や証明書類を市区町村へ提出する必要があります。
リフォームの内容によって必要な書類が異なるため、以下の表を参考にしてください。
※横にスクロールできます。
-
鑑定士コメント
申請を忘れてしまうと、原則として軽減措置は受けられません。忘れてしまうと本来支払う必要のない固定資産税を負担することになりますので、注意が必要です。ただし、自治体によっては申告期限後でも事情を説明すれば認められるケースや、還付を受けられる可能性もあります。気づいた段階で、できるだけ早く市区町村の窓口に相談してみましょう。
まとめ:自分の物件に合った固定資産税の軽減措置を見つけよう

まとめ:自分の物件に合った固定資産税の軽減措置を見つけよう
固定資産税の軽減措置とは、一定の条件を満たす住宅や土地に対し、税負担を軽くするための制度です。主なものには、住宅用地の特例、新築住宅の特例、リフォーム減税があります。
住宅や土地を所有すると必ず固定資産税がかかりますが、軽減措置を活用すれば負担を抑えられます。ただし、多くの制度は自動適用ではなく申請が必要です。
今回紹介した内容を参考に、該当する制度を早めに確認し、期限内に忘れずに手続きしてください。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
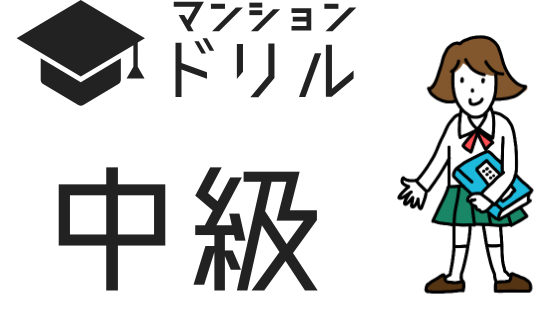
マンションドリル中級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。