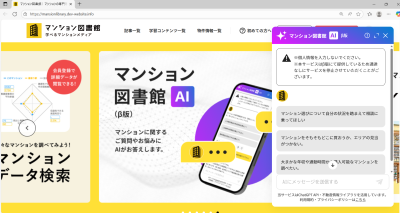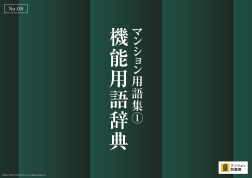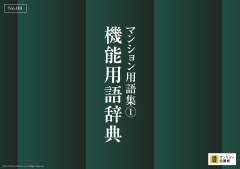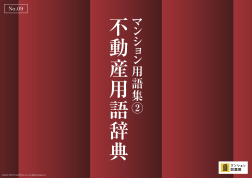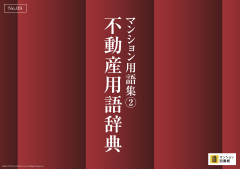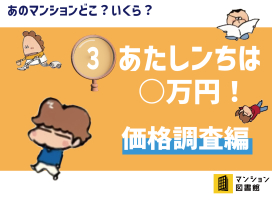全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.04.25
登録日:2025.04.25
マンションの火災報知器の基礎知識!共用部と専有部の違いや設置ルールを覚えよう

「マンションの火災報知器は必ず設置しなきゃいけないの?」
「マンションの場合、火災報知器は誰が設置するの?」
火災報知器について、このような疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では、マンションの火災報知器の役割や設置義務などを徹底解説します。火災報知器の種類や、警報音が鳴った時の対処法も具体的にわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
・火災報知器は初期消火や逃げ遅れ防止などに効果的
・マンションは部屋内である専有部とエントランスや非常階段などの共用部にわかれる
・⽕災警報器はすべての個人住宅に設置することが消防法で義務づけられている
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
マンション火災報知器の基礎知識

マンション火災報知器の基礎知識
マンションにおいて、火災報知器の設置が義務付けられています。ここでは、以下の3つについて解説します。
・マンション火災報知器の役割
・マンション火災報知器の設置義務
・専有部・共用部における火災報知器の違い
マンション火災報知器の役割
火災報知器は、火災によって発生した熱や煙などを自動で感知し、火災を建物内の人にいち早く知らせる役割があります。
火災報知器の設置により、火災が起きてもはじめの段階で発見できるため、初期消火ができるうえ逃げ遅れ防止にも効果的です。実際に、火災報知器の設置が義務化されてからは、火災によって死亡する人の数が減少してきています。
火災を防ぐためには、タバコやストーブの火の消し忘れに気をつけるなど、火の取り扱いに注意することが大前提です。しかし、もし火災が起きてしまっても、初期に発見できればすぐに消火や避難といった対処ができます。
火災を早期発見するうえで、火災報知器の設置はとても重要な役割を果たすのです。
マンション火災報知器の設置義務
火災報知器は、平成16年に行われた消防法の改正により、新築や改築をするすべての住宅を対象に設置が義務付けられています(※1)。高齢化社会の進展や、住宅火災の死者数の増加などを背景に制定されたものです。
既存の住宅においても、各自治体の条例によって平成23年からは設置が完全に義務化されています(※2)。
火災報知器の設置は義務化されているものの、設置の有無について報告する義務や罰則などはありません。そのため、実際には設置されていないマンションもあるのが実状です。
基本的には火災報知器が設置されていることがほとんどですが、設置率は100%ではないことから、マンションの購入前によく確認する必要があります。
※1参考:東京消防庁
※2参考:国民生活センター
火災報知器設置義務とは?場所・住宅タイプ別の条件や罰則を紹介
専有部・共用部における火災報知器の違い
マンションの各戸に設置されている火災報知器はマンションの管理組合で改修等を行うことができます。棟全体の非常通報設備の一部となっているものであり、共用部分の管理と一体となっているという解釈であるためです。
マンションの設備は、大きく分けると専有部と共用部に分類できます。専有部は主に部屋内を指し、共用部は非常階段・エレベーター・エントランスといった部分です。
室内に設置されている火災報知器は、一見すると専有部のものと思われがちですが、マンション全体の設備に関わることから共用部として管理できます。マンションによって管理方法が異なる場合もあるため、自分のマンションの管理規約を確認しておくことが大切です。
鑑定士コメント
古いタイプのマンションだと火災報知器が設置されていないことがあるのでしょうか?
古い賃貸マンションや中古マンションの場合でも、非常警報設備や火災報知器などは基本的には設置されていると考えられます。しかし、設置の有無について報告する義務や、設置していない場合の罰則などはありません。そのため、全ての住宅に設置されているわけではないというのが現状です。契約や購入をする前に、設置されているかどうかしっかりと確認しておきましょう。
マンション火災報知器の種類

マンション火災報知器の種類
マンションの火災報知器は、大きく分けると3つに分類されます。
・熱感知型
・煙感知型
・炎感知型
それぞれどのようなタイプなのか、以下で詳しく解説します。
熱感知型
熱感知型は熱に反応して鳴る報知器です。センサーが一定の温度を検知したときに、警報を発します。戸建て住宅やマンションなどに設置されることが多いタイプです。
熱感知型には2種類あり、ひとつは報知器の内部に入りこんだ空気の温度が上昇、膨張することによって作動する「差動式スポット型」です。リビングや書斎など、温度変化の少ない場所に多く設置されます。
もうひとつは、報知器の周りの温度が一定の温度に達すると作動する「定温式スポット型」です。キッチンのように、温度が高くなりやすいところに設置されます。
煙感知型
煙感知型は煙に反応して警報音を鳴らす報知器です。火災報知器内に入り込んだ煙を察知するタイプで、火災を早期のうちに感知しやすい特徴があります。
煙感知型は2種類に分類され、ひとつは報知器内のセンサーが光の乱反射を察知して警報音を鳴らす「光電式スポット型」です。
もうひとつには、光を発する送光部分と光を受ける受光部分との間に入った煙を検知し、警報を鳴らす「光電式分離型」があります。
煙感知型の火災報知器は、主に寝室や廊下、階段などに多く取り付けられます。
炎感知型
炎感知型は、火災の炎に含まれる紫外線や赤外線の変化を感知して鳴る報知器です。紫外線や赤外線の量が一定量を上回ったときに警報音を鳴らします。
監視できる範囲の広さが特徴です。赤外線の変化を検知する「赤外線スポット型」と、紫外線の変化を検知する「紫外線スポット型」の2種類に分類されます。
高温になりやすく、熱感知器や煙感知器を設置できない場所や、映画館や音楽ホールなどのように天井面が高い大きな空間に設置されます。
火災報知器の種類の基礎知識|選び方の前に押さえるポイントを紹介
マンション火災報知器の設置ルール

マンション火災報知器の設置ルール
マンションにおいて、火災報知器の設置ルールはどのように定められているのでしょうか。ここでは、以下の2つについて解説します。
・消防法で定められた設置基準
・管理組合・オーナー・入居者それぞれの義務
消防法で定められた設置基準
住宅用の⽕災警報器は、マンションをはじめとするすべての個人住宅に設置することが消防法によって義務づけられています。
取り付け場所や維持の仕方については、国の定める基準に従い、市町村の火災予防条例で定められています。取り付け場所の代表例は、キッチン・リビング・寝室・階段などです。
また、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などがすでに設備されている場合は、その箇所において火災警報器の取り付けが免除される場合もあります。
設置基準の詳細は各市町村の条例によって定められているため、火災報知器を設置するときは、市町村の所轄消防署で確認しましょう。
管理組合・オーナー・入居者それぞれの義務
管理組合・オーナー・入居者では、果たすべき義務がそれぞれ異なります。賃貸物件の防火対策として、管理会社はエントランスや階段といった、共用部の防火設備の定期点検・維持管理が主な担当です。
オーナーは建物全体の防火性能を確保することに対して責任を負い、入居者は住戸内の火災予防や避難経路の確保に努めなくてはなりません。
賃貸物件では多くの場合、住宅用の火災警報器をオーナーが設置します。しかし、設置の義務は入居者を含むすべての関係者に発生する点には注意が必要です。
火災報知器の設置をはじめ、どういった責任が生じるのかということは、賃貸契約書に明記されていることがほとんどです。不明な場合は、入居前に管理会社に確認するようにしましょう。
また、マンションを選ぶ際に事前にチェックすべきポイントを知りたい人は、以下の資料を参考にしてみてください。資料のダウンロードは無料です。
鑑定士コメント
マンションに火災報知器を設置しない場合のリスクは何でしょうか?火災報知器を設置せずに火災が起きた場合、逃げ遅れのリスクが高まります。たとえば、深夜の就寝時間帯において火災が起きた場合、火災に気が付かず亡くなってしまうということが想定されます。火災報知器があれば、火災の初期段階で気づけるため、いち早く避難が可能となるとなるのです。
マンションで火災報知器が鳴った際の対処法

マンションで火災報知器が鳴った際の対処法
マンションで火災報知器が鳴った場合、どのように対処すればよいでしょうか。具体的な対処法について、以下の4点を解説します。
・状況を確認する
・火災の場合
・誤報の場合
・自動火災報知設備の場合
状況を確認する
マンションで火災報知器が鳴ったら、はじめに周囲の状況を確認します。キッチンや電化製品周りなど、自宅内の火元となりうる箇所をよく見て、火の気がないかどうかをチェックしましょう。
自宅内で火の気がなく、煙の臭いもない場合は、マンション内で火災が起きていないかを念のため確認します。窓を開けたり外に出てみたりしたうえで、火や煙があがっていないかを確かめてください。
常に火災が起きている前提で動くことが大切です。現場を確認するなかで、炎や煙などが確認されず、火災ではないことが明確になるまでは緊張感を持って対応しましょう。
火災の場合
火災が起きていた場合は、すぐに119番へ通報のうえ周囲の人に火災が起きたことを伝えましょう。
火が天井に達していない場合は、初期消火を行います。普段から消火器の位置を確認しておくとよいでしょう。火が天井に達していたら、自力での消火をあきらめ、外に避難のうえ119番へ通報します。
屋外にいるときに火災に気づいた場合は、すぐに119番へ通報し、火が小さければ初期消火に協力しましょう。ただし、屋外から分かるほど火が燃え広がっている場合は、安全のため建物から離れます。消防への通報と、周囲の人の誘導に努めましょう。
誤報の場合
誤報だった場合は、火災報知器の警報音を止めましょう。誤報の原因はさまざまで、経年劣化や暖房器具の温風による温度上昇、気圧の変化などが挙げられます。状況を確認し、火事ではないことが確認できたら、火災報知器の音を停止させてください。
本体についているボタンを押すか、本体に付属されている紐をひっぱることで音を止められます。もしわからない場合は、取扱説明書を確認しましょう。
音を止めたら、誤報の原因を確認します。火災報知器の寿命は、使用環境にもよりますがおよそ10年が目安です。使用期限を確認し、必要に応じて交換を検討しましょう。
自動火災報知設備の場合
マンションに設置された自動火災報知設備の非常ベルが鳴った場合の対応は、家庭用の火災報知器が鳴ったときとほぼ同じです。周囲の状況を確認し、火災の場合は119番通報をします。
自動火災報知設備は、火災を見つけた人が発信機を押したり、火災による熱や煙などを感知器が感知したりした際に非常ベル等が鳴る仕組みです。火災が起きたエリアは受信機で確認できますが、受信機はマンションの中央管理室や防災センターに設置されています。
状況を確認しても火事かどうかわからない場合は、火災が起きていないことを確認できるまで、屋外の安全なところに避難しましょう。しばらくしても警報音が鳴りやまない場合は、管理会社に確認するのもひとつの手です。
まとめ:マンションの火災報知器は、火災の早期発見と迅速な設備が重要

まとめ:マンションの火災報知器は、火災の早期発見と迅速な設備が重要
マンションに設置されている火災報知器は、火災で発生した熱や煙をいち早く知らせてくれるもので、初期消火や逃げ遅れ防止などに効果的です。
マンションは、部屋内である専有部と、エントランスや非常階段などの共用部にわかれます。専有部の火災報知器は、マンション全体に関わる設備であることから、共用部のものとして管理組合が改修等を行えることを覚えておきましょう。
また、マンションの⽕災警報器は、すべての個人住宅に設置することが消防法で義務づけられています。具体的な取り付け場所は、各市町村の火災予防条例で定められているため、自宅内に適切に取り付けられているかどうかをいま一度確認しましょう。
#火災報知器、#設置、#感知器、#火災

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
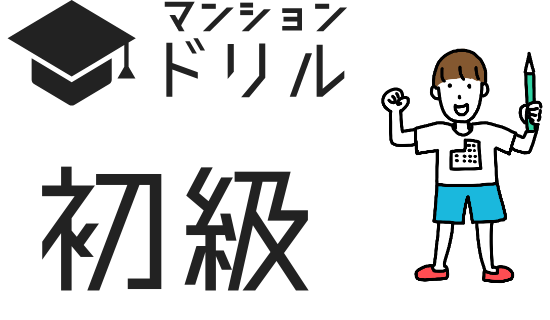
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。