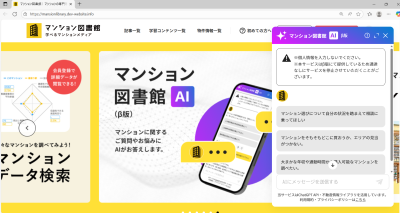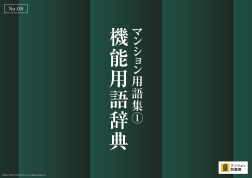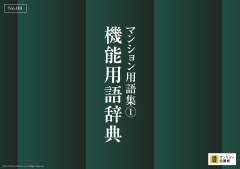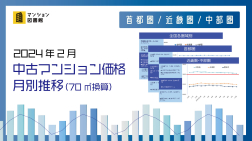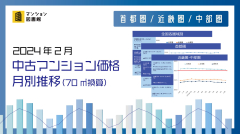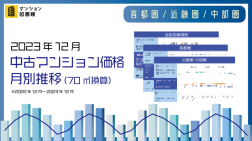全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.04.27
登録日:2025.04.25
火災報知器電池交換を自分で!初心者でも迷わずできる手順を解説

「火災報知器の電池交換は自分でできるの?」
「火災報知器の電池交換を自分で行う手順を知りたい。」
上記の疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では火災報知器の電池交換は自分でできるのかを詳しく解説します。交換手順やポイント・トラブル時の対処法なども紹介しますので、自分で火災報知器の電池交換を行いたい方はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
・住宅用の火災報知器なら、自分で電池交換をできる
・火災報知器の電池交換を自分で行う際の手順
・電池交換にかかる費用は100円〜1,500円程度
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
火災報知器の電池交換は住宅用であれば自分でできる!

火災報知器の電池交換は住宅用であれば自分でできる!
結論から言うと、住宅用の火災警報器の電池交換は自分でできます。
火災警報器には「電池式」と「内蔵電池式」の2種類があります。電池式は自分で交換できるタイプで、ドライバーがあれば簡単に交換可能です。
一方、内蔵電池式は電池交換ができず、本体ごと交換する必要があります。 寿命が来たらそのまま使い続けることはできないため、専門業者に依頼するのが一般的です。
電池式なら自分で交換可能ですが、内蔵電池式は交換できません。
なお、賃貸物件では電池交換の費用は「借主負担」となるケースが多いです。これは照明の電球交換と同じ扱いになるためです。交換が必要な際に備えて契約内容を確認しておくと安心でしょう。
火災報知器の電池交換を自分で行う手順

火災報知器の電池交換を自分で行う手順
火災報知器の電池交換を自分で行う際の手順は、以下のとおりです。
・火災報知器の種類と電池の種類を確認する
・電池交換に必要な道具を準備する
・火災報知器を取り外す
・古い電池を取り出す
・新しい電池を取り付ける
・火災報知器を元に戻す
火災報知器の種類と電池の種類を確認する
火災報知器は大きく2種類に分かれます。
また、使われている電池も2種類です。
・リチウム電池
・アルカリ電池
リチウム電池は約10年と長寿命で、多くの住宅用火災報知器に採用されています。
一方、アルカリ電池は寿命が約1年と短く、交換の頻度は高くなりますが、価格が安いのが特徴です。
「そろそろ電池交換かな?」と思ったら、まずは火災報知器と電池の種類をそれぞれ確認しましょう。
電池交換に必要な道具を準備する
火災報知器の種類と電池を確認したら、スムーズに交換できるよう道具を用意しましょう。
多くの火災報知器は天井や壁にネジやブラケットで固定されています。取り外しには「ドライバー」があると便利です。「電動ドライバー」を使うと、作業がよりスムーズになるでしょう。
また、火災報知器は高い場所に設置されているため、「脚立」や「踏み台」も必要です。安定性の高いものを選び、転倒しないよう注意しましょう。
交換前に必要な道具を揃え、安全に作業できるようにしてください。
火災報知器を取り外す
道具が揃ったら、火災報知器の取り外し作業に移ります。
天井側の台座(取付ベース)がネジで天井に固定されている場合は、ドライバーを使って取り外しましょう。
本体は、天井に押し付けながら左(反時計回り)に回すと外れます。半周ほど回せば取れることが多いですが、固くて動かない場合は、無理をせず販売メーカーや管理会社に相談してください。
なお、本体は意外と重いことがあるため、落とさないよう注意が必要です。
作業自体は数分で終わるので、焦らず安全に進めましょう。
古い電池を取り出す
火災報知器を取り外したら、電池蓋を開けて古い電池を取り出しましょう。電池蓋は本体の側面や裏面にあることが多いですが、機種によって異なります。
多くの機種では、電池がコネクタで接続されています。コネクタは無理に引っ張らず、丁寧に取り外してください。コネクタを外せば、電池を取り出すことができます。
電池を外した後は、接続部分や本体内部に汚れがないか確認し、必要に応じて掃除しましょう。
また、取り出した電池は、コネクタ部分だけでなく、電池のプラス(+)とマイナス(−)極にもテープを巻き、絶縁処理を行ってください。
新しい電池を取り付ける
新しい電池を本体の電池収納部に取り付けます。電池の向きを確認し、正しくセットしましょう。また、電池についているフィルムは保護のためのものなので、剥がさないでください。
コネクタを本体の電池端子に差し込みます。その際、コードの色と表示を合わせ、極性を間違えないよう注意しましょう。逆向きでは動作しません。コネクタは奥までしっかり差し込んでください。
なお、接続時にドライバーを使用すると、ショートや破損の原因になるため避けましょう。
最後に、電池蓋を忘れずにしっかり閉めてください。
火災報知器を元に戻す
新しい電池を取り付けたら、火災報知器を元の位置に戻します。
まず、天井に土台(取り付けベース)を固定します。付属のネジを使い、ドライバーでしっかり締めましょう。
次に、本体を時計回り(右)に回して固定します。しっかりはめ込み、「カチッ」と音がするまで回しましょう。確実にセットされているかをチェックしてください。
なお、火災報知器を取り付ける前に以下の点も確認すると、正しく取り付けられます。
・本体の表面が濡れていないか
・電池コネクタが確実に接続されているか
・煙や熱の入口にホコリやクモの巣がないか
・元の場所に取り付けているか
・引きひもがある場合、正しく通っているか
作動確認テストをする
火災報知器を取り付けたら、最後に作動確認を行いましょう。
テストボタンを押すか、ひもを引っ張ると警報音が鳴り、表示灯が点灯します。音やランプは自動で止まるので安心してください。
もし警報音が鳴らない場合や表示灯が点灯しない場合は、取り付けミスの可能性があります。
その際は、以下のポイントを確認しましょう。
・電池の向きや接続が正しいか
・本体がしっかり固定されているか
・コネクタが確実に挿入されているか
上記を確認しても作動しない場合は、故障の可能性があるため、メーカーや管理会社に連絡してください。
火災報知器の電池交換は自分でできますが、取り付けに自信がない方はプロに依頼するのも一つの選択肢です。プロに頼むべきか迷っている方は、以下の記事を読んで最適な方法を選んでください。
火災報知器の電池切れで交換するときの方法は?プロに頼むべきケースも解説!
火災報知器電池交換を自分で行うときのポイント

火災報知器電池交換を自分で行うときのポイント
火災報知器の電池交換をする際は、いくつかのポイントに注意しましょう。
電池の寿命が近づくと、警報音やランプの点滅で知らせてくれます。「ピッ、電池切れです」と鳴ったり、赤いランプが点滅したりすると交換のサインです。
取り外すときは、煙流入口を強く持たないようにしましょう。無理な力を加えると破損の原因になります。
交換する電池は必ずメーカー純正のものを使用してください。純正以外の電池では、必要なときに正しく作動しない可能性があります。また、間違えて別の部屋に設置しないように注意しましょう。
ホコリが溜まると煙を感知しにくくなるため、乾いた布で拭き取ることも大切です。特に台所では油汚れがつきやすくなります。中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってから、取り付けましょう。
【場面別】火災報知器の電池交換のトラブルを自分で対処する方法

【場面別】火災報知器の電池交換のトラブルを自分で対処する方法
ここでは、火災報知器の電池交換中に発生しやすいトラブルと、その解決方法を紹介します。
・電池を交換しても作動しない
・電池の種類を間違えた
・火災報知器が壊れてしまった
・電池交換中に警報が鳴り止まない
電池を交換しても作動しない
電池を交換しても作動しない場合、本体の寿命かもしれません。「普段使わないのに交換が必要?」と思うかもしれませんが、火災報知器は毎日稼働しているのです。
長年使い続けるとホコリが溜まったり、電子部品が劣化したりして、火災時に正常に作動しなくなるおそれがあります。
そのため、電池切れのタイミングは、本体の交換時期と考えてもいいでしょう。
なお、総務省消防庁によると、住宅用火災報知器の交換目安は、10年です。(※)
設置時期は、本体に記載された設置年月や製造年で確認できます。交換が必要なら、家電量販店やホームセンターで購入しましょう。
※ 参照:総務省消防庁
電池交換の際に火災報知器が劣化しているかどうかを確認する方法を、以下の記事で紹介しています。詳しく知りたい方は確認してみてください。
火災報知器の電池切れで音が止まらない!自分でできる対処法と注意点
電池の種類を間違えた
火災報知器の電池交換で種類を間違えたら、すぐに正しい電池に交換しましょう。 間違った電池を入れると、正常に作動しないことがあります。
また、「純正は高いから安いやつにしよう」と思うかもしれませんが、それは危険です。非純正電池はメーカーの品質管理を受けておらず、発熱や発火のリスクがあります。火災報知器は命を守る大切な機器なので、必ずメーカー純正の電池を使いましょう。
リチウム電池とアルカリ電池は見た目が似ているため、間違えて入れてしまうこともあります。交換前に説明書や本体の表示を確認し、適切な電池を選んでください。
どの電池を使えばいいかわからないときは、メーカーや販売店に相談しましょう。
火災報知器が壊れてしまった
取り付け時のミスや強い衝撃で火災報知器が壊れてしまった場合は、新しいものに交換するようにしてください。
総務省消防庁の調査によると、火災報知器を設置している住宅では、設置していない住宅に比べて火災による死者数や損害額が半減し、焼損床面積も6割減という結果が出ています。(※)
火災報知器がないと火災時の被害が大きくなる可能性があるため、早めに取り付けましょう。
火災報知器の交換は自分でできますが、取り付けに不安がある場合は専門業者に依頼するのも一つの方法です。
なお、火災報知器が「故障です」と警報が鳴り続ける場合は、電池を取り外すことで音を止められます。ただし、そのまま放置せず、必ず新しい火災報知器を設置してください。
※ 参照:総務省消防庁
電池交換中に警報が鳴り止まない
火災報知器の電池交換中に、警報が鳴り止まなくて困ることがあります。これは、火災報知器が正常に作動するまで続く仕組みになっているためです。
警報を一時的に止めるには、次の方法を試してみましょう。
・警報停止ボタンを押す
・ひもを引っ張る
ただし、上記はあくまで一時的な対応です。電池を交換しない限り、30分ごとなど一定間隔で再び鳴り続けることがあります。
警報の音を止めたあとは速やかに電池交換を完了させましょう。
以下では、火災報知器のほかにも知っておくべきマンション設備の用語を詳しく紹介しています。無料でダウンロード可能ですので、ぜひ読んでみてください。
鑑定士コメント
リチウムイオン電池はリサイクルが基本です。希少な金属であるリチウムを再利用するため、また発火の危険を防ぐためにも、適切な処分が必要です。
処分する際は、自治体指定の回収場所や家電量販店の専用回収ボックスを利用しましょう。他のゴミと混ぜるのは大変危険です。膨張や異臭がある場合は特に注意し、安全に廃棄してください。
自分で電池交換する場合の費用

自分で電池交換する場合の費用
火災報知器の電池交換を自分で行う場合、費用も気になるところです。 電池の種類によって価格が異なるため、事前に確認しておきましょう。
なお、前述のように、電池切れは「本体の交換時期」でもあります。長く使っている場合は本体ごとの交換を検討しましょう。
本体の交換費用は、1台あたり約1万円が目安です。
また、火災報知器は寝室や寝室のある階の階段など、複数の設置が義務付けられています。 交換時には、トータルの費用も考慮しておくことが大切です。
火災報知器は命を守る重要な機器。しっかり交換し、安全を確保しましょう。
火災報知器の電池交換の費用を抑えるコツ

火災報知器の電池交換の費用を抑えるコツ
火災報知器の電池交換にはコストがかかりますが、工夫次第で節約することが可能です。ここでは火災報知器の電池交換の費用を抑えるコツを3つ紹介します。
・電池をできるだけ長持ちさせる
・お得な方法で電池を購入する
・火災報知器の定期的なメンテナンスで寿命を延ばす
電池をできるだけ長持ちさせる
火災報知器の電池は、環境や使い方によって寿命が変わります。 少しでも長く使えるよう、工夫しましょう。
まず、定期的な掃除が重要です。 ホコリや汚れが溜まると、センサーに負担がかかり、電池の消耗が早くなります。汚れが気になったら、乾いた布で優しく拭き取りましょう。
水洗いは故障の原因になるため避けてください。ベンジンやシンナーなどの強い溶剤も使用しないようにしましょう。
特に台所に設置している場合は注意が必要です。 油煙がセンサーに付着すると誤作動を起こしやすくなり、電池の消耗を早める原因になります。
こまめな手入れで、電池を長持ちさせましょう。
お得な方法で電池を購入する
電池の購入方法を工夫すれば、コストを抑えることができます。
まず、価格を比較することが大切です。 ホームセンターでは1個1,000円強することがありますが、ネット通販なら100円~200円ほど安くなることも少なくありません。
また、火災報知器は家に複数設置されているのが一般的です。そのため、まとめ買いを活用することで、1個あたりのコストをさらに下げることができます。必要な個数を把握し、まとめて購入するとお得です。
さらに、セール時期を狙うのも一つの方法です。 年末年始やブラックフライデーなどの大規模セールでは、通常より安い価格で購入できることが多くなります。タイミングを見計らってお得に電池を手に入れましょう。
火災報知器の定期的なメンテナンスで寿命を延ばす
火災報知器は、定期的なメンテナンスを行うことで寿命を延ばすことができます。
少なくとも年に1回以上の「外観点検」と月に1回の「機能テスト」を実施し、常に正常に作動していることを確認しましょう。
外観点検では、感知部にホコリやクモの巣が付いていないかをチェックします。もし汚れがあれば、掃除機を使って優しく取り除きましょう。
機能テストでは、テストボタンを押して警報音が正しく鳴るか確認してください。長期間、特に3日以上留守にしていた場合は、帰宅後に一度テストを行い、正常に作動しているか確認するのがおすすめです。
定期的な点検とお手入れを習慣にすることで、火災報知器を安全に、そして長く使用することができます。
火災報知器の電池がどこで購入できるのか知りたい方は、以下の記事で販売場所を紹介しているので、ぜひご確認ください。
火災報知器の電池が切れた!どこに売ってる?販売場所や交換方法を紹介
鑑定士コメント
電池交換を忘れないためには、「習慣化」が大切です。 スマホのリマインダーやカレンダーに交換予定を登録すると、忘れる心配がありません。また、家族で情報を共有したり、本体に交換日を記入したシールを貼ったりするのも有効です。次回の交換時期を明確にして、交換忘れを防ぎましょう。
自分で安全に電池交換するための注意点

自分で安全に電池交換するための注意点
火災報知器は高い場所にあるため、安全に交換することが大切です。手が届かない場合は、安定した踏み台や脚立を使いましょう。使用前に耐荷重や取扱説明書を確認すると安心です。
注意したいのが危険なイスやテーブルの使用です。回転するイスやパイプ製のイスはバランスを崩しやすく、転倒のリスクがあるため避けたほうがいいでしょう。
また、電池を交換するときは向きを間違えないように注意してください。コネクタがある場合は、無理に引っ張ると破損することがあるので、慎重に扱いましょう。
安全に気をつけながら、正しく交換してください。
まとめ:火災報知器の電池交換は手順をしっかり守って行おう

まとめ:火災報知器の電池交換は手順をしっかり守って行おう
火災報知器の電池交換は自分でできますが、正しい手順を守ることが大切です。交換時には、電池の種類や向きを確認し、無理に取り外さないよう注意しましょう。
また、火災報知器の寿命は約10年です。電池を交換しても作動しない場合は、本体の交換が必要かもしれません。長く使用している場合は、設置時期を確認し、本体の買い替えも検討しましょう。
定期的な点検やメンテナンスを行い、火災報知器が常に正常に作動する状態を維持することが重要です。正しく交換し、しっかりと備えましょう。
#電池、#交換、#住宅用火災警報器

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
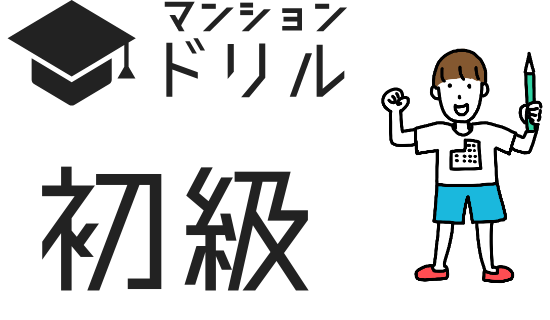
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。