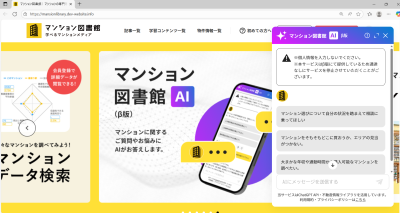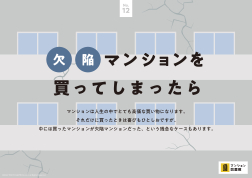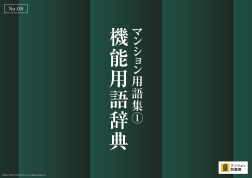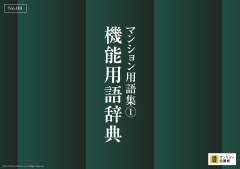全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.10.27
登録日:2023.07.20
液状化対策ガイド|地盤改良工法と費用、土地選びの注意点

地震が起きたとき、ニュースで「液状化現象」という言葉を聞いたことはありませんか。
液状化とは、地震の揺れで地盤がゆるみ、家が沈んだり傾いたりする深刻な被害を引き起こす現象です。しかし、事前に対策しておけば、そのリスクを減らすことができます。
本記事では、液状化現象が起きる仕組みや発生しやすい土地の特徴、地盤改良や対策工事の方法、費用の目安をわかりやすく解説します。長く安心して暮らせるマンションを選ぶために、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事でわかること】
・液状化現象とは、地震の揺れで地盤の砂などの粒子の結びつきが弱くなる現象
・砂地盤で砂が柔らかい場合や砂が地下水に浸されている場合に発生しやすい
・地盤改良や対策工事の方法と費用相場
・地震保険や補助金など公的支援の活用方法
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
液状化現象とは?

液状化現象とは?
液状化現象とは、地震の衝撃によって地盤に強い衝撃を受け、地盤を形成している砂などの粒子の結びつきが弱くなる現象です。通常、地盤は砂や礫、粘土などの粒子が強く結びつき、その間に水が満たされることで地盤が支えられています。
しかし、地震によって砂などの粒子の結びつきが弱くなると、粒子が水に浮いた状態になってしまいます。この状態を液状化と言い、液状化現象が発生すると、水よりも比重が重い建物が沈んだり傾いたりしてしまうのです。また、地盤の比重が液状化によって変化することで、地面に埋められたマンホールなどが浮上するなどの被害も発生します。
なお、液状化現象については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
液状化が発生しやすい条件

液状化が発生しやすい条件
液状化現象には、発生しやすい地盤があります。ここでは、どのような地盤で液状化が発生しやすいかについて解説します。
液状化が発生しやすい条件は次の3つです。
・砂地盤である
・地盤の砂が柔らかい
・砂が地下水に浸されている
砂地盤である
砂で形成された地盤は、液状化が発生しやすいのが特徴です。特に浅い位置に砂層があると、液状化現象が発生する危険性があります。粒子の大きさによる粒子同士の結びつきの強さや水はけが、砂地盤で液状化現象が発生しやすい原因です。
地盤を形成する地層には、砂層のほかに粘土層や礫層などがあります。粘土の粒径は0.005mm以下(※)と粒子が小さいため、結びつきが強く液状化現象が発生しにくいです。また、礫の粒径は2mm以上(※)あり、水はけがよいためこちらも液状化現象が発生しにくい傾向にあります。
一方、砂の粒径は0.074〜2mm(※)です。粘土ほど粒子同士の結びつきが強くなく、礫ほど水はけも良くありません。そのため、砂層は液状化現象が発生しやすい地盤だといわれています。
地盤の砂が柔らかい
砂層の地盤だという理由だけでは、液状化現象が発生するとは限りません。しかし、地盤が固まっておらず、砂が柔らかいと液状化現象のリスクは高まります。液状化現象は、粒子の結びつきの強さによって発生リスクが変わります。
しっかりと固められた砂層であれば、粒子の結びつきが強くなるため、ある程度の地震には耐えることができるでしょう。しかし、ふんわりと集まっているだけの砂層では、粒子がバラバラになりやすいため液状化現象が発生しやすくなります。
砂が地下水に浸されている
砂が地下水に浸されている場所も液状化が発生しやすい条件です。地下水の表面は地下水面と呼ばれ、地下水面を境界として浸水している部分としていない部分に分かれています。地層にある地下水は、すべての地層を満たしているわけではありません。
地震が発生すると地盤の粒子がバラバラになり、粒子が水に浮くことで液状化現象が発生します。そのため、地下水に浸されている砂層が地層に近いほど液状化のリスクが高まります。
鑑定士コメント
液状化現象は、地震が起きても必ず発生するとは限りません。地震の揺れの大きさや揺れの継続時間も液状化現象の発生に関係します。
また、本文に記載のとおり、一定の条件に該当しない地盤は、液状化のリスクは低いでしょう。
液状化現象への対策

液状化現象への対策
購入したマンションや戸建ての地盤で液状化現象が発生すると、最悪の場合は家が倒壊してしまう可能性もあります。そのため、できるだけ液状化現象の発生リスクを低くすることが重要です。ここでは、液状化現象への対策を3つ解説します。
・自宅の土地リスクを知る
・地盤を改良する
・液状化対策工事をする
自宅の土地リスクを知る
液状化対策は、まず自宅や購入予定地のリスクを知ることから始めましょう。液状化を防ぐには、地盤の強さを確認することが重要です。
リスクを調べる際は、国土交通省の「重ねるハザードマップ(※1)」や「KuniJiban(※2)」などのツールが役立ちます。
「重ねるハザードマップ」では、住所を入力し「土地の特徴・成り立ち」→「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を選ぶと、地図に色がつきエリアごとの液状化リスクが表示されます。
紫や赤に近いほど発生傾向が高いことを示し、凡例から詳しい説明も確認可能です。さらに地形分類を重ねることで、埋立地や低地など地形の成り立ちも把握できます。
「KuniJiban」では柱状図を閲覧し、地中の土質やN値(地盤の硬さ)を確認できます。自治体が公開する液状化予測図もあわせて参考にすると安心です。
※1 参照:国土交通省
※2 参照:国土地盤情報検索サイト
なお、洪水ハザードマップについては下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
鑑定士コメント
公開資料などで液状化しやすいエリアに入っていた場合、不安になるでしょう。しかし、液状化を引き起こす要因には様々な条件があり、必ずしもエリア全体が液状化するとは限りません。エリア内でも、土地によってその地層のでき方は違います。不安な場合は、専門の地質調査を依頼するのがおすすめです。その結果により、地盤改良の手段もあります。
地盤を改良する
液状化の心配がある土地でも、地盤改良を行えばリスクを減らせます。代表的な工法は、次のとおりです。
また、「転圧」という方法もあります。更地の状態で重機を走らせ、地面をしっかり踏み固めることで地盤を強くする工法です。地盤強化に有効ですが、効果は地表から約1mまでと浅い点には注意が必要です。
液状化対策工事をする
液状化のリスクは、すでに建っている家でも工事で減らせます。
代表的なのが「アンダーピニング工法」です。建物の重さと油圧ジャッキを使い、新しい杭を地中深くの固い地層まで打ち込んで家を持ち上げる方法で、ミリ単位で高さを調整できます。住んだまま工事できるため仮住まいは不要で、一般的な木造住宅なら3週間ほどで完了する点がメリットです。
また、「薬液注入工法」も建物が建ったあとに施工可能で、地盤を固めて強度と止水性を高めます。
さらに「浅層混合処理工法」や「深層混合処理工法」、「直接基礎(ベタ基礎)」などもあり、地盤や建物の条件に応じて選べます。
費用はかかりますが、事前に対策工事をしておけば建物の沈下や傾きを防ぎやすく、あとから大がかりな修理をする必要が減ります。液状化が起きても被害が小さく済み、生活の再建も早くなるでしょう。
液状化現象で知っておきたい対策費用と公的支援

液状化現象で知っておきたい対策費用と公的支援
液状化対策工事には、まとまった費用がかかります。決して安いものではないため、あらかじめおおよその費用感を知っておくと、予算計画が立てやすく安心です。
また、地震保険や自治体の補助金を活用すれば、自己負担を減らすこともできます。
ここでは、代表的な工法の費用相場と、活用できる公的支援制度を紹介します。
工法ごとの費用相場
地盤改良や液状化対策工事は、工法によって費用が大きく変わります。主な工法の費用相場は次のとおりです。
・注入工法:300~600万円(※)
・表層改良工法:100万〜500万円
・アンダーピニング工法:600万〜1000万円(※)
・深層混合処理工法:350万〜500万円
・直接基礎(ベタ基礎):100万〜320万円
実際の金額は、家の大きさや地盤の状態、施工範囲によって変動します。正確な費用を知るには、専門業者に見積もりを依頼しましょう。
※参照:埼玉県
地震保険への加入と補助金の活用
液状化対策をしていても、大規模地震では液状化が起きる可能性があります。そのため、地震保険への加入がおすすめです。
液状化で家が沈下・傾いた場合も、損害の程度に応じて保険金が支払われます。判定は専門の鑑定人が行い、全損なら満額、大半損なら60%、一部損なら5%が支払われます。(※1)
傾きが基準を超えると、外観の損傷が少なくても半損と認定されることがあるため、液状化リスクが高い地域では特に加入を検討しましょう。
また、自治体によっては補助金制度もあります。例えば東京都では、住宅の新築・建て替え時に行う液状化判定調査費用の一部(最大10万円)が補助されます(対象期間:令和7年4月1日~令和8年2月27日)(※2)。
補助内容は自治体ごとに異なるため、事前に確認して上手に活用しましょう。
※ 参照1:損保ジャパン
※ 参照2:東京都建物における液状化対策ポータルサイト
マンション選びでは、パンフレットやチラシの見方も大切です。下記の資料で確認ポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてください。
液状化現象が起きてからの対処法・修復工法

液状化現象が起きてからの対処法・修復工法
液状化対策をしていても、大きな地震では被害を完全に防げないこともあります。万一に備えて、被害後の修復方法も確認しておきましょう。
液状化現象が起きてからの代表的な修復工法は次のとおりです。(※)
建物や地盤の状態によっては、複数の工法を組み合わせて行う場合もあります。
※参照:埼玉県
まとめ:液状化現象の対策を理解し、マンション探しの参考にしよう

まとめ:液状化現象の対策を理解し、マンション探しの参考にしよう
液状化現象は、地盤の粒子の結びつきが弱くなることで、地面が液状になる現象です。特に砂層の地盤で発生しやすく、埋め立て地や旧河道では地震による液状化現象の被害が多く報告されています。マンションを選ぶ際は、液状化現象が発生するリスクができるだけ低い土地を選ぶことが重要です。
とはいえ、そのほかの地盤でも絶対に液状化現象が発生しないとは言い切れません。地盤改良が行われているか、マンションそのものに液状化対策の工事が施されているかも確認する必要があります。液状化現象の対策を理解して、マンションを探す際の参考にしましょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター
石川 勝
東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
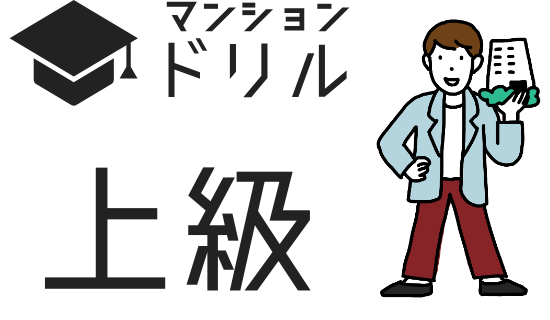
マンションドリル上級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。