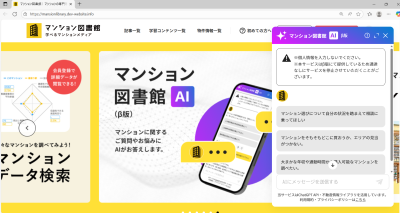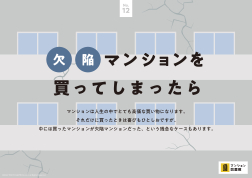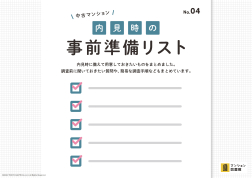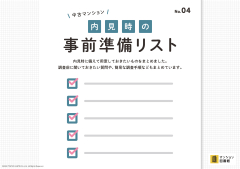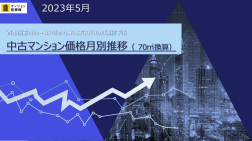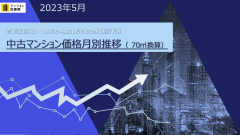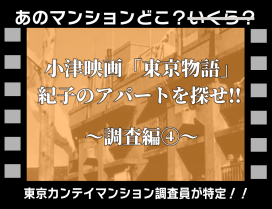全国市況レポート

注目記事
学ぶ
更新日:2025.04.25
登録日:2025.04.25
火災報知器外し方は?初心者でも簡単にできる手順を解説

「火災報知器の外し方がわからない」
「火災報知器を外してはダメなケースもある?」
住宅に設置した火災報知器を取り外すときは、正しい方法で行う必要があります。故障したときや交換するときのために、正しい外し方を確認しておくことが重要です。
本記事では、火災報知器を正しく外すための基礎知識をわかりやすく解説します。新しい火災報知器を設置して命を守るためにも、あらかじめチェックしておきましょう。
【この記事でわかること】
・一般住宅の電池式の火災報知器なら自分で簡単に取り外し可能だが、電気式(配線式)の場合は資格のある業者への依頼が必要
・火災報知器の取り付けが義務付けられている場所は、自治体によって異なる
・取り外し作業時には安全な足場を確保し、処分する際は電池を分別する
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
火災報知器の外し方

火災報知器の外し方
火災報知器の外し方について、基本の手順を紹介します。
・安定感のある足場を用意する
・本体の外周を持って上に押し付けながら左(反時計回り)に回す
・ロックが外れた本体を邪魔にならない場所に置く
・ドライバーで取り付け用ネジを緩めて取り付けベースを取り外す
取り付けベースがなく壁にビスで固定してある場合は、取り付けネジを緩めて取り外します。くわしい外し方は機種によって異なるので、説明書や公式サイトで確認しておくと安心です。なお、型番は本体に記載されています。
火災報知器は外しても問題ないか確認する必要がある

火災報知器は外しても問題ないか確認する必要がある
火災報知器の中には、外してはいけないものがあります。
・外しても大丈夫なケース
・外したらいけないケース
見分け方を紹介するので、外し方とあわせてチェックしておきましょう。
外しても大丈夫なケース
電池式の火災報知器なら、自分で簡単に取り外すことができます。一般的な住宅では電池式が使用されることが多いため、ほとんどのケースで外して問題ありません。電池式かわからない場合は、記載されている型番をもとに調べられます。
ただし、火災報知器の取り外しは交換が前提です。すべての住宅で住宅用防災機器の設置が義務づけられているため、外したままにすると違反にあたります(※)。寝室と階段など設置義務がある場所の火災報知器は、かならず新しいものと交換しましょう。
※参照:独立行政法人国民生活センター
外してはいけないケース
電気式(配線式)の火災報知器は、自分では取り外しができません。電気工事が必要なので、資格をもったプロの専門業者に依頼する必要があります。記載されている型番を確認して、電気式に該当するかチェックしましょう。
天井が高いなどの理由で、取り外しが難しいケースもあります。安全に作業ができないと感じたときは、無理せずに専門業者に依頼することを検討してください。
また、賃貸住宅の場合、火災報知器を勝手に取り外すとトラブルにつながります。経年劣化による交換は貸主に負担してもらえる可能性があるので、まずは相談することが大事です。
鑑定士コメント
マンションにも火災報知器の設置義務があるため、自分で取り外してはいけません。もし経年劣化や故障で作動しなくなったときは、まず管理会社や大家に相談しましょう。リフォームなどで一時的に取り外すときも、あらかじめ許可をとっておくと安心です。なお、マンションの場合、火災発生時にマンション全体に警報が鳴る「自動火災報知設備」が設置されているケースがあります。もちろんこちらも勝手に取り外すことはできません。
火災報知器を外すときの注意点

火災報知器を外すときの注意点
火災報知器を外すときの注意点をまとめました。
・作業時の注意点
・火災報知器を交換するときの注意点
・廃棄時の注意点
注意点を把握しておくことで、トラブルを防げます。
作業時の注意点
火災報知器を外すときは、基本的に高所で作業することになります。上をむいて手元に集中していると、足を踏み外す可能性があるので注意が必要です。
はしごなど丁度よい高さの安定した足場を用意します。安定した場所に設置して、怪我をしないよう慎重に作業することが重要です。
火災報知器を交換するときの注意点
火災報知器を外して交換する場合は、設置する場所に注意が必要です。基本的に同じ場所に設置すれば問題ありませんが、間違った場所に取り付けられている可能性も考えられます。
火災報知器の取り付けが義務付けられている場所は、自治体によって異なります。交換する前に、自治体の公式サイトなどでルールを確認しておくと安心です。
廃棄時の注意点
外した火災報知器を廃棄する場合、本体と電池を分別する必要があります。接続したまま廃棄すると、火災の原因になるため注意が必要です。
カバーがある場合はドライバーで外して、電池のコネクターを引き抜きましょう。あとは電池を本体から取り外して、両端とコネクター部分に絶縁テープを巻いてから処分します。
なお、以下の資料では、マンションタイプごとの注目すべき要素を確認できます。マンションの購入を検討している方は、ぜひダウンロードしてください。
火災報知器を外したときのトラブル解決方法

火災報知器を外したときのトラブル解決方法
火災報知器を外したとき、トラブルが発生することがあります。
・火災報知器が外れないとき
・火災報知器を外したら壊れてしまったとき
・火災報知器を外した後の処分がわからないとき
スムーズに解決するための方法を、チェックしておきましょう。
火災報知器が外れないとき
火災報知器が外れない場合、外し方が間違っている可能性があります。本体に記載されている型番を確認したうえで、説明書やメーカーの公式サイトでくわしい外し方を調べましょう。
また、電気式など、自分では取り外せないタイプの火災報知器もあります。自分だと外せない場合は、無理をせずプロに依頼することを検討してください。
火災報知器を外したら壊れてしまったとき
火災報知器を外して壊れてしまった場合、また取り付けて使用するのは危険です。火災が発生したとき警報が鳴らず、適切に対応できない可能性があります。
ボタンを押すもしくは引き紐を引いて正常に作動しない場合は、新しい火災報知器に交換しましょう。なお、火災報知器の寿命は10年が目安なので、過ぎている場合は故障していなくても交換を検討してください(※)。
※参照:消防庁
火災報知器を外した後の処分がわからないとき
本体を不燃ごみ、電池は自治体のルールに従って処分するのが一般的です。分別や捨て方は自治体によって違うため、あらかじめチェックしておきましょう。
火災報知器に使われている電池は、「リチウムイオン電池」です。処分方法について、自治体の公式サイトや問い合わせで調べておくことが重要です。
なお、以下の記事では、火災報知器が誤作動を起こしたときの止め方を紹介します。火災じゃないのに警報が鳴ったとき止められるように、ぜひチェックしてください。
火災報知器電池交換を自分で!初心者でも迷わずできる手順を解説
鑑定士コメント
火災報知器を外しても罰金や罰則はありません。しかし、火災報知器の設置は、消防法や各市町村の条例により義務付けられています。火災報知器を外したままにすると、火災が発生してもすぐに気付けない可能性があるので注意が必要です。自分や家族の命を守るためにも、外したあとは新しい火災報知器を取り付けましょう。
まとめ:火災報知器は解説書に沿って正しく外すことが大切

まとめ:火災報知器は解説書に沿って正しく外すことが大切
外し方さえわかれば、火災報知器は簡単に取り外せます。説明書や公式サイトでくわしい方法を確認したうえで、取り外しましょう。
一方で電気式(配線式)の火災報知器など、自分では取り外しができないケースもあります。外せるケースと外せないケースについて、あらかじめ確認しておくと安心です。
外すときの注意点やトラブル解決方法も紹介したので、あわせてチェックしておきましょう。設置は義務付けられているため、外したあと新しい火災報知器に交換してください。
#火災報知器、#交換、#設置、#住宅用火災警報器、#電池切れ
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
あなたのマンションの知識を確かめよう!
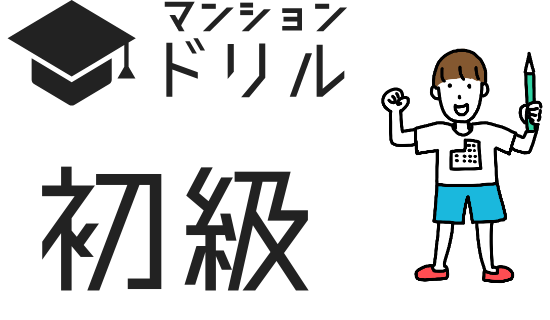
マンションドリル初級
あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。