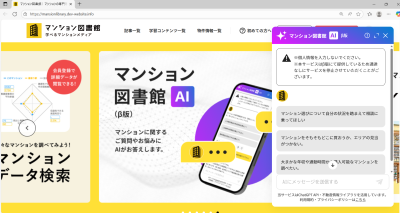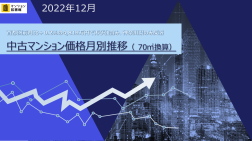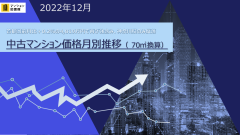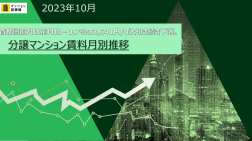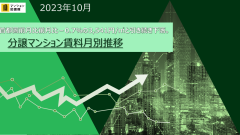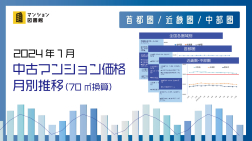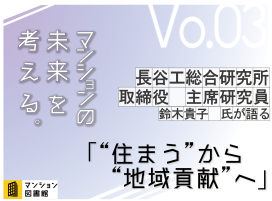全国市況レポート

注目記事
未来を知る
更新日:2025.05.09
登録日:2024.05.31
マンションの未来を考える【東京建物株式会社】

「マンションの未来を考える」では、マンションを取り巻く環境について、現在から少し先の未来、さらに10年、20年先の未来の姿について、マンションに関わっていただいている様々な業界、業種の皆様から、多角的に語っていただこうと思っております。第四回目は東京建物株式会社 住宅事業企画部の春田新一部長、同部マーケティンググループの宮川昌浩課長(以下敬称略)にお話を伺いました。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
マンションの「3つの老い」
――建物老朽化、居住者高齢化、管理員高齢化といったマンションの「3つの老い」は、すでに直面している課題です。人口減少・高齢化の中、総合不動産会社としてこの課題をどのように捉えていますか。
建設業界の高齢化・人手不足
春田:今挙がった「3つの老い」のほか、建設業界の高齢化・人手不足という課題を先に触れておきたいと思います。当社が直接雇用するわけではありませんが、建設業界の高齢化・人手不足も現時点でマンションの施工に影響を与えており、今後さらに大きくなってくる恐れがあります。
建物老朽化、旧耐震マンションをどうしていくか
春田:建物老朽化に関しまして、旧耐震マンションをどうしていくかはデベロッパーにとっても重要な課題と認識しています。当社は建て替えをソリューションのひとつとして提供しており、強みを生かせる分野です。古いものを新しくするだけでなく、余っていた容積を活用して延床面積を拡大し、より多くの方にお住まいいただける、建物の省エネ性能が向上して環境負荷を低減できるという点でも、建て替えの社会的意義は大きいと考えています。ただ、いずれは建て替えをせずに長くお住まいいただけるようなソリューションを提供することも求められるであろうと思います。具体的にはリノベーションですが、床や壁を新しくするだけでなく、エレベーターを新設したりバリアフリーにしたりと、長い期間を快適に住むことのできるリノベーションが必要です。現状ではそれが難しいため、建て替えの選択肢がとられている側面はありますが、社会的なニーズに応えるという意味では必要なことです。
居住者高齢化、合意形成の難しさ
春田:次に居住者の高齢化について申し上げますと、通常、管理組合では、建物の管理や修繕、建て替えといった高度な判断をすべて居住者の方にお任せするのが基本で、簡単な組織運営ではありません。この運営が未来永劫続いていくかというと、正直なところ難しいと感じています。これまでは、マンションに住んでいる方の多くが一次取得で、小さなお子さんがいて、だんだん成長していく、といったような近しい背景を互いに持っていたと思います。そういったかつての状況であれば、組合内での合意形成もしやすいのかもしれませんが、長い時間が経つと当然ながら居住者の方の入れ替わりがありますので、合意形成は難しくなっていくでしょう。昨今取り上げられている第三者管理が、唯一の解決策と言っていいのかまだ分かりませんし、マンションを提供する側として自分事と捉えていかなくてはなりません。
管理員高齢化、管理の複雑化と人手不足
春田:最後に管理員の高齢化ですが、やはり人手不足の状況があり、その上管理自体が複雑化しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)による管理の効率化を推し進めることはもちろんですが、それ以外の抜本的な解決策も必要です。我々デベロッパーだけではなく、居住者の方と一緒に、新しい仕組みをつくっていかなくてはと感じています。
旧耐震基準マンションの建て替えの課題
宮川:旧耐震基準(建築確認日が1981年5月31日以前)で建てられたマンションは、耐震性能への不安をはじめ、深刻な問題を抱えている事例が少なくありません。建て替えはそうした事例に対する有効な解決策であり、当社が注力する分野ですが、どんな事業者でもお手伝いできるものではないと思います。住まいというライフラインに直接関わることですから、専門的な知識やノウハウ、実績が大きく影響してきます。
春田:権利者(住戸所有者)の方から選んでいただいたおかげで、当社は早くからマンション建て替えの実績を積み上げてきました。建て替えは共同事業ですから、権利者の方と当社はパートナーなのです。財務基盤が脆弱であったり、自社の利益ばかり優先したりするデベロッパーは、パートナーに選ばれません。当社が選ばれてきた背景には、権利者の方にとっての利益や要望を踏まえながら建て替え事業を進めてきた実績があり、さらに、これからもその姿勢を続けてくれるだろうという期待を持っていただけたことなどがあるのだと思っています。また、「Brillia」のブランド力も貢献していると考えています。権利者の方にとってマンションは資産でもありますから、やはり価値のあるマンションをお求めになる意向が強いです。
法整備への課題
――マンション建て替え事業を進めるにあたり、課題と思うことはありますか。
春田:政策的な仕組みができあがっていないという一面はあると思います。今後の区分所有法の改正によって建て替えの組合決議要件の緩和が予定されていますが、日本全国の老朽マンションの多くは、補助金など何らかの支援がないと建て替えることができない状態にあります。もともと容積に余剰があったり、都心の一等地にあったりと、資金面をクリアできるマンションは建て替えが進んでいますが、そうではないマンションをどうするかを考えなくてはなりません。国からのサポートが必ず必要になってくると思います。
さらに、建て替えの進め方について法整備がされていない部分や、区分所有法とマンション建替円滑化法との齟齬が出ている部分など、ほかにもあるはずです。先ほど述べた資金面とともに、こういったテクニカルな面も、いずれ大きな壁となるでしょう。デベロッパーとしては、法整備に対して国へ声を上げ続けていくことが大切だと考えます。
石神井公園団地の建て替え(Brillia City 石神井公園 ATLAS)の事例
――東京都練馬区での石神井公園団地の建て替え(Brillia City 石神井公園 ATLAS)では、権利者の多くが建て替え後も住み続ける選択をしたと伺いました。
春田:権利者の方と一緒に建て替えを進めていこうという意識で、さまざまな取り組みをしました。例えば、建物の解体工事を一つのイベントとして企画したり、新しいマンションの販売センター内に交流スペースをつくったりしました。団地内にあった集会所が建て替えによりなくなってしまうので、権利者の方が集まることのできる場を継続して提供しようと考えたのです。
宮川:やはり地域に愛着があって、住み慣れた環境にいたいという権利者の方が多かったのだと思いますが、それでも、新しくできる建物の良さを感じていただけないと、別へ移ることもあります。そういう意味では、もともとの団地の良さを継承したつくりなどが貢献したのでしょう。石神井公園団地は敷地をゆったり使い、全棟が南向きという特徴がありました。建て替え後のマンションも、その良さを受け継いでいます。建て替えに反対される方、不安を感じる方、「これから何十年も住まないので建て替えは必要ない」と言うご高齢の方、当然ながらさまざまな方がいます。合意形成をスムーズにするためにも、権利者の方に寄り添った計画が必要です。建て替えは非常に時間のかかる事業ですが、当社の担当者は権利者の方と顔を合わせて、地域に入り込み、丁寧に事業を進めていたと思います。
ZEHや防災への取り組み
――次に、ZEHや防災への取り組みについて教えてください。
春田:当社は原則として、分譲・賃貸問わず新築するすべてのマンションでZEHを開発、標準化しようという方針を掲げています。ただ、ZEHと言っても具体的なイメージがお客様には湧きにくいと思いますので、映像などビジュアルツールをご用意し、「Brillia Gallery 新宿」などでお示ししています。

「Brillia Gallery 新宿」受付
宮川:以前よりお客様にZEHが浸透してきた実感はあります。当社では2019年に初めてZEHマンション「Brillia 弦巻」を竣工しましたが、当時はお客様への訴求ポイントとしては弱かった気がします。しかしその後、ローン控除など税制面が整ってきましたので、そういった点を含めてアピールしていきたいと考えています。「Brillia 弦巻」の入居から約1年半後にとったアンケートでは、ZEHマンションを再購入したいと思った方が8割以上もいらっしゃいましたので、住んでからその性能の良さを実感いただけると思います。
春田:防災に関しては、ハード面の整備よりも販売した後、管理組合や理事会へ防災の必要性を呼び掛けていくことが大切だと考えています。防災のためにするべきことに気付いていただけるような取り組みをご提案しています。
「脱炭素社会の促進」「循環型社会の促進」をマンションの視点から
――販売した後の取り組みとして、「すてないくらしプロジェクト」もあります。
春田:環境対策は「脱炭素社会の促進」「循環型社会の促進」という2つの大きな目標を掲げて、社内でプロジェクトチームをつくり、力を入れています。「脱炭素社会の促進」では、先に述べたZEHマンションをはじめハード面での取り組みが中心となっています。一方で「循環型社会の促進」に向けては、ソフト面の取り組みが主かと思いますが、何かできることはないかと考え、「すてないくらしプロジェクト」が始まりました。具体的には廃油と古着の回収を行います。どちらも捨てるのに困ることが多いものかと思いますので、参加される方のメリットが分かりやすいです。今後、広く展開していく予定です。
このほか、通いたくなるゴミ置き場を目指して「GOMMY」の採用も進めています。一般的には、ゴミ置き場は長居したくない場所なので、ゴミの分別もきちんとされず、汚れてしまってもっと行きたくない場所になる…こうした悪循環が起きます。そこで、居室と同じ温かみのある色味の照明とする、ピクトグラムを多用するなど、空間デザインによってゴミ置き場に対する意識を変えようというものです。ゴミ置き場に手間とお金をかけてつくり込むことは、住んでからのことを考えるととても大事だと考えています。

GOMMY採用事例(Brilliia西国立)
都市開発×マンションの未来
「Brillia Tower 池袋」からみる「マンション×○○」
――豊島区庁舎一体型の「Brillia Tower 池袋」のような、新しい「マンション×○○」の形で、今後他に考えられるものはありますでしょうか?
春田:「Brillia Tower 池袋」のような、全く新しい事例はそうそう出てこないかと思いますが、今年5月下旬から入居を開始した大阪市北区の「Brillia Tower 堂島」はホテルとの一体型であり、なかなかない事例だと思います。かつ、世界有数のラグジュアリーホテル「フォーシーズンズホテル」が入る超高層複合タワーは日本初です。

「Brillia Tower 堂島」と「フォーシーズンズホテル」が一体となった「ONE DOJIMA PROJECT」外観/撮影:ナカサアンドパートナーズ
宮川:かつての豊島区庁舎もそうでしたが、自治体の施設は防災拠点として重要な役割を持っているにも関わらず、多くが老朽化しています。施設の更新にあたり、交通利便性の高い立地へ移転したり、防災・耐震性能を高めたりといったニーズがあります。当社が参画している東京都葛飾区の立石駅北口地区第一種市街地再開発事業と、東京都江戸川区の船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業では、いずれも駅前へ区庁舎を移転整備するとともに、同じ施行区域内にマンションなどが整備されます。区庁舎を新たにつくるには大きな資金が必要ですから、我々デベロッパーと共同することで事業が進みやすくなります。
春田:都心部を中心にさまざまなエリアで再開発を手掛けていますので、事業を進めていく中で再開発建物の一部を住宅に、といった話は他にも出てきています。土地の最有効化を考えたとき、現状ではマンションが選択肢の上位に挙がります。今後もそういった事例が出てくるでしょう。
東京建物×マンションの未来
――最後に、マンションの未来像について伺います。住まいの中でマンションは今後どのような位置づけになっていくでしょうか。また、都市づくりの中でマンションはどのような役割を果たすべきだとお考えでしょうか。
春田:やはり人間は、便利さをどんどん追求していくものなので、住まいで言うと快適で心地よい住まいを目指していくのだと思います。その行きつく先がマンションだと我々は考えています。利便性の高い都市部で土地を高度に利用して、たくさんの方に快適に住んでいただくための手法がマンションであり、それはこれからも変わらないでしょう。都市部と言うのは東京だけでなく、地方であれば地方の中核都市のことを指します。コロナ禍で人口の移動はありましたが、今は都心回帰が進んでいる状況ですので、マンションが住まいの中で中心的な役割を果たしていくと思います。広いファミリータイプ、コンパクトタイプ、価格が手ごろなもの、高級志向のもの、さまざまなマンションを求める方がいらっしゃいますので、当社はそれぞれに応じた住まいを提供していきます。建て替え・再開発事業は、やはり都心部で今後ニーズが一層高まるでしょう。マンションだったものをマンションに建て替えるだけでなく、別の用途だったものをマンションへ建て替える事例も増えると思います。最近は、オフィスと一体型のマンションが出始めていますが、職住近接の最たる事例ですよね。オフィス街だったところにマンションができるように、都市のあらゆるところに住まいがあって良いと考えます。当社としては、さまざまな開発事業で住まいを提供していくと思います。
宮川:これまでのマンション建て替え事業では、建て替え後のマンションへ新たに住まわれるのは30代、40代の子育て世代が多くなっています。建て替え以前は長くお住まいの高齢の方が中心となっていたところへ、多世代の交流が生まれ、マンションという箱を超えて地域活性化につながる事例を見てきました。より高齢化が進む地方においても、マンションをつくることでそういった交流を生み出すことができるのではないでしょうか。それが、これからのマンションが果たすひとつの役割だと考えます。
ーーーーーーーーーーーー
東京建物は、東京駅前の八重洲や京橋エリアの大規模再開発事業にも携わっています。江戸時代から町人や職人のまちとして栄えたこのエリアで、どのような思いでまちづくりをしているかご担当者にお話を伺ったところ「長年お住まいになっている方や古くからお店を構えている方など、皆様それぞれにこれまで築かれてきた暮らしや生業、歴史、文化等があります。持続的に発展する街としては、そのような土地が持つ歴史・文化を大事にしながら、新しい要素を取り込んでいくことが必要であると考えています。そのため、再開発にあたっては、弊社は一権利者として、他の権利者の皆様方とともにそういった歴史や伝統、文化等を未来に繋いでいくまちづくりを目指しています」とありました。持続可能な開発という観点では、脱炭素に向けた取り組みが代表的な取り組みとしてあげられますが、同社のいう歴史や文化の承継も、都市開発における大事な要素であると改めて認識しました。
<略歴>
春田 新一 氏(写真左)
東京建物株式会社 住宅事業企画部長
大手金融機関に入社後、2004年東京建物入社。2014年企画部関連事業グループグループリーダー。企画部事業開発グループグループリーダー、住宅事業企画部企画グループグループリーダーを経て、2023年住宅事業企画部長(現職)。東京建物入社後は、ゴルフ場事業やグループ会社の経営管理・組織再編・M&A・新規事業開発に携わり、現在は東京建物の分譲マンションや賃貸マンションなどの住宅事業全般に亘って、事業計画策定・推進、マーケティング、ブランディングなどを担当。
宮川 昌浩 氏(写真右)
東京建物株式会社 住宅事業企画部 マーケティンググループ課長
大手住宅販売会社に入社後、2007年東京建物入社。東京建物入社後から現在に至るまで、一貫して住宅分野のマーケティング業務に携わる。長年培ってきた豊富な知識や経験を基に、市場動向やトレンドの把握、案件ごとの価格戦略など、マンション市場全般に精通する。同業他社とのネットワークも広い。

マンション専門調査員
今村 浩一
マンション管理会社にて管理組合の運営支援業務、その後、大手不動産仲介会社にて売買仲介営業に従事し、2016年に東京カンテイに入社後現在に至る。
マンション専門調査員として東京都心部を中心に、埼玉県全域、 名古屋市、札幌市、福岡市、広島市、宇都宮市、高崎市など、延べ15,000棟以上のマンションについて現地/データの二面から調査を行う。
趣味はマンション関連のネットサーフィン、モデルルーム巡り、マンション将来価格予想。夢は歴代住んだマンションの模型を部屋に並べてお酒を飲むこと。

マンション図書館専属ライター
藤谷 有希
建設業界紙記者、建築系書籍の編集業務に従事したのち、2023年東京カンテイ入社。市場調査部・研究員として、市況レポートや会員向け冊子の作成にあたっている。日本経済新聞、『グッド!モーニング』等に掲載・出演実績あり。
休日はおいしい食べ物を目指して街を歩く。スコーンやクッキーを見つけると、とりあえず買ってしまう。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
関連キーワード
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。