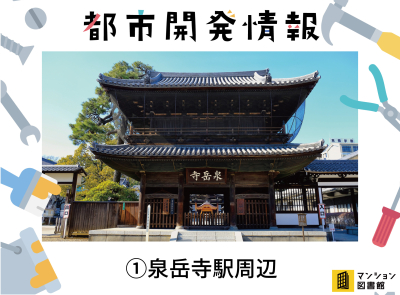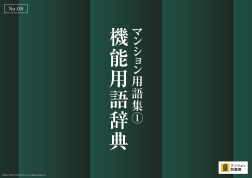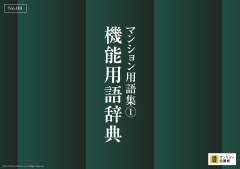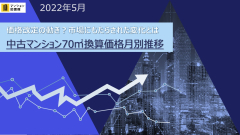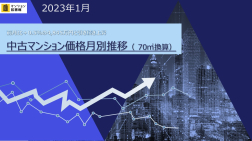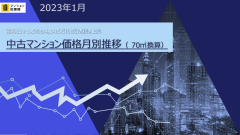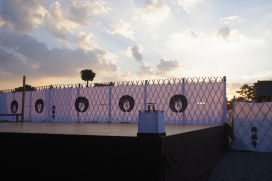全国市況レポート

注目記事
暮らす
更新日:2023.01.20
登録日:2023.01.18
白洲信哉 住まい考2

僕は初孫の定石通り、祖父母たちから随分とかわいがられたようで、週末になると父母方の実家へかわるがわる遊びに行くのが常だった。
マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント
表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」
が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
戦争世代の爺婆さん四人が健在というのは珍しかったし、
文芸評論家小林秀雄(1902~1983)は、
「鎌倉文士」
僕は小学校3年東京から鎌倉へ引っ越すまでは、
きっと子どもの頃から美術館好きなのも、
さて、著作に「ここに来てから、名月で、

文筆家/アートプロデューサー
白洲信哉(しらすしんや)
1965年東京都生まれ。細川護煕元首相の公設秘書を経て、執筆活動に入る。その一方、広く日本文化の普及につとめ、書籍編集、デザイン、展覧会などの文化イベントの制作に携わる。父方の祖父母は、白洲次郎・正子。母方の祖父は文芸評論家の小林秀雄。主な編著書に『骨董あそび』(文藝春秋)、『白洲次郎の青春』(幻冬社)『天才青山二郎の眼』『小林秀雄 美と出会う旅』(新潮社)『白洲家としきたり』(小学館)『かたじけなさに涙こぼるる』(世界文化社)『旅する舌ごころ』(誠文堂新光社)他多数。最新刊に『美を見極める力』(光文社新書)。
公式SNSをフォローすると最新情報が届きます
おすすめ資料 (資料ダウンロード)
マンション図書館の
物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ
(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による
コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正
評価」が見れる! - 新築物件速報など
今後拡張予定の機能も!
会員登録してマンションの
知識を身につけよう!
-
全国の
マンションデータが
検索できる -
すべての
学習コンテンツが
利用ができる -
お気に入り機能で
記事や物件を
管理できる -
情報満載の
お役立ち資料を
ダウンロードできる
関連記事
カテゴリ
当サイトの運営会社である東京カンテイは
「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。
1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。
不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など
3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。